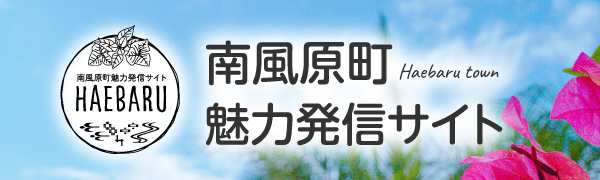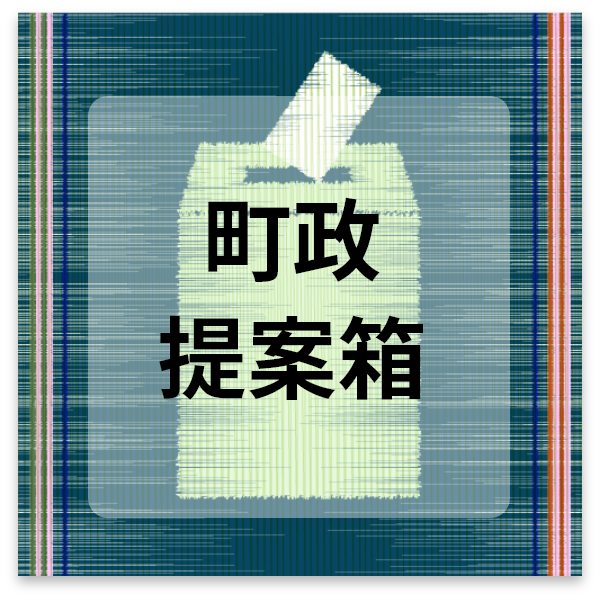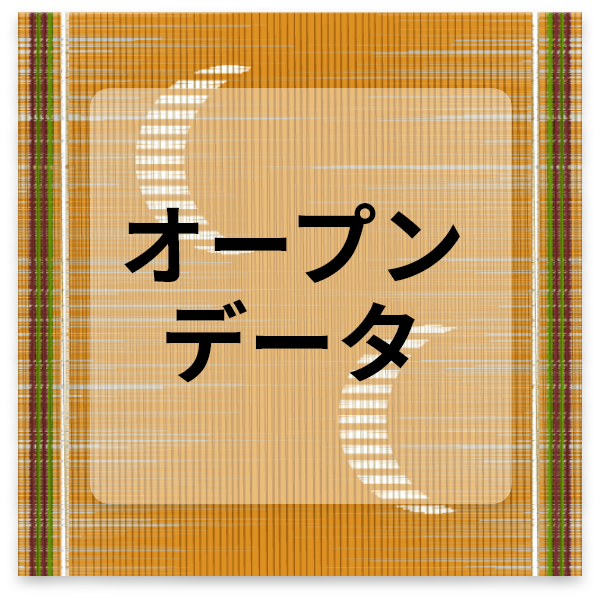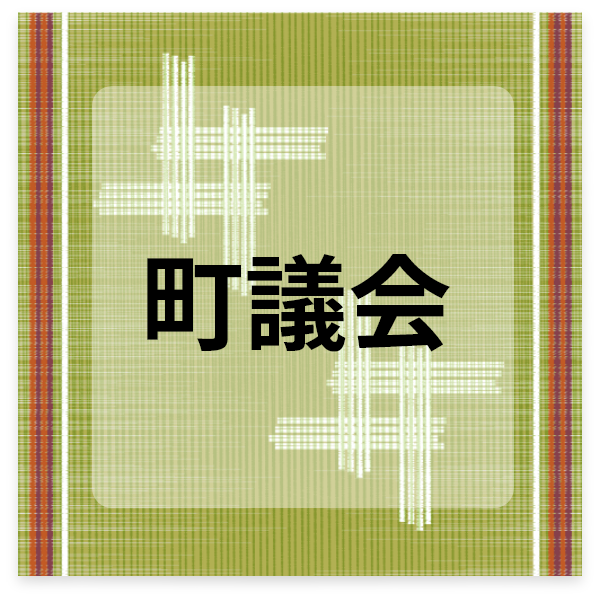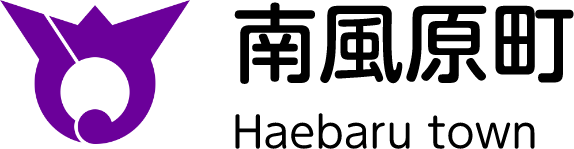本文
平成25年第3回定例会 会議録(第4号-1)
平成25年 (2013年) 第3回 南風原町議会 定例会 第4号 9月26日
検索
| 日程 | 件名 | 一般質問の内容 | |
|---|---|---|---|
| 日程第1 | 会議録署名議員の指名 | - | |
|
日程第2 |
|||
| 宮城寛諄 議員 | |||
| 金城好春 議員 | |||
| 浦崎みゆき 議員 | 答弁 、再質問 | ||
| 大城毅 議員 | |||
会議録
○議長 中村 勝君 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。
開議(午前10時01分)
日程第1.会議録署名議員の指名
○議長 中村 勝君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって1番 玉城光雄議員、2番 照屋仁士議員を指名します。
○議長 中村 勝君 日程第2.一般質問を行います。それでは、通告書のとおり順次発言を許します。4番 花城清文議員。
○4番 花城清文君 おはようございます。方言で言うと「はいさい、ぐすーよー」でしょうか。使わなければ使い切れないので練習したいと思っています。
それでは、通告書のとおり質問しますが、一問ごと質問させてください。1点目です。幼稚園、学校における食物アレルギー対策について伺います。東京都では、小学校児童の食物アレルギーによる悲しい死亡事故がありました。また、本県那覇市では、4件の発症事例があったと新聞は報じていました。それは決して対岸の火事ではありません。なぜなら、義務教育は保護者の選択が優先しません。また幼稚園も学校教育法によって入園拒否できません。そこで次の3点について伺います。(1)エピペン注射は、医療行為から外れ誰でもできるといいます。そのエピペン注射は、持ってくる園児や児童生徒がやるかどうかも含めてお答えください。答弁書もいただいていますが、今日しか見ていませんのでそのとおり質問させてください。(2)町内の保育園では、危機感を持って7月27日に研修会を行っています。町立の保育所や幼稚園、小学校、中学校でも必要だと思いますがその計画はどのようになっていますかお答えください。(3)発症した場合、職員の共通認識が大事であると思います。対象児の個人カード作成も含めマニュアルづくりもして職員への配布も必要だと思うがそれも含めてお答えください。以上、3点について質問します。
○副町長 国吉真章君 それでは、ただいま質問のありました町立保育所、幼稚園、学校における食物アレルギー対策についてお答えします。この質問については、町部局と教育部局両方に係る質問ですので、町部局に係る分については私のほうから、教育部局については教育委員会からお答えをするということでご了承お願いいたします。まず(1)ですが、宮平保育所には現在、エピペン使用をする児童は在園していません。それで保管はないということです。幼稚園には、2園に対象園児が各1名おりますので、保護者から園長が預かって保管しています。小学校は、対象児童がおりません。中学校には、対象生徒が1名おりまして、生徒本人が保管をしています。(2)ですが、宮平保育所では、今年度7月に2名、8月に4名の職員が研修会に参加しています。幼稚園では、1園で職員研修会を開催し、1園では保護者から対処指導を受けています。中学校では、養護教諭が研修会に参加をして学校で職員研修会を開催しています。(3)です。宮平保育所は、現在該当する児童が在園していませんので関係機関との連携は構築していません。幼稚園、中学校は、対象児童生徒の在籍する園、学校で保護者、主治医、消防と連携し救急処置ができる体制が整っております。以上であります。
○4番 花城清文君 それでは、1点目について再質問させてください。まず保育所では保育に欠ける児童が入所していますが、その集団保育になじまない児童は保育所に入所処置をしないということがありました。その法的根拠は何なのか教えてくれますか。保育に欠ける児童しか保育所には入所させていないということでしたね。そうであれば、保育に欠けるが集団保育になじまない幼児は保育所で預からないという法的根拠、それは何なのかということなのです。それを示してください。
それからもう1点は、今後、食物アレルギーを持った子どもあるいは重度の障がいを持った子どもが入所を希望した場合、それはどのように措置するのかそれも併せてお答えください。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。食物アレルギーとは関係なく保育に欠けながら措置できない人がいるかとのご質問ですが、あくまでも保育所ですので集団で保育のできる方です。非常に病弱だとかそういうのはどうしても預かることができないということでございます。
2番目のご質問にもあったように、ある程度の障がいがあって集団保育は可能ですが手助けが必要な児童については障がい児保育ということで加配をして保育している状態でございます。
○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。
○4番 花城清文君 たぶん過去にも重度の障がい、常時介護をしなければならない子どもを入所措置した経緯があるはずです。皆さんが委員会で話をしていましたが、保育に欠ける幼児しか今は入所していないということで、保育に欠けるが集団保育になじまない幼児は入所していないとありました。これは今言ったように過去にも重度の障がいを持った子どもの入所措置をしています。そういったものと今の食物アレルギーの対象児とどのような違いがあるのか。同じように保育に欠ける幼児なのに食物アレルギーがあるということで一方は断る。けれども、保護者あるいは職員が一日中介護しなければならない障がい児保育だと思うが、これも集団保育にあまりなじまないのではないかと思うがそこの違いと言うのか、何を根拠にしているのか。先に言いましたように、法的根拠はありますかと聞いたのも断る理由…
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前10時12分)
再開(午前10時12分)
○議長 中村 勝君 再開します。金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。食物アレルギーについて前回6月に玉城 勇議員からご質問がありまして、そのときにお答えした答弁書で町内11カ所の保育所で64名の食物アレルギーを有する乳幼児がおります。実際、64名は受け入れしていますということですね。ですから、食物アレルギーで入所できないということは今のところないという考えであります。
それから、障がい児保育についても前回の決算認定でもありましたとおり、平成24年度で13名の障がい児を受け入れているということでございます。ですから、集団で保育できる方については、そういうアレルギーや障がいがあっても受け入れはしているということでございます。
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前10時14分)
再開(午前10時14分)
○議長 中村 勝君 再開します。4番 花城清文議員。
○4番 花城清文君 では確認をします。今の部長の答弁は、アレルギーを持っていても入所拒否することはないとのことでした。それで理解していいでしょうか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。先ほどアレルギーがある方、障がいがある方も措置しております。しかし、集団に全くなじめない、アレルギーが多過ぎて給食も出せないとなるともちろん弁当を持ってきてもらえばできるとか、障がいのなかにも相当の重度であればできないということであって、受け入れが十分可能なところは受け入れしますという理解でお願いしたいと思います。
○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。
○4番 花城清文君 では、まず法的根拠をいろいろ検討してみてください。大事な子どもの命に関わることなので、と同時に保育に欠けるという条件も付いてくるので集団保育で本当にこの子がなじむのか、どういう場合はなじむ、どういうものはなじまない、それもやはり詳細検討が必要かと思います。その点では少し検討をお願いしておきます。
2点目にいきます。東京都では死亡事故がありました。新聞報道によると薬は携帯していたがそれが活用できなかったということでした。そこで、町立の保育所、小学校の職員が、せっかく子どもが携帯しているのにその注射を皆できるかどうか、その訓練もしたかどうか答えてください。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 教育委員会部局の関連で、幼稚園、小学校、中学校です。先ほどありましたうように、幼稚園にもその児童がいますし、小学校はいないと報告いたしました。中学校にもエピペンを保有している対象の生徒がいるということでございます。先ほども答弁のなかで申し上げましたように、各学校そういうアレルギー関係でエピペンを必要とする児童生徒は所持をしておりますのでそれについては職員が預かったり、中学校ですとその本人が所持をしております。先生方におきましても幼稚園でも4月にエピペンを所有する園児が入園してくるということがありましたので、早速職員研修をして、また模擬の注射器があるようですのでそれを実際さしてみるようなかたちで講習等を受けているということです。それから1園につきましては、先ほど申し上げましたように消防にお願いをしてやっているということです。それともう1園に関しては、保護者から実際に処置方法を習って、模擬のエピペン注射器で訓練、指導を受けております。それから中学校におきましては、養護教諭が実際に研修を受けてきて先生方と共有して対処するかたちで取り組んでおります。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。宮平保育所では、現在、エピペンを所有している方はおりませんが、先ほど副町長の答弁にもあったように今年7月と8月に6名の職員が研修会に参加しております。その後、保育所内の園内研修と言いますか学習会でお互い情報交換をしながら使えるようにはできていると思っております。次年度も研修会に何名かは参加させたいと思っております。
○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。
○4番 花城清文君 研修、講習に参加して習うことは非常に大事です。問題は、そのエピペン注射を職員ができるかできないかです。東京都のように、せっかく子どもが薬を持っているが処方できなかったということでああいう悲しい事故がありました。その職員ができるかどうか。そしてどういう講習会を受けて、そしてできると言えるのかどうかそれを答えてください。
○議長 中村 勝君 暫時休憩します。
休憩(午前10時20分)
再開(午前10時21分)
○議長 中村 勝君 再開します。金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。研修にも参加し、保育園内でもそういう勉強会をしています。エピペン注射というのは、そんなに難しい注射ではないと、すぐに腿にでも、服の上からでもできるというようなことです。年長の5歳児で、そういう症状がもし確認できたらそれをすぐ打つという講習会を保育所でもしていますので、当然、そのときにはそういう行動をすると考えています。できるという判断ですね。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 先ほど民生部長からもございましたように、教育委員会の幼稚園、中学校の対象児童がいる幼稚園、学校におきましては、そのように研修を受けております。このエピペンというのは、とにかく早く打ちなさいというのが原則のようでございます。それと実質的には本人が打つという対処のようでもございますのでそれも含めて、職員は研修を受けているので打てると、そのエピペンについては対処ができると考えております。
○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。
○4番 花城清文君 小学校の高学年であるとか中学校の生徒だったら自分でできるかもしれません。けれども、幼稚園とか保育所などはいざというとき自分でやることは無理だと思います。職員がやってくれないと、例えば心肺蘇生や人工呼吸についても実際現場ではなかなかできないのが現実です。それからすると皆さんはできるということであるが実際のエピペン注射を取り扱う講習会はやっていないと思います。それもきちんと講習会をやって、職員が十分対応できるようにやらなければ、東京都の二の舞になるかと思います。そういう点で、ぜひその講習会も各学校に任せるのではなくて教育委員会が全現場を網羅してやるべきだと思うのでそれも含めて取り組みをやってもらうようお願いしておきます。
それから3点目にいきます。発症した場合、職員の連携が大事かと思います。そこで先に申しました個人カード、その子にどういう症状がある、そういったものを記した個人カードも必要かと思います。もう1つはマニュアルも大事だと思う。どのような対応をしていく、また園長がどうする、担任がどうする、教頭がどうする、そして他の職員はどうする、そういうマニュアルづくりをやっておかなければ時間との勝負ですから現場は混乱します。そういったことで先にマニュアルはどうですかと質問しましたが答えがなかったので、マニュアルは作ってあるかどうか、そして教育委員会は現場に対してどのように指示をしているのか答えてください。
○議長 中村 勝君 稲福 正学校教育課長。
○学校教育課長 稲福 正君 ただいまの質問にお答えします。自己カード保管については、各園、父兄から医者の診断も含めて園に提出していただいていますので、中学校もそうですがそれを保持し、連絡網等については各幼稚園、中学校とも学校で作られ保管していると、それに基づいて保護者の連絡先、また消防への連絡、病院等の連絡先等も準備されているということで理解しています。
あとはガイドラインですが、これについては平成20年度ですか文部科学省から日本学校保健会の学校のアレルギー疾患についての取組ガイドラインというものが出されておりますので、それを各学校保管しているものと理解しています。以上です。
○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。
○4番 花城清文君 文部科学省が作成したものを各学校が持っているとのことらしいが、現場での職員の対応というものが非常に大事であります。先に言いましたように、本当に時間との勝負ですからさっさとやらなければ救える命も救えないかもしれない。そういったことできちんとしたマニュアルがあって、そして学校現場ではそのマニュアルどおり動けるかどうかそれもやはり大事でしょう。そういう講習と言うのか、それをやるのも大事でしょう。ですから、ぜひ学校現場にきちんとした教育委員会の指導、指示をやって欲しい。やらなければ、万が一それが起こったときに対応が不十分であったとなっては言い訳にしかならない。保護者からもその責任が問われるでしょう。きちんと学校で対応できるようなマニュアル、職員の研修・講習が必要だと思うのでしっかりやってください。お願いしておきます。
次に2点目にいきます。幼稚園の給食用エプロンについて質問します。町長や執行部の皆さんが、町民の声を大事にして町政運営をするのと同じで、私たち議員も町民から声があったら町政に声を届けるのが大事な仕事だと思います。そういったことで質問させてください。児童生徒が使用するエプロンですが古くなって隙間が見えるものやあるいは給食材料がこびり付いて洗っても落ちないものがあるそうです。それを取り替えて欲しいという声があります。また、幼稚園でも去る5月から給食が始まりましたので次の3点について質問します。(1)園児の自立性を教育するため、給食の準備や配膳など子どもたちができるものについてはさせていいのではないかと私は思います。そこで園児は今どういうふうにしているのか聞かせてください。(2)です。エプロンの取り替えについては、行政懇談会でも意見があったと聞いています。保護者からも苦情がありました。現在、その取り替えはどういうふうにしているのか含めて答えてください。(3)幼稚園や学校にあらかじめ予算計上をしておいてエプロンが古くなって替えないといけないとなったときそれぞれ園や学校に任せてはどうか、それも1つの方法だと思うのでそれも含めてお答えください。
○教育長 赤嶺正之君 お答えいたします。幼稚園で給食が始まりましてエプロンも必要じゃないかという趣旨のご質問でございます。今年度から幼稚園で給食が始まり、2園についてはエプロンを保持しておりますので、他の2園につきましても園の要望に応じてまいりたいと考えております。
それから(2)汚れが落ちないエプロン等の取り替えの件でございます。小学校や中学校の古くなったものや汚れたエプロンについては、各小中学校の判断でそのつど予算要求していただきエプロンを取り替えるようにしてまいりたいと考えております。
(3)の取替用エプロンの保管でございますが、現在、取替用エプロンに関しましては、幼稚園や学校から要求がございませんので現段階では予定しておりません。以上でございます。
○4番 花城清文君 やはり清潔感が大事だと思います。教育の現場ですから汚れた物あるいは古くなった物をそのまま着せるのも教育上良くないと思うので、学校現場からそういう要望があればそのつどきちんと対応してください。これで終わります。
では3点目にいきます。しまくとぅばの継承と取組について伺います。私が南風原に転校してきたのが小学校三年生でした。そのとき、いくつもの方言に驚きました。例えば代表的ですが津嘉山の方言であるとか山川の方言、宮平の方言、それぞれ独特の方言があります。南風原町にしかないこれらの方言は、非常に大事だと思っています。そのために永久保存と言いますか保存継承が大事だと、那覇市が今一生懸命取り組んでいますね。そこで次の3点について伺います。(1)語学は年齢が低ければ低いほど習得、上達が早いそうですが、しまくとぅばの指導をどういうふうにしているかお答えください。それから(2)です。中央公民館で既にうちなーぐちの入門講座があるそうで、その取り組みは私も評価します。しかし、その講座というのが時期的、それから回数、時間、いろんな制約、条件があるのかと思っています。そこで中央公民館でやっているその講座はどういうふうにやっているのか、受講者が何名おられるのかどうか含めて聞かせてくれますか。(3)です。地域には独特の訛りがあります。また、読み方というのかそれも違います。そこでそれぞれの地域にある言葉を音声で残して欲しいと思っています。その3点についてお答えください。以上です。
○教育長 赤嶺正之君 しまくとぅばの継承と取組についてのご質問にお答えいたします。(1)ですが、学校から児童生徒へのしまくとぅばの指導についてお願いがあります。そこで学校支援地域本部をとおしまして地域の方々に指導をお願いしておりますが、なかなか引き受け手がなくこれまで実現はいたしておりません。総合学習の老人クラブの皆さんに昔遊びあるいは平和教育で戦争のお話はやっていただいているのですが、しまくとぅばに関しての授業と言いますか指導は引き受ける方がいなくて実現していない状況でございます。しかしながら、今後ともこの実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
それから(2)ですけれども、中央公民館では平成22年度からうちなーぐち入門講座を毎年開催しております。本年度のうちなーぐち入門講座は、受講者17名、9月4日から8回の予定で毎週水曜日に開講している状況でございますけれども、ご質問はたぶんこれが年間をとおしてできないかという趣旨かと思いますし回数や時間等も考慮できないかという議員さんの趣旨だと思うのですけれども、内容、人数等につきましては担当課長より答弁させていただきたいと思います。
それから次の(3)でございますけれども、本町の各字に伝わるしまくとぅばをCDやDVDに保存して活用することは、地域文化を育てる意味でも重要だと考えておりますので町文化協会とも連携を図りながら取り組めないか検討してまいります。これは教育委員会独自で取り組むことは非常にフィールドが広過ぎまして難しいかと思いますので、できるのであれば文化協会などそういった町内の専門の方々にお願いをしていく、あるいは連携して取り組んでいく方法がいいのかと思いますのでそのあたりを検討してまいりたいと考えております。
○4番 花城清文君 1点目から再質問します。役場の職員はどうでしょう。調べたことがありますか。方言を聞くことができるか、言うこと、喋ることができるのか調べたことがありますか。もしなかったら調べてみてはどうでしょうか。役場の職員から方言を使う取り組みをしてみてはどうかと思っています。それについてお答えください。
それから、県の教育庁では各市町村の教育委員会にその普及に取り組むよう通知があったそうです。それを今やりたいがなかなか教える人がいないということです。それもしっかり取り組みをしてください。
それから、那覇市では副読本が作られています。本町はどうでしょうか。そういうものを作る計画がありますか、答えてください。以上。
○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 では、お答えします。役場の職員で実際に方言が使いこなせるかどうか調べたことがあるかについては、そういう調査を具体的にやったことはありません。ただ、通常の職員との事務連絡あるいはやり取りのなかで方言を使う機会もありますし、使える方も何名いるかある程度は分かります。正式な意味でのそういう確認をしたことはないです。今後、町をあげて役場職員が率先してとの話ですが、急な質問ですのでそれについては持ち帰って内部で検討ささせていただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 しまくとぅばの普及に関する通達でございますけれども、文書自体を確認はしておりませんが、多分に以前しまくとぅばの日が制定された時に県からそういったように普及に関して努めるようにというような文書があったかとは考えております。
それから副読本については、4年生の副読本を作っているわけですけれども、これも南風原町内のいろんな状況を紹介するものですから紙面に限りがございまして、そのあたりは副読本制作検討委員会がございますのでそのなかでもどういったふうに取り上げるか検討させてみたいと思っております。現段階、副読本では、しまくとぅばに触れてないと思っております。以上です。
○4番 花城清文君 それでは4番目にいきます。新川の43番地の町道認定です。これも平成24年9月に質問しました。また改めて次の3点を質問します。地権者の協力が得られるよう交渉に努力すると答弁がありました。その交渉の結果を答えてください。(2)議員や自治会長が動かないと町も動かない、では困るわけです。そこで行政についてどのように考えているかお答えください。(3)理解が得られたら認定手続きを取るとの答弁がありました。あれから一年経過しています。どのようになったか答えてください。以上。
○副町長 国吉真章君 では質問事項の4番目にお答えいたします。まず(1)です。新川43番地内にある私道の町道認定については、以前から地権者と交渉を重ねてまいりましたが、町に無償譲渡できないということで処理が済んでいない状況であります。その後、財産管理人に説明するために電話で日程調整を確認したところ、なかなか日程調整がつかず、現時点ではまだ無償譲渡についての確認が取れておりません。今後引き続き交渉を重ねて町道認定に向けて進めてまいりたいと思っています。
(2)ですが、道路行政における固有事務としては、町道や里道開発行為に伴う南風原町に帰属した道路を整備若しくは管理しまたは使用に関する事務を行うことがご指摘のとおり自治体の自治事務だと考えております。
(3)は、(1)で答弁しましたが、土地の権利者や財産管理者の意向が確認できていないことと私道の一部が那覇市にまたがっておりますので区域外道路の認定に係る那覇市の承諾も得る必要があることから、見通しについて現時点では未定であります。以上です。
○4番 花城清文君 しっかりと認定を早めにやってください。お願いしておきます。
5点目です。新川180番地と213番地の町道は、道路冠水します。それも平成23年度12月に質問しました。現場を調査し検討するとの答弁がありました。そこで3点を伺います。現場を調査したかどうか。そしてどのように検討されたかお答えください。(2)地域は集合住宅の開発あるいは、なでしこ保育園や旧公民館から流れてくる雨水の流入が大きいです。しかも住宅が建ち並んできました。その側溝を造るときは畑でした。でも今は住宅が張り付いています。側溝は小さい。それともう1つは、側溝と側溝を接続するとき直角でつないでしまって水の流れを悪くしています。改善が必要です。それから(3)です。住宅が張り付いています。それと南風原バイパスが完成するとますます地域の開発が進みます。そういったことで早めにやって欲しいがどうでしょうか、お答えください。
○副町長 国吉真章君 では、お答えいたします。質問5については、(1)、(2)、(3)関連しますので一括して答弁をいたします。新川地内の180番地、213番地付近の町道の排水溝を確認したところ、昨年に清掃を行ったことにより排水溝内の堆積物はありませんでしたが、ご指摘なされた排水溝断面の狭小箇所や道路勾配による雨水の流速が速いために排水溝に入らず溢れた雨水が213番地付近に流れて道路冠水が起きていると判断されますので、応急対策として213番地付近にグレーチング(蓋)を設置する方法で早急に対処してまいりたいと思います。
○4番 花城清文君 これも早めにね。町道が完成して、ある住宅は自分で土嚢を置いて自己防衛している所があります。そういったことですから早めに対策を講じてください。以上で質問を終わります。
○議長 中村 勝君 暫時休憩します。
休憩(午前10時52分)
再開(午前11時01分)
○議長 中村 勝君 再開します。順次発言を許します。10番 宮城寛諄議員。
〔宮城寛諄議員 登壇〕
○10番 宮城寛諄君 通告書にしたがいまして質問したいと思います。まず、長寿日本一を取り戻すということでの質問です。取り戻すにはどうしたらいいかということです。今年発表された最近の平均寿命、2010年の統計によると沖縄県の女性は1位から3位に転落、男性は26位から30位まで順位を落としたようです。健康長寿県の看板を下ろすだけでは済まない、そういう状況になっている。近い将来、不健康短命県というような看板を掲げるかもしれないと危惧する新聞報道もされておりました。県は「健康おきなわ21」(2010年発表)を作成して健康管理を高めるようにしてきてはいますけれども、平均寿命は伸び悩んだと、県は各界、各層を網羅した県民会議を今年中に設立するそうです。去った9日には推進本部の初会合もあったと聞きました。一人一人の意識を高めて一人一人自分自身の問題として真剣に向き合う、そういうことがこの長寿県を取り戻すには必要だと私は思いますけれども、しかしながらまた県民が健康的に暮らせる環境を作ることが行政の立場として行うことが必要でありますし、高齢者が安心・安全に、健康的に暮らせるように生活の質を高める努力もしなければならないとも思うわけです。当町も健康長寿社会を築こうと頑張っているようですけれども、具体的にはどのような事業、どのような目標を持って行っているのか、その現状はどうなっているのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○副町長 国吉真章君 では、(1)にお答えいたします。沖縄県の健康長寿おきなわ復活推進本部は、平均寿命の都道府県順位1位を男女とも奪回し健康長寿延伸の推進に取り組むことを目標に設置されました。本町は、基本目標の1つ、健康で活動的な高齢期を過ごせるまちづくりとして健康づくりの推進、介護予防事業の充実の事業を展開しております。具体的には特定健診の平成24年度の受診率は45パーセントですが、平成29年度は60パーセントを目標としております。また、平成22年度の要介護者は、17パーセントですが、介護予防事業を推進し元気な高齢者を増やして、平成26年度には15.7パーセントを目標としております。現状は町民の健康診査の受診率の向上の推進、その健診結果を保健師、管理栄養士が受診者の家庭訪問をし保健指導を実施しております。また、高齢者が要介護状態に陥らないため一般高齢者介護予防支援通所事業、各字のミニデイサービス、筋力トレーニング教室、高齢者水中運動教室等を実施しております。
○10番 宮城寛諄君 特定健診の数字はあったのですが、ここにも健康診断の向上とか高齢者の介護にならないための字のミニデイサービス、筋力トレーニング等書いてあります。私が質問しているのは、このいろいろな事業をやっていて例えば対象者がどれぐらいいてどれぐらいの方にこれをやってもらおうみたいなところでして、特定健診の場合は対象者がいくらいて何パーセントだと、それに対する例えば指導も何パーセントだと出てはいますが、皆さん方はそのへんの成果をどう考えているのか。将来的に60パーセントだと持っていて、それはもちろん100パーセントやらなければいけないだろうし、無理だとしてもそこに向けての目標をやっていかなければいけない。国のペナルティは60パーセントだとかいろいろあるのですがそれに向けて、また他の事業にしてもそのへんをやって欲しいというものがあるはずなのです。だからそれに対して皆さん方は目標を持っておられると思うのですが、それがどういう状況なのかをお聞きしたいのです。例えば南風原町の保健福祉計画など出されていて、これは平成26年までなのですけれども、それの目標というものがあるのではないですか。現状はどうなのかということなのですけれども、お答えお願いできませんか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。ご質問の具体的目標でございますが、特定健診は40歳から74歳までで、これは国が平成24年度までは65パーセントでした。それをちょっと下げて60パーセント。この60パーセントとは、国の目標でございます。本町も45パーセントでまだまだでございますが県内では良いほうで、国の目標の60パーセントまではぜひやりたいということです。介護予防の老人福祉関係計画のなかでは、17パーセントの方が介護状態にあるものを15.7パーセントにしたいというのが目標でございます。他にも健康南風原21など個別の計画がございまして、そのなかには国の指針どおり糖尿病を10パーセント落とすとかそういうものがございます。県の健康長寿おきなわ復活推進本部のなかにも施策等いくつかございまして、よく言われています20歳から65歳の死亡率が沖縄県は高い、あるいは肥満、メタボが全国でもトップである、それを予防するためには運動、栄養、水分などいろいろあり、健診等を受けてもらい保健師や管理栄養士が個別指導して防げる病気をぜひ防いで重症化させないことに取り組んでいくことが目標でございます。以上です。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 何と言いますか、特定健診がよく言われていつも目標があって分かりやすいところではあるのですけれども、その他の事業でも目標があってやろうということがあるはずです。例えば先ほどの介護の話でもそうなのですが、要介護を15パーセントに減らすとあります。国のほうで要支援1・2を介護保険事業から外すとか、その分は各自治体に任せるとか、そういう案が出ていて次の国会に出そうかという話まで出ているわけです。そういうことを聞いたときに、果たしてその事業が今後続けていけるかと思うわけです。いままでどおりのメニューを皆さん方が町民のためにできるのか。今だったら介護保険で全国一律のサービスを行っているけれども、各自治体に任されると自治体ができるのかという心配があります。今は平成26年まで福祉計画のなかでいろいろやることはあるのですけれども、次の計画を立てるときにどうなのかなと思うのです。ですから、こういう目標を立てるときに、2、3年ではなくて長期的に、特に特定健診だったら10何年かは30パーセント台から44、47パーセントときて、昨年は54パーセントとなっているのですけれども、そういうのはずっと続けていかなければまさに長寿になっていかないのではないかと私は思います。ただ、報告によると南風原町の男性は平均寿命の点では全国で5番目の町みたいですね。それでも81.何歳。女性は50番にも入っていないのですがその女性よりもずっと下にはなるのだけれども、それでも全国で5番目となっていますが、それを将来的に続けられるかどうか難しいところがあるのではないかと思います。ですから、そういう事業を目標を持って、その目標に対してどこまで達成したと、達成していなければ達成するまでどんどん続けていくというようなことをしないと、国の政策が変わってくるとお金がこない、財政が厳しい、ではこの事業は止めようかとなっては非常に困ると私は思うわけです。もちろん先ほども言ったように健康とは個人でやるものではあるのですが、行政が助けられるところはそういった事業をやってくれないと非常に困ると私は思います。ちゃんと目標を持ってやって欲しいと言ったのはそこなのです。
長野県の長寿日本一の村なのか、松川村では特定健診50パーセントを5年以上続けているという話なのですね。それは隣の町の池田町の例をとったと、この池田町も5年前から54パーセントを超えて昨年は65パーセントまで特定健診が上がったということです。それから、いろんな健診の無料化を行うとか検診を安くするとか、当町も今度、一括交付金を利用してでしたかいろんな健診の町民負担を少なくするということも行っていますけれども、そのようなことも含めて事業の一つとして長寿を目指すという目標を持って、これに向かってぜひ頑張って欲しいと思います。そのへんはどういう心構えかお伺いします。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。いくつかありましたけれども、介護保険については要介護が改正される方向が出ている部分があります。その代わり、逆に地域でやる事業を増やすという方針でございます。ですから、介護予防等の事業等も充実強化するようにということになると思います。これについてはまだはっきりしていませんので具体的なことは分かりませんが、そういう方針でございます。
それとお話があったように長野は平成22年度のもので男女とも1位でありまして、南風原町の65歳以上の男性については全国で5位、女性が48市町村の90位タイということです。県全体では男性が大分下がっていますけれども、町としては男性はいいのかなと見ています。そういうことで健康というものは単年度では作れませんので、長期スパンで一般健診含めて特定健診も含めてぜひ健康になるような保健指導及び事業に取り組んでいきたいと考えております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 長寿日本一を取り戻すということでぜひ町長にも答弁をもらいたいのですけれども、南風原町は男子5位、女子は1800市町村のなかでだったかと思いますが90位で、まさに南風原町が日本一を取り戻す。それに対していろんな事業を展開しているわけですけれども、今後ともその事業の質は落とさないと、その目標に向かって頑張っていくと、質はもっと向上させていくことはあっても落とさないということで町長、日本一を取り戻すということでの決意をお願いできませんか。
○議長 中村 勝君 城間俊安町長。
○町長 城間俊安君 議員がおっしゃるとおり、男性においては市町村ごとで全国5位であることは喜ばしいことだと思います。しかしながら、今の食文化について、また町もいろいろな角度から長寿命化、健康のまちを推進するため議員皆さん方も毎日歩こうということで万歩計を持ってもらい、万歩計を持つことで意識的に一歩でも多く歩こうというこの意識を町民皆に感じ取ってもらうような環境を整えていきたいと思っております。そして行政がフォローできるところはフォローしながら、また町民一人一人が動けるようなまちづくり。今は敬老月間でありまして、南風原町で90名いらっしゃるトーカチ訪問をしてみてその皆さん方の声を聞きますと、健康の秘訣、長寿命の秘訣は動いていらっしゃることだということです。畑はなくても自分の屋敷のアタイグァ(家庭菜園)の草むしりをしたり、手足指先を動かしているこの延長線が健康のトーカチを迎えた方々なのかなと、やはり体を動かすことが大事だと、行政が務めていくべきことは継続して進めていきながら、健康の環境も整えていきたいと思っております。議員の皆さん方が頑張っていらっしゃるこの万歩計を活用すれば、その結果如何によっては町民皆にお配りすることを考えてもいいのではないかと、もちろん議員の皆さん方が実績を作ったその延長線で町民にどうするかは検討してみたいと思っております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 議員は互助会から配られたのではなくて、自分たちの金で買っていますので。私も毎日やっていますけれども、日頃から体を動かすことをやっていれば肥満にもならなかっただろうとは思いますがしかし、この万歩計を使ってのウォーキングなど2番目に移りますが、この推進本部でもウォーキングコースを整備するとか公共交通、地産地消などいろいろあるようです。ここにも書いてありますが、僕らもウォーキングするときには陸上競技場を使いますが、ただ陸上競技場は一周回っても640、650メートルで野球場を回っても800メートルぐらいしかないものですから、同じ所をぐるぐる回っているみたいでなかなか難しくて、気分を変えるために漫湖公園に行ってみたり、それから一番多いのが国道507号津嘉山バイパスを歩いています。この2点目の質問で、国道507号バイパスの歩道の草が茂って、先の政権のときだったか公道の草刈りを3回から1回にするとか2回にするとかそういう方針が出てからなのかどうか分かりませんが、国道507号は年に1回刈っているのかどうか疑問に思うぐらいです。今はまだ歩ける所があるのですが、ただ、2人連れがすれ違うことはできないのですね。1人同士でもちょっと立ち止まってどうぞと言わないと草が生えていて難しい。ですからせっかく利用しているこういう所、新たに整備することももちろん必要ですけれども、今あるせっかくあるウォーキングコースを管理していくことが大事ではないかと思います。この状況は以前に町長もお調べになって、写真も撮って県にも申し入れをしてすぐにやってもらったことはあるのですが、どうも1度やると1年ぐらい放ったらかされるという状況があるものですから、沖縄県特有の気候では頻度の高い管理をしてもらいたいと思うのです。そのへんは今どういうふうに対処されているのですか。
○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 ではお答えいたします。町内にある町道、いわゆる町が管理する道路については、すぐやる班を中心にまめに点検をしながらご指摘のウォーキング、歩行の妨げにならないように管理を徹底しているところです。ただ、国あるいは県が管理する道路については、ご指摘のとおり歩道等に雑草が繁茂してウォーキングコースとして不適切な箇所が数多く見られます。これについては、町民の健康増進を図るためにもそれぞれの道路管理者に要請をしてまいりたいと思います。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 ぜひ国・県に要請をして年に1度と言わず頻繁にやって欲しいと思います。南風原町の町道については、頻繁に草刈されているようですので、国・県にもぜひ要請をしていってください。よろしくお願いします。
(3)に、先ほど部長からもあったように65歳未満の死亡率が全国ワーストであると言われています。25パーセント以上も65歳以下の方が亡くなっているということです。その原因として病気もいろいろあるのだけれども、従来から交通事故や自殺などが沖縄県は多いと言われていたのですが、このあいだの報道では沖縄県の自殺が減ったと、大分良くなったとは出ていました。ただそういうのも原因で悪いと言われているわけです。沖縄県では通院診察より入院が多いと言われていました。重症化してから病院に行くというようなところがあるとあるのですけれども、そのへんの原因がどこにあるのかと思うのですね。(4)とつなぐのですが、どうお考えかその点をお聞きしたいと思います。ただそこで、県民所得が一番低いなかでその通院にかける費用がないと、それから健康保険が払えなくて手帳を持っていないと、短期証があったりなかったりということで通院ができないということがあるのではないかと思ったりするのですね。重症化してから病院に運び込まれるということではないのかと思うのですけれども、皆さん方はどう思うかお聞かせください。要するに特定健診で引っ掛かって、あなたは病院へ行ったほうがいいですよと指導されても病院に行く金がないとなればそれはなかなか難しいわけですからそこも原因の1つではないかと思うのですけれども、皆さん方はどうお思いかお伺いします。
○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 では、お答えします。まず(3)ですが、本県における65歳未満の死亡率は、男性がワースト1位です。そして女性が3位。男女とも好ましくない状況です。沖縄県は、外来受診率が低く入院受診率が高くなっており、重症化してから医療受診をするため入院医療費が高額となっています。県内の65歳未満の死亡率は、全国ワーストであることの要因としては、65歳以下の働き盛りの方は仕事を優先し自分の健康事に無関心で、いざとならない限り医療受診をしない。これはご指摘のありました全く同様に分析しています。重症化してから病院に駆け込む例が多く見られると、それが要因だと分析しています。
(4)については、本町の国民健康保険特別会計の平成20年度からの決算状況を見ますと、一般会計からの法定外繰入金、これは給付費のおおむね3パーセントから5パーセントを目途にその上限の5パーセントを繰入金に充ててしても歳入歳出の不足額を翌年度から繰上充用している現状にあります。平成24年度決算では、2億3,847万1,000円の繰上充用額であり、現時点での国保税の引き下げは厳しいと考えています。健康長寿県を取り戻すためには、多くの方が一般健診や特定健診を受診し、病気の早期発見に努め保健指導等を受けることで生活習慣病に起因する糖尿病、高血圧、心疾患、脳梗塞等の発病予防、重症化予防につなげることが重要になってくると考えています。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 今の答弁にあるように、重症化してから病院に駆け込む例が多く見られると、要するにその前の例えば特定健診で注意されても、人間ドックでちょっと引っ掛かってもなかなか行かないという方が多いわけです。ですから、それはなぜなのかということをお聞きしたいのです。沖縄のてーげー主義の県民性なのか。でもそれでは片付けられないことだと僕は思うのです。だからそこがこの保険料の問題ではないのかと、所得の低さではないのかと、全てとは言いませんけれどもこれも1つの要因ではないかと(4)で質問しているのです。この(3)では今そのように見られるということは、副町長も答弁なさったとおりのその要因が何なのか、そこを皆さんはどうお考えですか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。65歳以下のワーストであるということで、実際に他の都道府県に比べて入院のほうが多い。基本的には、初期であれば通って重症化防ぐということですけれども、沖縄県は重症化してから行くものですからすぐ入院となると、南風原町の数字を見ても医療費のなかの6割近くが入院になっております。先ほどもお答えしたとおり、働き盛りの方がなかなか病院に通わないことが数字で表れているということです。それから、生活習慣病は自覚症状があまりないということがありまして、沖縄県の肥満などそれがあって気付かないうちに重症化しているというのが現状だと見ております。それと医療費についてですが、税については赤字ですのでなかなかできない部分と、病院に行って医療費の支払いについては全国3割負担で同じですよね。これについては国の制度ですので全国一律だということです。当然、高額医療制度がありますので所得が少なければ高額医療で還ってくる部分もあるということでございます。医療費については、全国一緒でありますのでどうしようもないことだと考えております。以上でございます。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 ですから重症化しないようにすることで、もちろんそれは本人も気をつけなければいけませんし保健指導だと思うのですけれども、そういった若い人たちが仕事が忙しいということで病院に行かないとか、例えば特定健診の指導でもなかなか会えないという話もお聞きします。そういう意味ではそのへんの指導ができていない、要するに全国的にワーストだということは病気の軽いうちに診察を受け通院して治すというのが少ないということですよね。入院の費用が南風原町は6割近いというこれが全国的にどうなのか分からないのですけれども、ただ、沖縄県は多いと言われていますから南風原町もそういう位置なのかと思います。それを下げるためにもやはり、早期発見、早期治療がどうしても必要だと思うのです。ですから、保険料の問題ではもちろん全3割負担、所得の低い人はそれなりに軽減措置があるのですけれども、それでも払いきれないということはあるはずなのです。国保の現年度の収納率は95パーセントだったか、5パーセント近くは滞納しているわけですね。その原因は皆さん方がよくご存知だと思います。単なる無理解で払っていないのか、生活困窮で払っていないのか分析していませんが、生活困窮で払えず延滞を繰り返している方も多いわけです。ですから、そういう生活の問題から保険料が払えない、手帳がない、病院に行けないということもあるのではないかと思います。国は今度また国保の減免措置の所得をもう少し広げるとか言っていますけれども、それも必要ですが保険料を下げることがもっと必要ではないかと私は思うのです。町は5パーセントをこれまで入れているし、また次年度からも持ってきてやりくりしている状況もあるのでこれ以上引き下げられないとのことで財政面いろいろあると思うのですけれども、そういった努力もすべきではないかと私は思います。国や県へ要請するとか知恵の使いようであって、やるべきことだと思います。またそのへんの要因はぜひもっと詳しく研究しなければいけないと思います。特に特定健診や健康診断、いろんなことで再検査の必要がある人たちがなかなか行かない、通院しないことが一番の問題だと思うのですけれども、その指導の問題では例えば南風原町の保健師の数は意外に多いのではないかと思ったりしましたが、実際に僕らが特定健診を受けて相談を受けるのになかなか時間が合わないときもあるのです。それだけ多いのかとも思ったりしたのですが、指導の面で人数の確保と言うか体制と言いますかそのへんは今万全という感じですか。それともまだまだ足りないという感じですか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。医療費を減らすためにも町民が健康であることが一番大事でありますので、そのためには健診を受けて保健指導でちゃんと摂生や通院してもらうということです。市町村で保健師の数としては、南風原町は低いほうではございません。数字的には少ないほうではないということです。しかし、町の取り組みとして本人に説明をすることを前提に保健指導していますので、特定健診の受診率が上がって指導する数が増えると当然足りなくなるわけです。今45パーセントの特定健診で、健診受診率が上がってきますとどうしてもメタボなど要指導の方が増えてきます。そうすると今言う人たちより保健師を管理栄養士含めてでありますが増やさなければいけないとは思っています。なるべく皆さんに親切に適切な指導ができるように考えていきたいと思っております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 特定健診の受診率が高くなり指導が多くなれば保健師も足りなくなるということですので、十分に対応できるようにやってください。県でも市町村の保健師の数を確保すると今度の推進会議では目標に上がっているようですので、早期発見と言うか重病にならないように対応して欲しいと思います。それから保険税についても私はもっと引き下げるべきだと思うのですが、それも検討としてやって欲しいと思います。
2点目の「非核平和宣言の町」の標柱についてであります。1982年に南風原町が全国で2番目でしたか先駆けて宣言を行ったわけですけれども、そのことを町役場や兼城十字路、それから旧社会福祉センター前などにあって内外にそういうアピールをして、それがどんどん増えて今はほとんどの市町村がその宣言もしているのではないかと思います。南風原町の場合、いろんな工事があって、役場前も兼城十字路も撤去されたことがありますけれども、新たに立てることが必要ではないかと思うのです。南風原町役場は道路はまだですが役場敷地内としては完成なのでしょう。そうではないのですか。ですから早めにやるべきではないかと思います。兼城十字路についても電光掲示板が立っているわけですから、その横にでも立てられる。あの角としてはそれ以上削られることはないと思いますから、そういう所は早めに立てられるのではないかと思うので今後の計画はどのようになっているのかお伺いします。
○副町長 国吉真章君 では、お答えいたします。今質問のありました標柱については、南風原中央線の拡張工事に伴って撤去されました。この標柱の内容については、非核平和宣言の町・琉球絣の里かぼちゃの産地南風原町、そういった町をPRするための内容となっていました。現在、非核平和宣言について表記された看板は、照屋十字路のみとなっています。それで兼城十字路の旧交番跡に電光掲示板を設置していますのでここで非核平和宣言の町の表示をしています。また、町民広場にメディアタワーを設置していますのでこれを有効活用するために観光あるいは物産等のPR用懸垂幕の作製も考えています。そこでその懸垂幕にも非核平和宣言の町南風原町の表示について検討をしてまいります。それ以外に固定式の標柱についても適当な場所があるかどうか確認をして、対応していけるように併せて検討してまいります。
○10番 宮城寛諄君 確かに絣の里かぼちゃの産地というのも書かれていました。だからそれがなくなったのも残念であります。町民広場のメディアタワーの有効活用ということで垂れ幕をとのことですけれども、懸垂垂れ幕は例えば敬老の日や国民の祝日、博覧会などその時々のイベントであってそういった絣やかぼちゃもそうですが平和宣言については固定的にするのがいいのではないかと思うのです。特に町民広場はスペースがそれだけあるわけですから、真ん中でなくても道路から見える所にでもやるべきではないかと思います。固定式について今後場所を確認して検討するとのことですのでぜひ検討して欲しいと思います。この質問のなかにはどことは書いていないのですけれども、南風原町の入口、例えば新川や津嘉山の区画整理地域はこれから公園整備をします。そういう大きな道路が入ってくる所、目立つ所に、ここから南風原町なのだと見せる意味でも非核平和宣言の町、それから絣、かぼちゃ、今は美瓜などいろいろあるようですし観光振興でもPRすることはあるでしょうが少なくともこの非核平和宣言の町については、核兵器を世の中からなくすということでいろいろやっていて2015年には世界での核兵器をなくそうという大会が開かれます。残念ながら日本とアメリカは批准していないようなところがあるのですけれども、非核拡散防止の集まりもあるようですので核兵器をなくそうとPRすることでは早めに場所を検討してやって欲しいと思います。以上、終わります。
○議長 中村 勝君 暫時休憩します。
休憩(午前11時47分)
再開(午後1時01分)
○議長 中村 勝君 再開します。午前に引き続き順次発言を許します。9番 金城好春議員。
○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。
○9番 金城好春君 今日初めての質問ですので、JAと協議したいとのお話でした。これから協議をしてぜひ良い方向にもっていってもらいたいと要望して、この問題は終わります。
2番目にいきます。カンナの花でまちおこしを。(1)カンナの花は多年草で一年間花が咲きます。また、一度植えるとどんどん新しい株が出てきて増やすことも簡単であります。町が音頭を取って、まちぐるみでカンナの花を植え、南風原町をカンナの咲き乱れるまちにすることはできないか。(2)世界中のめずらしいカンナの花を集め、のちのち南風原町でカンナの花まつりを目指すことはできないか。よろしくお願いします。
○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 それでは(1)についてお答えいたします。町道6号線は、字本部の方々によりカンナの花が植栽されたいへん素晴らしい景観になっています。多くのお褒め、そして評価の声も耳にしています。また最近では株分けをしていただいて役場前の交差点からちむぐくる館までの道路にも植栽され、町道が花で彩られ感謝しています。本町では地域や住宅地の緑化について、南風原町みどりとやすらぎのあるまちづくり助成、花壇登録制度等を実施してきていますが、今後はカンナの花も含めて町民等との協働による景観づくりや緑化の仕組の構築等を検討してまいりたいと思います。
(2)についてです。これまで町花・町木コンテストを実施してきていますので、ご提案の花まつりも含め、これも併せて検討してまいりたいと思います。
○9番 金城好春君 幼稚園、小中学校、町の公園、それから町道等にカンナの花を植えてどんどんカンナの花の町らしく増やして欲しい、植えて欲しいのです。どうでしょうか。それから、ふるさと博覧会でいろいろな花の苗を無料配布していますね。そのときにカンナの花の苗を事前に作っておいて無料配布できないものかどうかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 カンナの花を学校関係、公園関係とありますので、学校関係につきましては教育委員会から、公園関係について私からお答えさせていただきたいと思います。今現在、公園はまだそこまでやってはおりませんが、道路関係については一部カンナの花を率先して字本部に植えてもらいましてかなり見事な花が咲いております。それと連動しまして、先ほど副町長からもありましたけれども、役場前の交差点からちむぐくる館向けに町職員がカンナの花を植えております。引き続きそれを私どもも推進していこうと考えております。また、来月10月13日には観光協会のほうで第一団地と町道6号線、津嘉山タクシーの所にカンナの花を植えましょうということで企画しております。また多くの方々の参加も呼び掛けておりますので、議員各位にもご参加をお願いしたいと思います。また、公園関係についても随時管理状況を鑑みながらカンナの花の植栽についても今後検討していきたいと考えております。また、まつり関係でカンナの花を事前に栽培して配布してはどうかというご提案につきまして、たいへん良い提案だと考えております。予算等の絡みもありますけれども、今後のまつりで検討させていただきたいと思っております。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 学校関係、幼小中でカンナの花を植栽してはどうかというようなご質問でございました。先ほどもありましたように町道のカンナは街路の花としてたいへんきれいでございますので、学校のほうも学校と調整して取り組めるように検討してまいりたいと思います。
○議長 中村 勝君 9番 金城好春議員。
○9番 金城好春君 このカンナの花のメリットといたしまして、いったん植えるともう二度と買わなくてもよろしいと、自然と竹の子みたいに株がどんどん増えていくのですね。その株を抜き取って別の所に植えていきます。それから、種もできるのですけれども、種はちょっと時間を要します。でも株を分けると一年ではまた花も咲くのではないかと言われております。そういうことで、50坪でもいいですから畑の一画にこの株を植えておくと、根付いたら最後、どんどん増えていってその株でもって爆発的に増やすことができるというメリットがございます。いつも町道6号線を見ているのですけれども、歩道の植栽は溢れるぐらい株が竹の子みたいに出て、これを字本部の方はどんどん植えたい人に分けているのではないかと思います。それで提案なのですが、今からこの苗づくりに力を入れていただきたいのです。字本部が南風原町の原産地みたいになっていますので、本部の皆さんにこの苗づくりを委託することはできないものかどうか伺いたいと思いますがどうでしょうか。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。カンナの花を南風原町全域に広めるとありましたこの苗づくりを進めていくのが基本ではないかと考えております。議員さんのほうからも提案がありました例えば字本部への委託も含めて、その苗がどういった内容で増産が可能であるか今後検討させていただきたいと思っております。
○議長 中村 勝君 9番 金城好春議員。
○9番 金城好春君 ぜひ町で温度を取っていただいて、商工会あるいは観光協会、PTA、各字・自治会網羅して、このカンナの花の普及をお願いして2番目の質問を終わります。よろしくお願いします。
3番目に移ります。津嘉山北土地区画整理区域内の歩道の整備についてお伺いします。津嘉山北土地区画整理区域内の17街区、18街区、24街区、26街区の通り沿いはほとんど住宅とアパートが建ち並んでいるが、歩道は未整備のままとなっている。早急にアスファルト舗装はできないかお伺いします。よろしくお願いします。
○副町長 国吉真章君 お答えいたします。ご質問の箇所については、8月13日に工事請負契約を終えて現在12月末の完了に向けて工事進捗中であります。
○9番 金城好春君 ありがとうございました。ぜひ立派な舗装をしていただいて、地元住民の要望に応えていただきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
○議長 中村 勝君 暫時休憩します。
休憩(午後1時14分)
再開(午後1時14分)
お問い合わせ
議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp