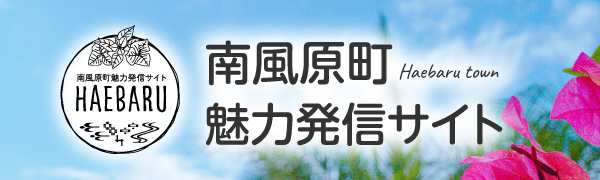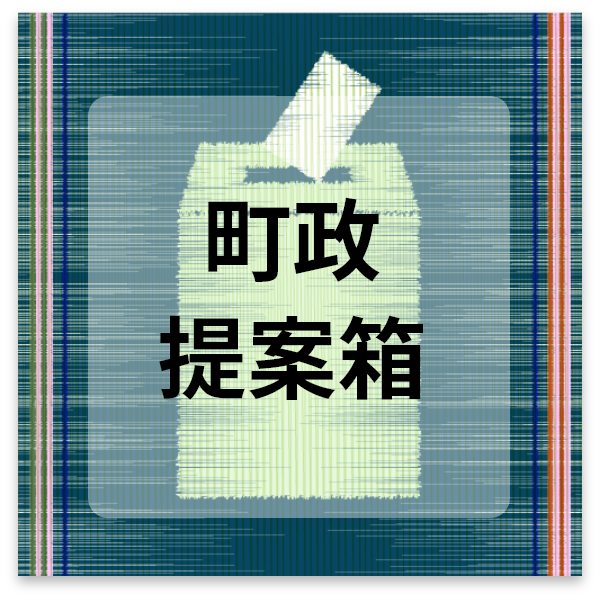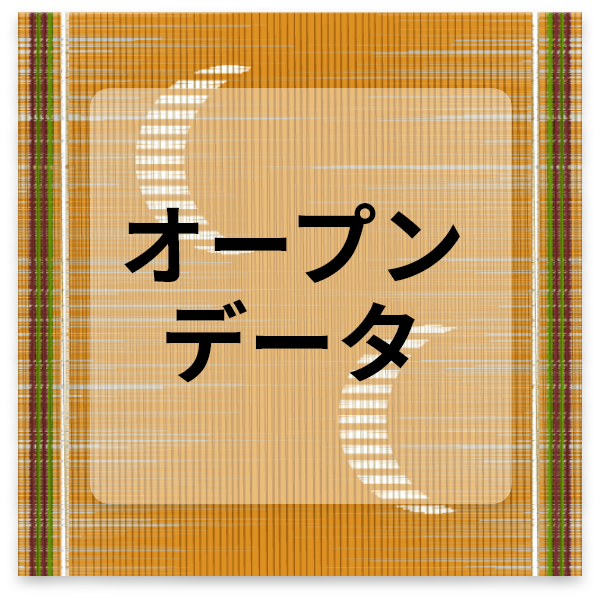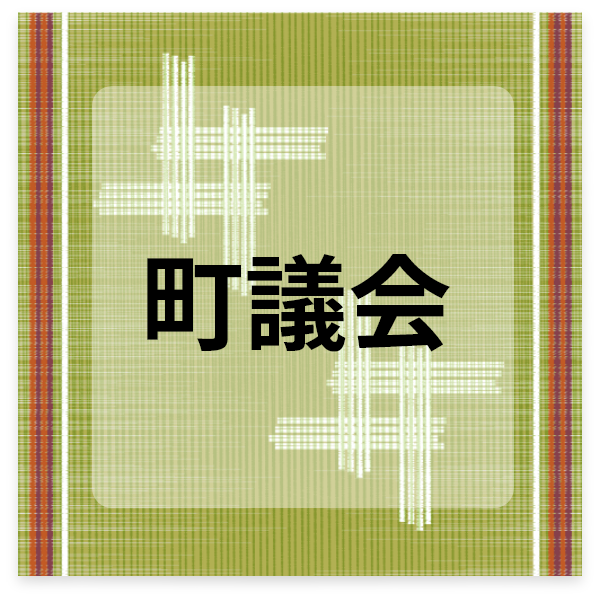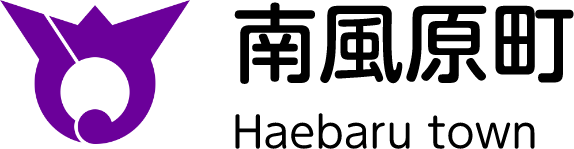本文
平成26年第4回定例会 会議録(第3号-1)
平成26年 (2014年) 第4回 南風原町議会 定例会 第3号 12月17日
一覧
| 日程 | 件名 | |
|---|---|---|
| 日程第1 | 会議録署名議員の指名 | |
|
日程第2 |
質問議員名 | 質問内容 | |
|---|---|---|---|
| 赤嶺奈津江 | |||
| 大城勝 | |||
| 宮城寛諄 | |||
| 金城好春 | 答弁 、再質問 | ||
| 上原喜代子 | |||
会議録
○議長 宮城清政君 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでございます。
開議(午前10時01分)
○議長 宮城清政君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって8番 花城清文議員、9番 赤嶺雅和議員を指名します。
○議長 宮城清政君 日程第2.一般質問を行います。それでは、通告書のとおり順次発言を許します。6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん 一般質問2日目、一番手で質問させていただきたいと思います。大きい問いを1つずつ質問させていただいて、答弁をいただいたのち、1問1答でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
1.発達障がい児支援について問う(1)発達障がい児支援・特別支援教育支援員について具体的にどのような問題があるのか。(2)特別支援教育支援員の人員確保についての課題は何か。よろしくお願いします。
○教育長 赤嶺正之君 おはようございます。それでは、奈津江議員の質問事項1.発達障がい児支援についてのご質問にお答えします。(1)でございますが、特別支援教育支援員は、幼小中併せて39名で、担任と支援体制の確認や特別支援教育コーディネーターと研修等を行い、幼児・児童生徒の安全確保や声かけ等、個人に応じた支援を行っています。課題といたしましては、支援員の人員確保が課題となっております。
(2)でございますが、特別支援教育支援員が年々増えている状況であり、支援員の確保が厳しくなってくると思われます。発達障がいは、比較的新しく概念付けられた障がいの総称を言い、児童生徒によって支援の方法が違います。研修等で支援員の質の向上に努めておりますが、児童生徒の個性により援助の方法が違います。また、どこまでが支援の範囲なのか個々によってばらばらですので、マニュアル化できないところが課題でもございます。以上です。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。前回の議会のなかでも浦崎みゆき議員から同様な質問がありまして、人員確保が大きな課題になっているということで今回私のほうでも取り上げさせていただきました。私も1期目、最初に発達障がい児支援の質問をさせていただいて、いろいろ課題があるのではないかということで一般質問に取り上げておりますけれども、やはりマンパワーが必要な支援ですので、良い人材、また教育が必要だということでずっと訴えております。この支援員の継続率と言いますか、3年が基準だと思いますけれども、3年たったあとの状況を確認したいと思います。どうなっていますでしょうか。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 赤嶺議員の再質問についてお答えします。特別支援教育の支援員につきまして3年経過後にはどうなりますかという質問でございました。非常勤につきましては、基本的には1年の賃金職員でございますが、特別支援につきましては継続して3年まではその勤務に就いていただいております。その後は終わっていただくかたちになっています。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。3年たつと終わっていただくとの答弁でしたけれども、人員確保が課題であれば同じ学校で3年になってしまえば違う学校でといった対応はできないのか。また、障がいの度合いによって支援員の方に慣れる、慣れない、愛情の問題等もあると聞いています。交替して途中で人員が変わった事例もあったと聞いていますけれども、そういった点で継続雇用と言いますか支援に就いてもらうよう検討されたことはないでしょうか。
○議長 宮城清政君 教育長。
○教育長 赤嶺正之君 ただいまのご質問にお答えします。ご指摘のとおり、やはり特別支援教育に関しましては支援員を短期間で交替というのは非常に難しいところで、現実的にそういうことがございます。先ほど部長からもございますように、基本的に賃金職員の場合は1年間という制度、法律的なことがございますので、1年間で交替となるのですけれども、相手が児童生徒でございますから、だいたい1年生が3年生になるぐらいまではある程度成長の度合いが分かるということがございますので、3年までは継続させてもらいたいということで、制度的なものもありますけれどもなんとか継続しております。では、3年ないし5年まで雇用できる嘱託職員でどうかという考え方もあったのですけれども、そうなりますとこれも制度的に勤務時間が6時間という制限もございまして、やはりフルタイム7時間15分の賃金職員のほうがいいのかと考えましてそういった体制で臨んでいるわけでございます。教育委員会としては、まさに議員ご指摘のとおり、できれば長期間雇用して子どもたちに対応できるように、そしてまたそれで経験が蓄積していきますのでその人のノウハウも広がっていくと、そういうこともございますので何とかしたいのですが、現段階では現実的に難しいところがございます。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。教育委員会としても同様な悩みがあるということで伺いました。やはり制度的な問題等もあるとのことですので、どういう実態なのか他の自治体等を調べていただいて、また連携してこのシステムの改正等を訴えることも必要だと思います。これまでそういった活動、動きをやったことがあるかどうかお伺いしたいと思います。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 ただいまの特別支援員関連の雇用形態と言いますか、嘱託か賃金かというようなところの状況は、与那原町、西原町、南城市、八重瀬町、豊見城市、他市町村の例としては、嘱託と賃金の雇用形態がございます。そのように調べてはございます。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。賃金かどうか調べはやったとのことですけれども、ではこのシステムで問題があるということで、この子どもたちと接する支援員の確保とか継続支援が必要であるといった問題点についての話し合い、研究、そういった場はないのでしょうか。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 再質問にお答えします。先ほど申し上げましたのは、状況を調べるといったデータを持っているということで、他の自治体とその件についての研究会は今のところもってございません。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん これまで賃金など待遇面での情報交換はあったとのことですが、どの自治体も同じ課題を持っていると思います。特に近年は発達障がいと認定される子が増えてきていますので、できましたらそういった情報交換の場をもって、どういった支援が必要なのかを国と県と調整しながら、現場から要請することも必要だと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。
○議長 宮城清政君 教育長。
○教育長 赤嶺正之君 お答えいたします。議員ご指摘のとおり、そういった状況までいければ各自治体が助かると思うのですけれども、特別支援に関しましては現段階市町村任せの部分がございまして、なんとか県に音頭を取っていただければという気はいたします。特別支援教育とは、支援員にウエイトが重くなってきていますけれども、本来は学級担任の先生あるいはまた各学校に配置されています特別支援教育コーディネーターの先生が一緒になってどう対応していこうかと決めて、それを教育活動のなかで実施していくというものでございまして、それになかなか手が届かない部分があるのを支援員がフォローしていくのが本来の姿でございます。これが最近はほとんど支援員に負担がかかってきております。本来でしたら、先ほど言いましたように学級担任と各学校の特別支援教育コーディネーターさんは県の教職員でございますのでそういった先生が連携を取ってどういったふうにやっていこうとしていただければ助かるのですけれども、なかなかそれ以外の部分に時間が割かれて難しいようです。そういった部分をわれわれは教育長会あたりで県へ要請してまいりたいと考えております。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。現場は現場で結構大変だと聞いていますし、また実際親御さんが発達障がいと認めていなくて支援員がつかない事例もやはりあります。実際、支援員がついている子以外の気になる子がいて、反対にその子に手がかかるという実態もあると聞いていますし、私たちも読み聞かせで入るときに実際それを体感することもあります。そのなかで先生方の負担というのは、やはり支援員だけではなく学校の先生方も負担に思っているところもあると思います。昨日の一般質問で大宜見洋文議員から行事が負担になっていないかというような質問もありましたけれども、それ自体、先生方の本来の業務でない部分もかなり負担してくれているところもあります。実際、運動会の準備期間に陸上競技大会が何件か、町主催でないにしても県大会であったり地区大会であったり、そういったところも見てくれているのが現状です。やはり学力向上というところでも放課後がんばってくれたり、それだけに係わるのではなくてそういった発達障がい児にもかかわっていかなければいけないですし、またなかには問題行動ということで相談を受けたりということもあります。現状では、学校の先生方の負担はかなりのものだと思いますので、町が先頭を切ってこういう課題はないですか、こういうことをやってはどうでしょうかということで提案することも大事だと思います。やはり負担というところで、現状ではかなり厳しいと思いますので、ぜひ町が先頭を切って現場の相談も受けて、また保護者の方の相談も受けて、障がい児だけではなく子どもたちがすくすくと育つ環境を作っていただきたいと思います。また、質問に戻りますけれども、人員確保が課題とありましたけれども、この継続雇用以外にも待遇面での問題もあるのではないかと思いますが、前に時給等の一般質問をさせていただきましたけれども、それからの見直しであったり検討されたかどうかお伺いしたいと思います。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 特別支援教育支援員の待遇面として、その待遇には時間であったり報酬・賃金であったりあります。賃金につきましては、先ほど隣市町村の状況ということで調査をしてある程度の数字が出ております。そのなかで南風原町より高い賃金、時給であったり、低い賃金であったりございます。議員から前回もありましたように、そういった賃金体系が安いのではないかというニュアンスの指摘がございましたので、確認をしまして、内部で報酬的にはどうであろうか検討いたしましたが、総体的に町全体として他の賃金職員の賃金体系と同等に推移しているということであります。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。他と比べてそのままにしているということで、町の職員と比べてということだと思いますけれども、実際に賃金とか待遇面を見て辞められた方がいるかどうか。全部がその理由ではないと思いますけれども、それを理由の1つに挙げた方がいるかどうかお伺いしたいと思います。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 支援員の途中退職した方はいらっしゃいます。それが待遇面、賃金が安いからなのかどうか把握してございません。一身上の都合と提出されていますので、そういう待遇面で辞められたかどうかについては把握してございません。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。その確認をされていない、ほとんどが一身上の都合だとのことですけれども、他で同じような内容と言いますか障がい関係で時給が100円以上変わったのでそちらに移りますという方が実際いらっしゃいました。子どもたちと別れるのはつらいけれども、やはり生活を考えると厳しいのでということでおっしゃった方がいらっしゃいましたし、同じような悩みを持っている方がいるとも聞いています。また、高学年になってくると体力が要るということで、特に男の子を支援する場合、女性の方では厳しいところもあると聞いています。そういった場合、男性が非常勤、臨時職員で就く場合には生活の問題も出てきますので、ずっと付いていないといけない、ずっとこの人でなければいけないということでもないのかもしれないですけれども、支援員の方にお願いしなければならないといったとき、やはり子どもたちの心を考えたり保護者、先生方の負担を考えるときには、そういった待遇面も考えるべきではないかと思います。また、座っての事務も大変であるかもしれませんが、身体を使って心を使ってという部分でも、仕事によって賃金は変わるものではないかと思うのですけれども、その点どのようにお考えでしょうか。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 議員から質問がございました。途中で100円高い所に行ったということがございます。隣町村を調べてそのぐらいの差がある所もございます。特別支援の業務につきましては、どれが負担と言いますかきついかきつくないかという視点では、総体的比較はできないと思いますが、支援員の場合は先生方を補佐するということでありますので、一般職の業務と同等なのかという比較がございます。総体的に見て南風原町の賃金は760円で設定してございますが、そのように包含したかたちでの賃金体系になっています。各職種によって、見方によって違ってくると思いますけれども、それは町全体のバランス的なことも考えてそういう設定で進んでいるということです。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。私も一般事務職、総合事務職で臨時職員として入られている職種が楽だということではないのですけれども、やはり現場にいて子どもたちの度合いに応じて相談事だったりいろんなことを抱えるなかでは普通の事務職とは若干違うのかと、先生には言えないけれども相談員には言えるというところで保護者だったり子どもたちの受ける部分は大きいのかなとそういう質問をさせていただきました。また、持ち帰りで考えることも多いと聞きます。この子にとってどれがいいのだろう、叱ることがいいのだろうか、どういった対応をしていけばいいのだろうかというところでかなり悩んだり勉強したりも多いと聞いています。継続して支援するなかでかなりの負担となって途中で辞められた方もいると聞いていますので、通常の、ただの補佐ではないという部分で比重は大きいのではないかというところです。また、先ほど言いましたように、支援員がついていない子どもたちに対しても実際対応しているところもありますので、学校に配置されてこの子にというセッティングはあるかもしれませんが、全体的に見ているところもあると、全体的に手がかかる子には担当の子以外でも対応していると聞いています。またそういった子が何人かいるとクラスの雰囲気にもかかわってきますので、現場の状況を把握してその待遇面、人員配置、人員確保をやっていただきたいと思います。今回、人管があって給与の改定もありましたけれども、また、沖縄県の時給の改正もあって今は677円が最低だと思います。しばらく町のほうは変わっていないですけれども。近隣市町村で時給や賃金の差があるのかないのか調査をされたかどうか聞きたいと思うのですが、どうでしょうか。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○議長 宮城清政君 支援員の賃金の面で差があるのかというご質問でございます。調べた状況を年額で申し上げます。時間も若干嘱託であったりそういったことで違ってきますが、町で年額11カ月でございますので、138万4,150円。与那原町では161万2,800円。豊見城あたりも167万9,000円ぐらいですね。そのように年額でも差があります。低いほうでは111万6,000円ぐらいの所もございます。時給で申し上げますと、町が760円でございますので、隣の与那原町では960円となっています。南城市で744円、八重瀬町で750円、豊見城市で860円となってございます。そういう状況になっています。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。低い所もあるということで、先ほどおっしゃっていましたが、隣市町村はほとんど南風原より高い賃金をもらっているということですね。前回も言いましたけれども、南風原町で人員を育てて他市町村に流れているのではないか、そういったところもあると思います。実際に、民間でも南風原町には福祉施設がありますので、なかにはここで3年ぐらい経験して、時給には幅があるそうですが、新規採用の時でも臨時でも830円から880円の時給の中で最高の880円からスタートして毎年10円ずつ上がっていくというような待遇をもらった方もいらっしゃいました。そういったところから言えば、南風原町はある程度就職支援になっている部分もあるのかもしれないですけれども、子どもたちにとってはそういう人員を逃してしまっている、せっかく育てた支援員が他に流れてしまっている可能性も大きいのですね。せっかくこれだけ予算も時間もかけて育てたのに他市町村に流れるというのは、もったいない部分であるのはないかと思うのですけれども、今後その改善を検討する余地があるのかないのかどうでしょうか。
○議長 宮城清政君 教育長。
○教育長 赤嶺正之君 確かに議員ご指摘のとおり、先ほどの部長の調査結果でもございましたが隣町村に比べ低い額であると、南風原町より低い箇所は1、2カ所しかないという状況でございます。私のほうが年額で説明するように指示したのですが、と申しますのは、やはり勤務形態も市町村でそれぞれ違います。南風原町は39名の支援員がおりまして、だいたい2対1、1人の支援員が1人の児童生徒を見る、2人の児童生徒を1人の支援員が見るというようなものが基本でございます。他市町村は3人ぐらいを見るという所もあるわけですね。そうしますと必然的に支援員の数も減ってくるわけですので、当然賃金的な検討の余地も出てくるということで、賃金が高い所はそのような対応があるのかという気はします。本町も低いほうの部類であるということで、教育委員会としましては常に町長部局にもお願いしながら協議をしているところです。全体的なバランス等もございまして、そのような結果となってはおりますけれども、教育委員会としては議員ご指摘のとおり町で経験を積んだ支援員をできるだけ町でがんばってもらいたいという方針は持っておりますので、今後もその点含めて努力をしてまいりたいと思っております。以上です。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。教育部局でも同じような問題を同じ視点で問題だと感じてくれていることに感謝します。やはり現場の声、また子どもたちの状況に応じて町も変わっていかなければいけないところもあるでしょうし、子どもたちは宝物ですので、早い対応をすればそういう障がいを持った子でも普通に生活ができるし普通に仕事ができるといわれていますので、子どもたちへの対応を良くしていくのは大人の責務だと思います。ぜひこれからも前向きな検討、執行部でも前向きに検討していただきたいと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。
○議長 宮城清政君 町長。
○町長 城間俊安君 お答えします。先ほどから教育長がお答えしたようなかたちであります。支援員は、大事です。こちらで育成して他に流れているということですが、この支援員については県下で浦添と、そして島尻教育事務所管内では南風原が最初だと思います。と申しますのは、今は一括交付金を活用しているのですが、以前はそうではなく、県からも僅かな、1校に50万円とかあるのを南風原町においては自前の経費で2,700万円も単費を費やした経緯があります。また以前は、自分の子を普通学級に通わせたいから支援員を配置している南風原に転校したほうがいいのではないかという子が何名かいることも聞いておりました。そういう意味で、南風原町は率先して南部でも県でも一番に支援員を取り入れ進めてきた経緯もあることをご理解お願いしたいと思います。また、議員がおっしゃるように、発達障がいを持つ子には相性というのもあります。1年、2年積み重ねて、この先生であれば一緒に登校していろんなものを学びたいということが、人が変わるとまたゼロからスタートだという面でやはり相性があります。特に夏休みなどで長期間離れると先生に会いたいということもよく聞かれます。そういう意味で発達障がいの子たちは幼稚園、小学校1年、そして高学年になるにつれ体力がついて変わってきます。中学校になると普通に学校に通えるようになりますので、私たちもこの支援員は大事にしたいと思っております。その意味でここ数年は一括交付金を活用させてもらい、これについては県に対しても強く訴えてきた経緯もあります。教育委員会は支援員をやりたい、しかし財政はどうするのか。今までは町単費でやった経緯があるからどうしても一括交付金を活用させてくれと強く訴えた経緯、これが今すばらしい方向につながっているのかと思っております。他市町村においては1人で3名、4名も見ているとも聞いております。しかし私は、それよりマンツーマン、そして隣の子たちともどう接するのか、クラス担任の先生方のサポーターとしてやっていくことも一番大事だと思いますので、私もこの支援員についてはいろいろな角度から協力体制、なるべく複数ではなくマンツーマンできるような体制、状況によっては1人より2人まで対応という場合もあろうかと思いますが、できれば少人数で対応できるようサポートしていきたいと思っております。
○6番 赤嶺奈津江さん 町長、ありがとうございました。福祉的にも、いつも先頭を走っている南風原町であって欲しいと思いますので、ぜひ協力をお願いしたいと思います。嬉しい答弁をいただきましたので、次の質問に移らせていただきたいと思います
問い2番です。学校施設の整備について問う(1)北丘小学校が大規模改造工事をしておりますけれども、今後、北丘小学校を含め4小学校、2中学校の再整備、メンテナンスについての計画がどうなっているかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○教育長 赤嶺正之君 それでは、質問事項2番、学校施設の整備に関するご質問にお答えいたします。(1)でございます。北丘小学校整備が終われば、実施計画に基づいて南星中学校から順次整備を進めていきたいと考えております。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。順次整備を進めていくとのことで、南星中、翔南小と続くと思いますけれども、どのような整備になっていくのか、どの程度の整備になっていくのか。北丘のような大規模改造になっていくのかお伺いしたいと思います。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 再質問にお答えいたします。学校施設の整備についてでございますが、教育長からも答弁していただきましたように、南星中学校を挙げましたが、年数のたっている学校を順次メンテナンスを重視して北丘同様の手法でやっていきたいということです。それから、実施計画に基づいて順次やっていきますが、大規模改造的な工事とは別に、教育委員会サイドで多くの事業がございます。例えば北丘小学校斜面の道路擁壁部分であったり、津嘉山小学校裏門の避難通路であったり、それから学校のクラス増が発生することが考えられますのでそのクラス増築がございます。それらは予定していますと言うより実施計画、財政等の関連もございますし、また事務対応の関連もございますので随時それに向けては取り組んでいくということにします。そのように取り組んでいきたいと思います。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。北丘が大規模改造になりまして、次に南星中ということですけれども、実際北丘が大規模改造に入るときに、町長から公共施設のこれまでのあり方ということでメンテナンスをしてこなかったからこういった大規模改造になったという話がありました。その点から南星中は、もうじき30年にもなりますのでどうしようもない部分もあると思いますけれども、大規模改造以外でどのようなメンテナンスをやっていこうという計画があるのかお伺いしたいと思います。
○議長 宮城清政君 町長。
○町長 城間俊安君 教育部長からありましたが、メンテナンスとは大規模改造ではないと思います。メンテナンスとはやはり景観、防水視点、防水を疎かにしたから水が浸透して腐食しますので、こういうことを抑えるため一番それが大事ではないかと思います。まず、大規模改造をする以前に外壁も防水をやっていくことが一番大事ではないかと思います。そのように防水をして、その次の時点、どうしても改修しなければならないというような教室の配置など内部のリフォームをすることが大事ではないかと思っております。そういうことを基本的にやっていくのが大事だと思っております。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん 町長、ありがとうございます。かなり酷い状態になってからお金をかけるのではなく、いかに延命させきれいに使っていくのかが大事だと思います。景観、防水関係なども常に心配りをしながら学校の環境を整えていただきたいと思います。北丘小学校も3分の1きれいになりまして、先生方、保護者からも大規模改造ということでリフォームなのかと残念がった声があったのですが、実際に入ってみるとかなりきれいになっていて、こんなにきれいになるとは思わなかった、以前の教室や廊下は若干暗い色だったものですから、とても暗いイメージだったのですが、配色を変えたことで学校の雰囲気が変わっていると、新しく大規模改造をやっているところの出来上がりが楽しみであるというような声も聞かれています。南星中、翔南小、津嘉山小、南風原小ときますけれども、各学校どうしたら良い雰囲気になっていくかも考えながら、また子どもたちはきれいだと汚さないのですね。あまりきれいでないと、心理的なものなのかこれぐらいはいいだろうと散らかしたりするのですけれども、きれいなものだとごみ一つでも気になったりと、きれいなところはきれいな状態にしたいというのが心情だと思いますので、ぜひ子どもたちの環境を整える意味でもこれからのメンテナンス、再整備をお願いしたいと思います。
先ほど、部長から北丘小学校の法面や階段、津嘉山小学校の裏門のことがあったのですけれども、校舎以外での今後の整備について検討されている事項を教えていただけますでしょうか。
○議長 宮城清政君 学校教育課長。
○学校教育課長 稲福 正君 ただいまの質問にお答えいたします。北丘小学校につきましては、体育館をこれから検討しております。北丘では現在、進入口が1カ所しかないということで、避難通路含めてあと1カ所検討していこうという方向もあります。また、北丘小学校の屋内環境、北丘幼稚園の屋外環境、そういうものも今後検討していこうという方向で計画を持っております。他の学校につきましては、今のところトイレの改修、敷地等外部についてはないというところです。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。これから特に北丘は避難通路もないということでそういったことも検討されているとのことでしたので、子どもたちの環境づくりのためにこれからも早めの対応をお願いしてこの質問は終わりたいと思います。
問い3番にいきます。子どもたちの居場所づくりについて問う(1)南風原町は那覇市に隣接し、住宅もどんどん増加しております。共働きも多いため、放課後の子どもたちの安全確保は必須となっておりますが、町内には小学校区ごとに児童館はありますけれども、それだけでは補えないくらいの児童数だと思います。地域に合わせて町と各自治会・校区が協働で子どもの居場所づくり事業が行えないかを質問したいと思います。(2)翔南学童で増園の課題が出ていると聞いております。地域環境の違いに合わせた子ども居場所づくりを支援してはどうかお伺いしたいと思います。
○副町長 国吉真章君 それでは、質問事項3点目の子どもたちの居場所づくりについて問う(1)にお答えします。町では小学校区ごとに児童館を設置し、放課後等の児童の居場所として活用していただいています。それ以外にも地域における公共的な施設について、地域や保護者等の合意を得ながら地域の特性に合った利活用ができれば子どもの居場所になる可能性もあると思われます。現在、教育委員会と放課後子ども総合プランについて意見交換をしておりますので、そのなかで児童の安全・安心な居場所の確保に向けて議論をしてまいります。
(2)です。翔南小学校においては、平成23年4月から空き教室1室を利用して翔南学童クラブが保育を行っております。現在、52名の児童が利用しておりますが、同校区は他の小学校区に比べて学童クラブが少ないため、毎年定員以上の申込があり、学童クラブに入れない児童が出ているのが現状であります。そのため、保護者等から学校敷地内への新規学童の設置要望が寄せられております。その件については、これから教育委員会と協議を進めてまいりたいと思います。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。教育委員会と調整しながらやっていきたいとの答弁だったと思いますけれども、文科省のホームページを見ますと居場所づくりということでかなりの事例があります。公民館を利用していたり学校の敷地内を利用していたり、1つのパターンではなくたくさんの事例があるので、そういったところからも先進地を見に行って、南風原に合ったものを、とはいえ南風原には小学校で言いますと4校区ありますが4校区全然違うと思うのですね。北丘の場合には、地元でもありますので、学校のそばに児童館もあって学童クラブも無認可の保育園だったりそういったところが引き受けてくれてかなり充実しているかと思います。また、校内で「わんぱく事業」ですか、週2回、3回、子どもたちを預かるシステムも動いていて居場所づくりはかなり充実してきていると思います。それ以外に、北丘のなかでも与那覇、宮城、翔南であれば山川、神里、児童館から遠かったり児童館が学校のそばになかったり、地域によっていろんな特性があると思うのです。そういったところに合わせた、コミュニティ単位で子どもの居場所づくりができればいいのではないかとこの質問をさせていただきました。ただ一緒くたに南風原町で決めるのではなくて、自治会、この校区に合わせた運用方法を検討されてはどうかと思うのですけれども、そのなかでも保護者はどうしたらいいのか分からないという点で、町からこういった選択肢、こういったパターン、こういったものも活用できるよというような情報提供、アンケートを取って充実した居場所づくりをしてはどうかと思うのです。そういったアンケートを取ったことがあるのか、またはこれから取る予定があるのかないのかお伺いしたいと思います。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。奈津江議員からありましたとおり、南風原町には児童館が4館、小学校校区ごとにあります。県内でも南風原が特に良いと考えています。そこでも平成25年度は4館平均して毎日45名ほどの子どもたちが利用しているということで、もちろん館で多少の違いはありますが利用していただいているということであります。質問の最後のほうでアンケートを取りませんかとのことでしたけれども、子ども・子育て支援会議のなかでこういう対象者にアンケートを取って、そのなかで教育委員会ともタイアップしてぜひ進めていきたいということです。国が出した要綱も今年の7月31日付文書で文部科学省、厚生省、局長クラスの連名で各市町村に来ています。それも踏まえてぜひ今後、各字の公民館あるいは児童館等、そこでできるかどうかについては今から調査して検討していきたいと思っております。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。今のご答弁は、前向きな答弁だったということで受け止めております。自治会単位では、学校からは近いところだと児童館に行って地元で遊ばない子も多いとか、また反対に児童館が遠くて、地元でも遊ぶ所がなくて、3名以上でいると団体でたむろしているよと言われたりということもあると聞いていますのでやはり居場所というのは大事だと思います。私がとても良いなと思ったのは、それが嫌だと言う子もいるかもしれませんが、北丘児童館はわりと小学生が多くて中学生が少ない、本部児童館は中学生がかなりいて小学生が少ないとかいろんな特性があるのですが、私がたまたま児童館で卓球を教える際に、最初は中学生がたくさんいて小学生が来たときには譲ってあげて、また小学生の手が空いていると一緒にやるかと中学生が声をかけて教えたりとか異年齢交流がいい感じでまわっていたのですね。この子たちの居場所というところでその役割を児童館やコミュニティセンターが担うと青年会につながっていったり、その地域の活動につながるのかなと思います。できましたら児童館だけではなく、児童館も家が遠いとなかなか行かない、または荷物を置いてまた行くのか、宿題等も学校でやった人たちは帰るのは5時半以降になるとかいろいろ課題があると思いますので、その地域の実情に合わせた子どもの居場所づくりをお願いしたいと思います。
(2)にいきたいと思います。同じように居場所ということなのですけれども、翔南小学校の地域は学童が少ないということで、昨日は大宜見洋文議員からの質問もありましたが、校区外の学童に行っていたりと寂しい思いをしているのか、または親の負担があるのかと思います。また今後、子ども・子育て新制度のなかで、6年生までが学童に入ることができると、あるいは幼稚園児ができないとかいろんな課題がありますけれども、そのなかで継続して入りたいとかまたは新規で入りたいということが増えてくる可能性がありますし、実際20数名の子が入れていないという実態から、他の校区とは違う問題点が翔南校区ではあるのかと、学童がない、受け皿がないところでは課題なのかという思いです。公平・公正に安心して放課後を過ごせるという点から、敷地に余裕があるのであれば翔南小学校のなかに増園のかたちで学童をやってもいいのではないかと思いますけれども、その点を教育部局はどのようにお考えでしょうか。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。教育委員会部局と調整しながら進めていますので、私のほうからお答えしたいと思います。昨日、洋文議員にもお答えしました。今、翔南小学校で1園学童をやっています。これは空き教室がたまたまあると、しばらく使えるということで開設しました。その当時から学童のなかの待機が出るという心配はしておりました。今年で4年目になりまして20数名入れないということで、学校外の学童を使ってもらっています。これについても確かに翔南校区のなかで学童クラブが近くにないということで、それは地域、学校区ごとに感覚が違います。町としてももし翔南小で作れるようなことであれば、4校とも一緒に作れるような、時期が違ってもそういう考え方で示さなければいけないだろうと考えています。これについては、敷地の問題あるいは今ある既存の学童をしている方とも調整しながら、しばらく時間はかかると思いますので昨日も話したように、すぐに必要であればぜひ民間の施設等も利用してやってもらいたい。昨年からちょうど5万円以内の家賃補助も出ていますので、そんなに大きな負担はないと思います。このへんは保護者とも調整しながら進めていきたいと思っております。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございました。4校同じような条件でとおっしゃっていましたけれども、学校区ごとに地域の環境は全然違うと思います。実際、北丘ではそういった受け皿的な認可外保育園だったりがいろんな役割をしてくれて、バスで迎えに来たり車で迎えに来たりということで送迎まで全部やってくれるので、以前あった殺傷事件の時など学童とのやり取りをして迎えに行けない親たちは大変助かったと思います。私も小学校へ迎えに行きましたけれども、学童の先生方も急いで迎えに来て子どもたちを引き受けて先に帰るというようなことをやっていました。仕事場から直接迎えに行けないといったときには、学童は大変ありがたい存在で、子育てをするなかでは重要な役割をしていると思います。南風原小学校も近隣に何カ所も学童がありますし、認可外ではなく学童として運営しているところもかなりありますけれども、翔南小学校では学童がかなり少なく校区外が多いとも聞いていますので、公平・平等の点から同じように子どもを安心して預けられる場所を先に作ってあげることも大事だと思います。全部が全部、条件が整ってからだとその間にかなり不便と言いますか不都合を期する親御さん、子どもたちがいると思います。今後、やっていくことを前提であったとしても、先にいって走るべきだと私は思います。なぜなら、子どもたちを安心・安全に育てるための学童であるわけですから、平等の観点はそこから見出すべきだと私は思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
○議長 宮城清政君 民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。学童クラブが校内にもしあれば当然安心・安全の面では最適な場所だと考えています。現状として翔南校区に学童クラブが少ない点もあります。ですから、この期間、町として方針が出る間、1年ないし2年、それなりの町補助で400万円から500万円ぐらい、そして家賃補助も月々5万円ぐらいありますので、場所があれば、いちでも申請してもらえれば学童を認可することができますので、議員がおっしゃることも承知していますけれども、しばらくどういうかたちがいいのか議論して支援していきたいと考えております。
○議長 宮城清政君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江さん ありがとうございます。場所があればというお言葉があったとおり、場所がないから親が困っているわけでありまして、そういった場所を作るための人員確保だったりそういった環境を整えるためにはかなりのパワーが要りますし、既存のものと同じように作ることができれば親も安心できると思います。ある意味、任せきりになる可能性が出てくるわけですね。予算などは面倒見るけれども、場所がなければ実際に子どもたちを預けることができないわけですから、誰か運営してくれる人を他の場所で探して、そこまで設置しないと学童は運営できないわけですよね。そうではなくて、そういう場所を町が作っていくことも大事であると思いますので、そういった点からも町が率先して、そうであれば作りましょうと言えるような前向きな協議をやっていただいて、北丘と津嘉山は児童数がかなり増えて北丘が800名ぐらいですか、津嘉山も同じぐらいになってきているのでしょうか、学童の受け皿が近くにあることでまだ余裕があるのかもしれませんが校内の敷地内には余裕がなくなってくる可能性があるわけです。また北丘小学校は地すべりが近くにあったりそういった所に設置するのかという課題も出てくると思いますので、そういったところから言えばそれぞれの学校に合わせた学童設置が必要になってくると思います。ぜひ前向きに、早めに対応することを検討していただいて、これはお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議長 宮城清政君 暫時休憩します。
休憩(午前11時04分)
再開(午前11時17分)
○議長 宮城清政君 再開します。通告書のとおり順次発言を許します。3番 大城 勝議員。
○3番 大城 勝君 3番議員、大城 勝です。2つの内容を一括して質問します。1.このたびの沖縄県知事選挙は、うちなーんちゅのアイデンティティが問われた選挙だったと思いますが、わが南風原人のアイデンティティについて触れたくていくつかの質問をします。(1)近年、しまくとぅばに対する関心が高まっていますが、わが南風原町の小中学校現場における、しまくとぅば教育の取組について質問します。(2)本町の兼城交差点の歩道上に「へーばる通り」と表記されている標識プレートが設置されています。その設置の経緯について質問します。(3)わが南風原は、会話としてのしまくとぅばでは、「ふぇーばる」とも、「へーばる」とも言い方があります。一方、記述したり文献表記では「ふぇーばる」がほとんどだと思いますが、それについての町行政の見解を聞かせてください。
2.南風原町歌の町民への普及度合いについて問います。(1)日頃から南風原町の町歌に親しみを持つことは、町への愛着度を高めるのに効果的だと考えます。地域や学校現場での町歌の普及度合いについて教えてください。(2)町活性化の一環として、南風原町歌を振り付けして全町民が踊れる音頭を作ったり、町歌大会などを開催して南風原町へ観光客を呼び込める仕組みが作れないか。質問は以上です。よろしくお願いします。
○教育長 赤嶺正之君 大城 勝議員の、南風原人のアイデンティティについてのご質問にお答えいたします。(1)でございますが、小中学校の授業では、特別な取組はありませんが、町教育委員会と町文化協会主催の「ウチナーグチ大会」に数人の児童生徒が参加しております。同じく質問事項(3)でございます。南風原に伝わるしまくとぅばを大事にして取り上げていただき感謝をいたします。さて、しまくとぅばとして南風原の地名である「ふぇーばる」と「へーばる」の言い方がありますが、地域でも読み方が違うため、教育委員会の見解といたしましては、しまくとぅばで表記する場合はそれぞれの地域での読み方で良いと考えております。以上でございます。
○議長 宮城清政君 副町長。
○副町長 国吉真章君 それでは、質問事項1番の(2)標識プレート設置の経緯についてお答えします。本町の兼城交差点歩道上に「へーばる通り」と表記されている標識プレートを設置した経緯については、平成16年度に道路に親しみが持てる快適で美しく使いやすい道路環境づくりを目指して、南風原町道路愛称選定委員会が選定した国道・県道・町道の13路線について広く町民に道路愛称募集を行いました。応募があった路線愛称については、南風原町道路愛称選定委員会で審査を行って国道329号については「へーばる通り」で決定しております。標識の設置については、南部国道事務所が設置しております。
質問事項2.南風原町歌の町民への普及度合いを問う(1)です。町歌については、新年宴会や毎年4月1日の町制施行記念日での表彰式、町陸上競技大会での開会・閉会式等で歌う機会があります。また、役場の午前と午後の始業時に庁内放送で流しています。しかしながら、地域や学校現場ではまだ十分普及しておりません。(2)です。町歌には、作者の思い等がありますので、振り付けについては難しいと考えています。町歌とは別に、南風原町民音頭があります。振り付けもされ盆踊り等で踊られております。町活性化の材料になれるような仕組みについては、皆で知恵を出し取り組んでいきたいと思います。以上です。
○3番 大城 勝君 ご答弁ありがとうございました。今度の知事選挙で新知事に当選された翁長さんが用いていた言葉に、うちなーんちゅとしてのアイデンティティがありますが、それを南風原人としてのアイデンティティに置き換えてみたとき、南風原人としてはどういう心構えを持ち得るかになろうと思うのです。私は、南風原人としてのアイデンティティとはなにかと問われたとき、それは南風原のそれぞれの集落が持っている地域文化や風土のなかにそのアイデンティティを形作るものがあると思うのです。与那覇の集落から神里までの昔からの12集落、それに団地やハイツなどの自治会において、それぞれ浅い深いはあるにせよ、昔から使われた地域の文化・風土は持っています。この地域の文化は、しまくとぅばであったり伝統的な民俗の踊りであったりします。この地域にある文化や風土を土台にして、私たちは南風原人としてのアイデンティティを感じ取り、地域に育てられていくのだと思います。その地域からの文化や風土の息づかいを感じ取り育てられて一歩進みえたところに南風原人としての誇りも生まれ、南風原を愛しこれからもずっと南風原町に住みたいという気持ちになると思うのです。ところで、私の小中学校時代、もう50年も昔ですけれども、学校では日本語、家や地域ではしまくとぅばというバイリンガル的な言葉の使い分けをしていました。学校でしまくとぅばを使うと方言札や掃除当番をさせるという罰を与えるのではなく、日本語もしまくとぅばも話せることはバイリンガルで格好いいという教育的配慮がなされていたらと思えてなりません。私も掃除当番をさせられた一人なのですけれども。近年、沖縄県内でしまくとぅばに対する関心が高まっていることは、地域文化を守り、それを育て発展させるためにも大事なことで素晴らしいことだと思います。その観点からもしまくとぅばが学校現場ではどのように授業の一環として捉えられているのか関心のあるところなのです。先ほどの答弁のなかで小中学校の授業で特別な取組はありませんとありましたけれども、どう取り組むか今後の課題として理解したいと思いますが、ちょうど2年前でしょうか翔南小学校の学校評議員をやっておりましたけれども、校長に招かれて翔南小学校の運動会を見る機会がありました。球入れの入れた球を数える時、小学校2年生か3年生だったでしょうか、子どもたちが「てぃーち、たーち、みーち、ゆーち」と、「とお」の次にはなんと言っていたかよく覚えていないのですが、「じゅういち、じゅうに」になっていたのでしょうけれども、そのようにして数えていました。それから、ラジオ体操の第一体操がだいたい2分30秒ぐらいですけれども、それをうちなーぐちバージョンで行っていました。学校現場では先生方がいろいろ工夫されていて、そういった様子が伺えました。私が見ましたのは翔南小学校ですので、あとの5つの学校がどうか、先ほどの町教育委員会では町文化協会との「ウチナーグチ大会」で数人の児童生徒が自由に参加しておりますという、だいたいそのレベルかと私は見ております。
次に、「へーばる通り」の標識についてですが、通りの標識プレート名は、本来、そこの地域住民に親しまれている名称であるべきだと思いますが、本町の兼城交差点一帯は、交通量も多く町役場にも通じ、南風原町の表通りであることから南風原町を代表する通り名が相応しいと私は思います。「ふぇーばる」なのか「へーばる」なのかの論議ではなく、南風原を訪れる者に受け入れられやすい表記が相応しいと思います。
次に、(3)についてですが、わが南風原をしまくとぅばでは「ふぇーばる」とも「へーばる」とも表現します。言葉は時代に即して変化していく点ではなんら「ふぇーばる」と「へーばる」に異議を唱えるものではありませんがしかし、書いたりする点では「へーばる」の「へー」は文献的にも日常生活のなかでもほとんど見ません。逆に「ふぇーばる」がもっぱらの使用であり、南の風を「ふぇー」と表現するがごときで、「南の風(へーのかじ)」とはまず言いませんよね。答弁にありますように、それぞれの地域での読み方で良いと考えることも町全体を視野に入れた町行政としてはよろしいかと思いますが、このように文化の多様性という見方ではなく、町外にわが南風原を情報発信していくとき、やはりどちらでも良いとするあり方は間違った情報を発信してしまうのではないかと思います。ここは町内の有識者を募り、わが町・南風原は、しまくとぅばではどう表現・表記できるのか論議してもらうのもいいのではと考えますが、それについて町の考えをお聞かせください。
○議長 宮城清政君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 「へーばる」「ふぇーばる」について、方言、読み方と言いますか、うちなーぐち読み方ということで、最初の答弁ではそれぞれの読み方でいいのではというような考え方は、町全体の見解として述べてございます。それを論議して町外に発信して統一するというようなことは、これまでの経緯、ちなみに「ふぇー」と「へー」については、先ほど道路の話もありましたが「へー」という読み方を公募で募ったところであります。それから、「へーばらくどぅち」というものがあるようですが、それは「へーばるくどぅち」だと文化協会の方は言っていたようです。そのように、文献では「ふぇー」、実際使っているのは「へー」というように混在していますので、地域的にと言いますかその語源的なものもあると思います。最初に答弁しましたように、その地域の呼び方でいいのではないかと考えています。今のところ委員会等立ち上げて、南風原町としてどう決定するというようなことは考えていないということです。「ふぇー」と「へー」を議論に挙げたところで、なかなか難しいのではないかという考え方を持っています。
○議長 宮城清政君 3番 大城 勝議員。
○3番 大城 勝君 今の答弁で、難しいからやらないと理解してしまうのですけれども、やさしかったら私は自分でやりますという話なのですね。難しいところをどうにかしましょうと、そういった場合にはそれを専門にしている人たちを招いて、あるいは諮問してみてはどうかという私の考え方があるのだということで質問を留めます。
次にいきます。南風原町の町歌についてですが、役場庁舎内で一日に朝・昼の2回、数分間流れています。庁舎の場所によっては、作業に支障があるからなのか、あるいは庁舎を訪れる町民への配慮か、控えめな音量の気がします。町歌の1番に、「明けゆく朝よ 南国の 空にかがやく 日の光り 溢れる希み はつらつと ああ 躍進の 雲が飛ぶ われらが郷土 南風原町」とあります。カラオケがあればそこで歌ってみるかという気もするのですけれども、それはやめましょう。歌詞のなかにも「はつらつと」とあるように、町歌を歌うときは表情なども生き生きとして元気よく歌いたいものだと思います。それから、町歌の2番では、額に汗して働く町民にそよ吹く風もさわやかに吹き、3番では緑豊かな黄金の森は美しく人の和の花が咲くと結んでいます。このように、「はつらつと」、「さわやかに」、そして「美しく」との表現を用いてわが南風原を讃えているのです。ここに南風原町歌に関する資料がありますが、これは議会事務局の優秀なスタッフに、過去の議会広報のなかから探してもらいました。40何年も前の資料です。この南風原を讃える歌は、本土復帰前の1971年に作られた歌ですが、まだ南風原が町ではなく村の時代で、村歌として一般からの募集によるものです。そのときの募集要項によりますと、南風原の飛躍的発展を象徴するものを趣旨にした歌詞にしたことであることが要望されています。そのときの1等入賞賞金が50ドルとなっています。60歳以上、私ぐらいの年齢になると、50ドルがどれぐらいの価値か分かりますが、今の物価で20万円ほどの大金になろうかと思います。私の給料よりも高いということですね。20万円もの大金をはたいたということは、当時の人たちがその村歌の誕生をいかに期待していたかがうかがえると思うのです。その歌が誕生して40数年経過した今日でもなんら色あせることなく南風原町の飛躍的発展を象徴した歌詞であることに変わりはないと思います。この南風原町歌を町民により親しみを持ってもらうために、役所1階ロビーの壁に大きなパネルで町歌歌詞を掲げてはどうかと私は提案します。この質問をするにあたって、あちこち調査したのですけれども、この町歌についてはどこにも見当たらないのですね。文字として記されたのは、この40何年か前の資料にしか見当たらないのです。あるいは1月4日の新春にいただくパンフレットにはきちんと記されていますね。1年に1回ですから、365日分の1日しか見ることができないということなのです。答弁のなかにもあるように、地域や学校現場に普及がないままにしておくと、町役場を滅多に訪れない町民にとっては、この町歌の存在すら分からなくなってしまいます。
さて、城間町長におかれましては、わが南風原町の飛躍的発展を願い、日々奮闘されておられるわけですが、40年前に先人たちによって作られた南風原町の町歌に関して行政の長としての考えもおありではないかと思います。そのへんの思いをよろしければお聞かせください。
○議長 宮城清政君 町長。
○町長 城間俊安君 しまくとぅば、また町歌に対する思いに感謝申し上げたいと思います。私たち南風原町において、まさにしまくとぅば、12字では方言も異なっておりました。特に喜屋武、本部、照屋は、隣近所でありながらも地域の言葉があり、私も津嘉山ですが津嘉山言葉というものがありますし、津嘉山言葉は荒いということもありますが、そういう意味では大事にしていきたいと思っております。言葉に関して私が反省しなければいけないのは、自分の子どもたち、孫たちに対して方言で話をせず共通語でやってしまった、これが大きな弊害につながったのかというところです。そしてまた南風原町の地域の言葉というのもずいぶんなくなってしまっている。方言を使えば名残が残ったのでしょうが、使える子どもたちが少ないことは悲しいことです。地域、地域の言葉というのは、大人が子、孫に対して教えていくことも大事だと反省している部分があります。
また、町歌については、今日、はっとさせられました。ありがとうございます。と、申しますのは、町歌を掲示すべきだったと思います。学校では体育館に校歌が掲示されております。行事があるたび、表示された校歌を参考にして生徒たち以外も皆、曲が流れると同じように口ずさむことができます。町も役場には町民ホールがありますし町民の皆さんの出入りもありますから、朝、昼に町歌の曲が流れたときに表示されていれば聞くだけではなく歌詞を見ることもできます。これは大事だと思います。役場建設の際にデザイン的にそぐわないということがあったのかどうかは分かりませんが、私自身はあるべきだと思っておりますので、この問題等においては即、担当をとおして町歌に相応しいかたちで掲示できるよう準備させてもらいたい、進めていきたいと思っております。気付かせてもらい、ありがとうございました。
○議長 宮城清政君 3番 大城 勝議員。
○3番 大城 勝君 そうですね。町長の前向きなご答弁だと受け止めます。なるべく早い時期に掲げるようなさってください。その時に、40数年前の資料も一緒に掲示するような仕組みを取っていただければと思います。
ここで南風原人としてのアイデンティティを考えるとき、わが南風原を「ふぇーばる」とも「へーばる」とも言えるなかで、私はやはり南風原人としてのアイデンティティを持ちたい。確かに、しまくとぅばに対する認識が低ければ、「ふぇーばる」も「へーばる」も止めて、「はえばる」で統一すれば良いことかもしれません。しかし、地域文化のあり方を行政が理解を示すスタンスを持っているならば、「ふぇーばる」にすべきだという私のこだわった考え方だということで私の質問を終わります。以上です。
関連記事
お問い合わせ
議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp