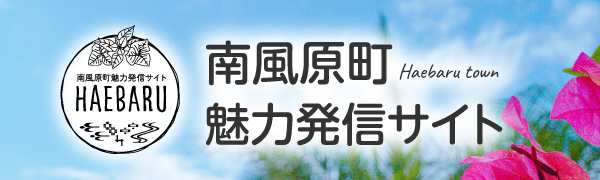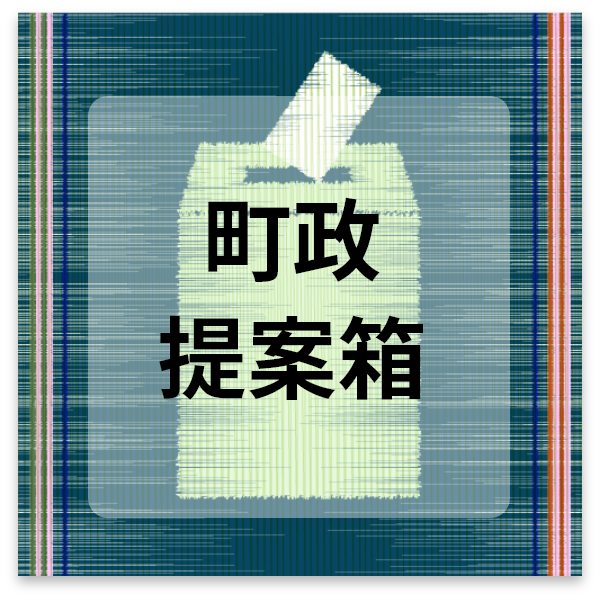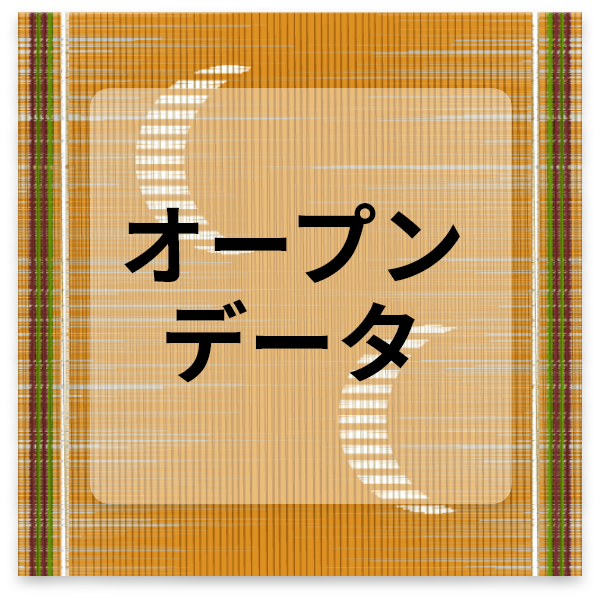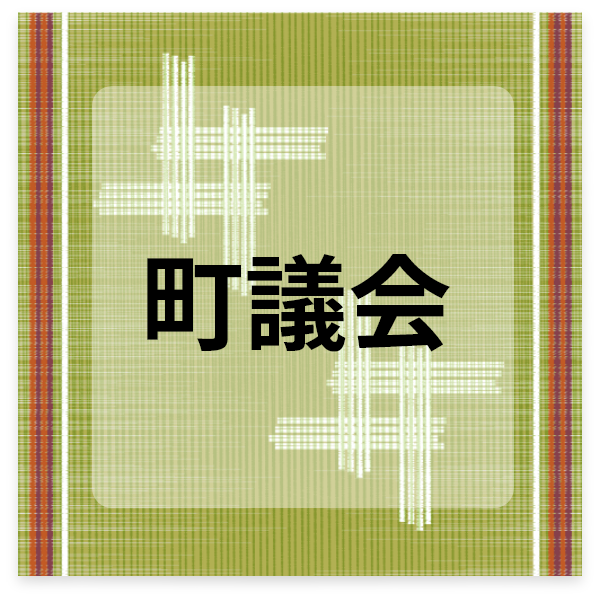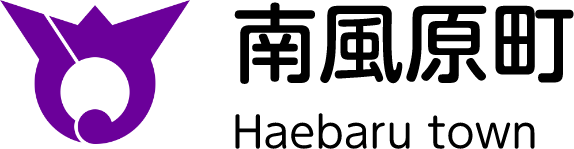本文
平成26年第2回定例会 会議録(第2号-1)
平成26年 (2014年) 第2回 南風原町議会 定例会 第2号 6月17日
検索
| 日程 | 件名 | |
|---|---|---|
| 日程第1 | 会議録署名議員の指名 | |
|
日程第2 |
質問議員名 | 質問内容 | |
|---|---|---|---|
| 知念富信 | 答弁 、再質問 | ||
会議録
○議長 中村 勝君 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。
開議(午前10時00分)
日程第1.会議録署名議員の指名
○議長 中村 勝君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって7番 知念富信議員、8番 宮城清政議員を指名します。
○議長 中村 勝君 日程第2.一般質問を行います。通告書のとおり順次発言を許します。15番 大城真孝議員。
○15番 大城真孝君 2点について質問をさせていただきます。1点目に、津嘉山小学校校区について。津嘉山北土地区画整理事業があり、津嘉山小学校の生徒数は増えてきていると思いますが、現状はどうか。(2)津嘉山北土地区画整理区域内の校区は今後も津嘉山小学校のみになるのか。教育委員会では校区をどう考えているかお伺いします。
2点目に、クサティ森等保全事業について。津嘉山地区のクサティ森等保全事業の計画はどうなっているのかお伺いいたします。
○教育長 赤嶺正之君 それでは、大城真孝議員の、津嘉山小学校校区についてのご質問にお答えいたします。まず、津嘉山小学校の生徒数はどうなっているかのご質問でございますが、津嘉山小学校生徒数の現状は、平成21年5月1日で690名、平成22年度は703名、平成23年度690名、平成24年度702名、平成25年度726名、平成26年度757名となっており、5年間で67名増えております。
(2)のご質問でございますけれども、津嘉山北土地区画整理区域内の既存の人口を約2,400人と予測しまして、約2,800人増える計画でございます。これらを踏まえまして、平成26年5月1日現在の津嘉山小学校校区人口に対する在籍数を見ますと、現在の津嘉山小学校区人口の約9,554人に対しまして在籍数が757名となっております。区画整理後の津嘉山小学校校区人口は、約1万2,354人と予測されますので在籍数を978名と予想いたしております。よって、区画整理完了後も数字的には現校区でも対応できると予測しております。以上でございます。
○副町長 国吉真章君 それでは、質問事項2つ目、クサティ森等保全事業の計画についてであります。平成25年度にクサティ森周辺の基本計画委託業務と津嘉山殿(トゥン)周辺の実施設計業務について平成26年1月に地元との計画説明等を終え、2月に同業務を完了しております。殿(トゥン)周辺の整備については、平成26年度に擁壁や造成等の工事に着手し、平成27年度に園路など施設の整備を行う予定で進めております。また、殿(トゥン)周辺以外の箇所については、平成27年度より実施計画を行い順次整備を進め、平成30年度に事業完了予定となっております。
○15番 大城真孝君 教育委員会ではあまり差し支えないという捉え方をしていますけれども、では、津嘉山公民館では週2回に放課後の事業をやっていますね。区長からお伺いしますと、その理由はおそらく学校では教室が足りないからということで津嘉山公民館を使用させてくれとお願いされているはずです。それなのに教室は足りているという考え方は、理解し難いところがあります。
一番気になるのは、小学校校区はほとんど字でやっていますよね。向こうの一部は、字本部なのです。同じ区域内で隣は翔南小学校、隣は津嘉山小学校となっては困るのではないかということです。それで今回、どういう考えを持っているのか取り上げています。また、南風原小学校近くの郵便局向かいから入って行った南風原産婦人科の通りの本部地番は翔南小学校ですよね。子どもたちは、南風原小学校の正門を背負って翔南小学校に向かっていくのです。それも理解し難いところがあるので取り上げています。そこはどう思いますか。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 ただいま再質問の津嘉山小学校校区の件でございます。今の津嘉山小学校区の人口については、先ほど教育長からも答弁がありましたように区画整理に伴い集合住宅等の建設、個人住宅等の建設で徐々に増えてきております。それはご承知のことだと思います。それで最初にありました放課後子ども教室は、津嘉山小学校は空き教室がないため津嘉山公民館にお願いをして週2回、火曜日と金曜日に3時から5時の時間帯で開催させていただいております。それについては、大変ありがたく思っております。それで、学校に空き教室がないというのは、例えば北丘小学校はクラブハウスを作ってそこでやったり、翔南小学校については普通教室の空き教室があります。津嘉山小学校につきましては、そういう空き教室が今のところないということでこれまでやっておりませんで、昨年から津嘉山公民館にお願いをして行っております。学校にも確認をしましたら、普通教室の空き教室は今のところありませんけれども、2階、3階に多目的教室がありまして、これで3教室分のスペースがございます。津嘉山公民館が大変支障をきたしているというようなことでありましたら、再度学校と調整をしてその多目的教室を活用することはできないものか検討させていただきたいと思います。2階の多目的教室を放課後子ども教室に利用しますと、その子ども教室の内容は1年生からの申込制となっておりますので、1年生は授業が終わるのが早く高学年との時間帯の差があります。教室の近くに1年生の児童が来て放課後子ども教室をしますと、バランスが違いますので子どもたちが動いたりそういったようなところで不都合があるのではないかということでこれまでできなかったというようなことでございます。普通教室の空き教室はございませんが、それについて多目的教室が可能かどうか調整をしてまいりたいと思います。
それから、校区につきましては、本部の一部が南風原町立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則のなかで、津嘉山小学校の校区といたしましては字兼城地番の県営第二団地自治会の部分ですね。それから字本部の一部ですけれども、281から348番地、そして字津嘉山という校区分けがされています。この本部の地番は、本部公園から少し下ったところの分譲兼本ハイツに行く所の道路から下のほうが津嘉山の校区になっております。そのなかでそのまた一部が区画整理されていて、295番地から320番地あたりのその部分は、本部地番に入っていますが津嘉山小学校区になるというように考えております。
そしてもう1つございました、南風原小学校の兼城と本部の境界部分、元南風原産婦人科あたりの地番の方については、本部地域ということで翔南小学校校区とされています。確かに現状といたしましては、通学路として南風原小学校正門の前を通っていって翔南小学校に通学するというような現在の校区の割り振りで、住んでいる方、児童からすると距離的に不都合があるというようなことですけれども、翔南小も分離した平成3年当初には700名であったのが年々減ってきている現状もありますので、近いからという視点で校区を変更するのは今のところ厳しいのではないかと思います。しかしながら、平成3年に分離してございまして、規則の改正から見ますと大きい分離があったときに校区の変更をしているというような捉え方をしておりますので、今後、津嘉山区画整理の部分等も含めて、大きい道路の形態で分けるのか、コミュニティ関係、集落関係でもう一度見直しするのかは、今後の進展、町の発展によって再度検討していく事項ではないかと今のところ考えております。
○議長 中村 勝君 15番 大城真孝議員。
○15番 大城真孝君 皆さんが計画しているのは、区画整理区域内は全地域、津嘉山小学校だという認識でいいわけですよね。前に校区を確認したときには、向こう側は元々農地が並んでいて警察宿舎と第二団地は津嘉山小学校校区だと、では区画整理後は字本部の場合どうなるのか。と、言いますのは、そこに保留地があります。津嘉山小学校だろうということで保留地を買ったと、ところが学校は翔南小学校だったというように、分からない方もいらっしゃいますのでそのへんが気になったものですから質問しています。そのように皆さん方教育委員会で決めているのでしたら、それなりに教室は不足するはずです。普通教室が足りないと、特別教室か何かを利用すればどうにかできると言いながら、津嘉山区長から直接は聞いていませんが、たぶん不都合があって議会報告会のたびにそういう意見が出るのです。普通ならそういうことは出ないはずだと思うのです。皆さん方は、地域に押し付けではなくて相談してやるはずですのでね。皆さんの計画からすると教室を増やすのは小学校が平成28年ですか、平成27年に幼稚園も入っているはずですが来年はないわけです。それは足りているからだという考え方ですよね。当初予想は区画整理区域でも人口増が5,200名、それ以上に集合住宅が増えているのです。皆さんが予想した以上に増えているのではないかと思っています。そういうことがありますので、ぜひ、仮に津嘉山小学校だったら計画に応じて教室を増築するなりしないと地域にも迷惑をかけては困りますので、そのへんは十分なされているのかもう一度お願いします。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 お答えいたします。まず、校区の問題でございますけれども、部長からもございましたように、翔南小学校が分離したのが平成3年でございますので20年を超えていますし、津嘉山小学校の開校からしますと昭和50年ですから49年ほどになるわけでございますので、現実的に当時の校区の考え方自体が現状としてそぐわないことも十分考えられます。もちろん、津嘉山小学校の教室の増築等も計画はございますけれども、やはり現実的な問題としまして校区の問題も慎重に検討しなくてはいけないと考えております。教育委員会のなかでは、定例教育委員会等で校区に関して議論をしたことはございませんが、議員ご指摘のとおり現状がそうでございますので、今後、この校区に関しましても教育委員会のなかで慎重に議論してまいりたいと考えております。そのなかで先ほどから出ておりますように、地形・地物の道路あるいは自治会・コミュニティといったようなものを押さえまして、弾力的に柔軟性を持って検討してまいりたいと考えております。
それから、放課後子ども教室の学校利用に関しましては、ご指摘のとおりでございまして、学校施設を利用しての放課後教室が原則でございますので、そういったかたちで実施できるように努力してまいりたいと考えております。学校がどうしても普通教室の余裕教室がなく多目的教室だったらという状況だったものですから、字のほうに協力依頼をしまして協議をしまして使わせてもらっているのですけれども、多目的教室を何とか工夫して活用できないかも含めて検討してまいります。以上でございます。
○議長 中村 勝君 15番 大城真孝議員。
○15番 大城真孝君 今、教育長が言いましたように、地域で交流させるために公民館を利用しているのかと思いましたけれども、区長の話を聞きますと教室が足りないからという言い方だったものですから、区長としてはまだ理解していない段階です。やはり地域の公民館を使う場合は、一方的にではなく責任者の区長ときちんとした協議をしなければ、部落の評議員会にしても区長との協議で終わっているのだとなって、そしてまた議会報告会のたびに区長が手を挙げて質問をなさる。そうなると、皆さん方は押し付けで事業を進めたのかと思う面もありますので、地域を利用する場合は、ぜひその責任者と十分なる協議をやっていただきたいと要望して終わります。
2点目に入ります。クサティ森等保全に関して、公民館で評議員に説明したこの案は、実施計画案になっているわけですよね。そうなのか、そうではないのかお答え願います。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。今年の1月に地元評議員会に計画説明会をしました内容のとおりで、今年度から工事実施をする予定となっております。工事につきましては、発注前に再度、評議員へ各年度の計画を説明してから現場サイドには入っていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
○議長 中村 勝君 15番 大城真孝議員。
○15番 大城真孝君 確かに皆さんの計画は、緑地公園も一部入っていますよね。区画整理区域内の緑地公園という部分も入っていますよね。ただ気になるのが、確かにこれは一括交付金を使っての事業だと思いますけれども、そうなってくると観光なさる方の散策路として使うだろうと思いますが、皆さんの計画のなかに1カ所もトイレが入っていないのです。散策路として使うときには、外部から人がいらっしゃる所ですからまず一番必要なのは駐車場・トイレなのです。山の中でやりなさいでは通らないでしょう。ウォーキングも一緒ですけれども、散策していて一番困るのはトイレです。ウォーキング路を造るときにはトイレ、散策路にもどこか一部にないといけない。この場所で字有地は山しかありませんのでおそらくトイレは造られていないはずです。この計画案からするとトイレの計画が全くないのですよね。このことについては、部落の評議員会でも意見は出たと思います。どうしてその計画に入れていないのか、理由があれば教えてください。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。実施設計によりまして、駐車場として7台。トイレにつきましてもつかざんトンネル近くで公共下水道に接続できる位置にトイレも計画してございます。
○議長 中村 勝君 15番 大城真孝議員。
○15番 大城真孝君 では、駐車場の隣にトイレを造るという考えですよね。皆さんは、散策して、この公園を今のトンネルの上まで上がってさせようですよね。地域で出た意見は、上に造りなさいというものです。今、あなた方が示している場所は、まだ下水道が接続されていません。下水道が接続されている所にトイレを造ればいいのに、いつなるのか分からない所に造ってどうするのですか。下水道につながるようにと言いますけれども、つなげない状態です。下水道につなぐ考えがあるのでしたら、下水道が整備された所にトイレを造るのが普通でしょう。そこはどう思いますか、お答えください。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。駐車場とトイレにつきましては、若干離れております。駐車場は、区画整理のほうから来ますと出口近くにございます。トイレは逆に区画整理のほうから向かいますとちょうど入口の所に計画となっておりまして、こちらはそのまま公共下水道に接続ができるということでこの位置を選定しております。以上でございます。
○議長 中村 勝君 15番 大城真孝議員。
○15番 大城真孝君 部長がおっしゃっているのは、将来は下水道につなげるという話ですよね。今つなげるのですか。どの場所を示しているのですか。
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前10時26分)
再開(午前10時26分)
○議長 中村 勝君 再開します。
○15番 大城真孝君 では、集落内から上がってくる集合住宅の近くだという認識でよろしいわけですね。はい、分かりました。以上で終わります。
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前10時26分)
再開(午前10時27分)
○議長 中村 勝君 再開します。順次発言を許します。2番 照屋仁士議員。
〔照屋仁士議員 登壇〕
○2番 照屋仁士君 それでは、通告のとおり一般質問をしてまいりたいと思います。去った5月22日、28日に第3回目となる議会報告会を開催いたしました。過去2回の報告会では、町民の皆様からの意見・提言を受けて、今年は時期や場所、そして開催内容を少し変え、より多くの意見交換が行えるよう工夫してまいりました。職員の皆様にも多数ご参加いただき、お礼を申し上げるとともに、そのなかで議論された町行政への要望や報告内容についても先日全員協議会で取りまとめ、後ほど議長より町当局へ提出していただく予定をしておりますので併せてご検討いただきますようお願い申し上げます。
さて、そのなかで町民の皆様から本町の予算の面に対しもっと詳しく知らせることはできないかとのご意見、また町の借金や財政状況についても不安の声がありました。今回の一般質問では、ぜひ町民の皆様にご理解いただけるようご答弁をお願いいたします。
それでは、通告書のとおり一問一答の質問に移ります。1.借金時計の導入を検討せよです。『平成26年度ハイさいよ~さん』によると、平成25年度末町債残高は168億3,658万円となっております。そのなかで後年度の交付税措置等で補填される額は、89億4,060万円あり、差引いたしました実質の本町の借金は78億9,568万円となっております。町民の皆様にも、町債残高の全てが町民の皆様の負担ではないことや交付税措置が受けられるよう行政も努力していることを示すべきだと考えるので次のとおり質問いたします。(1)『平成26年度ハイさいよ~さん』でも平成25年度末時点での町債残高や交付税措置額、実質の借金、基金の残高や推移についても説明がされております。さらに町民の皆様に分かりやすいように過去5年の推移等を一目で理解できるように『ハイさいよ~さん』で工夫できないかについてお伺いいたします。
○副町長 国吉真章君 それでは質問事項(1)町債の残高について過去5年間の推移を工夫して『ハイさいよ~さん』で示せないかということでありますが、町財政の運営に対しての貴重なご提言については感謝申し上げます。『ハイさいよ~さん』の資料編において過去10年間の町債残高の推移について掲載してあります。今後さらに町民に分かりやすい資料を提供できるよう工夫してまいりたいと思います。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。そのご答弁のとおり、過去10年間についてはそれぞれのところで細かく示されています。私も調べて非常に参考にさせていただきました。ただ、これも報告会のなかで質問があったのですけれども、借金の総額だけを見てこんなにいっぱいあるのかという誤解もあったものですから、そのなかには交付税措置額や実際に支払わなければいけない借金も示されていますけれども、それについては単年度になっているわけです。ですから、私からも案として示させていただきましたが、各会計の予算、徴税、町債、基金など実質の借金を掴むためには比較対照する必要があるのではないかと考えております。私の質問の趣旨からしますと次のような表が考えられると思うのですが、まず平成21年から平成25年までの経過を横軸にして、縦軸に各会計の合計、一般会計から特別会計までありますので各会計の合計、それに伴う町債の残高、そして交付税が措置される額、そしてこれを差引した実質の借金総額が出てきます。また、参考に貯金であります基金の残高も併せて示していただくことで実質的な町の財政状況が分かるのではないかと思いますので、これについてどうお考えかお答えいただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。毎回、非常に貴重なご提言をいただき感謝申し上げます。議員が今おっしゃられたことは資料でも事前にいただいており、非常に良い資料だということでぜひ参考にさせていただきたいと思っております。町債につきまして、借金というのは事実ではあるのですが、これに対する交付税措置、例えば会社のような経常経費の運転資金とは意味が違っていて、必ず建設事業債の反対側には投資されたハードの社会資本があるということもございますので、起債はなぜ起こすのか、どういった趣旨で行うのか、そういったものも含めて丁寧に分かりやすく説明していく必要もあるかと考えております。議員が提案されたグラフについても、今後そのようなかたちで分かりやすく表現させていただきたいと考えております。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。分かりやすくするために今後も努力していただきたいと思うところでございますけれども、この表を作ってみて非常に感じた点もあります。過去5年間で見るとまず予算の総額が159億円から平成21年度時点で187億円というように大きく予算が動いている。それに伴って町債の発行額も約17億円増えているわけですけれども、では17億円も借金が増えたのかと言ったらそうではなくて、実質の借金については約4.4億円しか増えていないわけです。そういった部分では、私もただ借金が増えていくことに対する懸念だけではなくて、それに対して町行政も努力しているよというところがやはり町民の皆様にも示していくべきではないかと考えております。そのような私の理解で正しいのか、行財政の努力という点も評価できるのかについて見解をお伺いしたいと思います。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。確かに示されたとおり17億円の借り入れに対して交付税措置を考慮しますと実質の起債額は4.4億円ということでも非常に分かりやすく示していただきましてありがとうございます。議員ご指摘のとおり、できるだけ交付税の算入率が高いもの、それからそれがあるものを基準に借り入れは行っているつもりであります。今後もそこは配慮しながら、最大限負担ができるだけないような起債の借り入れ方をしてまいりたいと考えております。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 私たち議会も当然チェックをして、理解して毎年の予算組みを見ております。ただ、町民の皆さんにどう示すかという点が必要なことだと思います。実質的なものもそうですし、努力も示していく必要があると思いますのでそのようにお願いしたいと思います。
2番目に移ります。多くの行政需要ですとかインフラ整備、そして近年では一括交付金への対応など町債の発行額が増えるのはやを得ない部分も確かにあると理解しています。ただ、実質の借金については、減らしていかなければいけない。これは当然のことだと考えております。それについてどのように取り組んでいるかお答えいただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 2点目の実質の借金を減らすためにどのように取り組んでいるかという質問でありますが、まず町債の活用の意味は財政負担の年度間調整、それと世代間の負担の公平が図られ、計画的で効果的な財政運営ができることであります。今後も建設事業等の際には、有効に活用していく考えであります。しかしながら、町債の安易な発行は、後年度の財政負担を増すことになるため、元利償還金に対して地方交付税措置のある有利な地方債の活用に努めてまいります。また、毎年度の臨時財政対策債を除く町債の借入額は、元金償還額以下となるように努めてまいります。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 どのように取り組んでいるかの質問に対してのご答弁でしたので、先ほどもあったように実質の借金についても極力増えないように抑えて努力されていることも含めてご答弁いただいたと思います。それでは、現状、努力はされていると、ではなぜ実質の借金を減らすことができないのか。さまざまな要因があると思います。当然、人口も増えていますし行政需要も増えている、そういうところが想定されるわけですけれども、現状として行政として今どのように考えているのかお答えいただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。先ほど副町長からもございましたが、償還元金のプラマイで言うと借り入れがゼロ以下になると、そのプライマリーバランスを保っていくのは当然大きな基本としては持っております。ただ、議員からもご指摘があったとおり、人口増、それからより若い世代が多く町内には住まわれていますので、教育とか民生関係、いわゆる起債の種類で言えば学校の大規模改修、それから法人保育園の建て替え、実はそれについては交付税の措置がない起債がございます。どうしても交付税措置を借り入れしたいのですが、事業の種類によっては制度的に交付税の算入がないものがございます。そういった点から、行政需要に対応していくためには、いかんせんと言いますかどうしても財政負担を強いるべき必要もあることから、大基本にある償還元金よりは少なく借りるというようなものが崩れることも年度によってはあるとご理解いただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 答弁、ありがとうございます。想定しているとおり、まず一言で言えば行政需要が増えているということだと思います。先ほどからもお話しているように、非常に努力をしているのは私たち議会も理解しているところなのですね。ただ、やはりこれからも増えていくだろうという行政需要に対して、僅かではあれ現状としては借金が結果として増えていることに変わりないのかと思います。
そのような視点から次の質問に移りたいと思いますが、今まで言ったとおりさまざまな行政改革に取り組んでいると理解しています。ただ、その姿勢を町民の皆さんに分かりやすく示す必要があると考えています。その行政も意識しているというその一端として、借金時計というシステムがあって、私もそれを見てこういうところでこのように示しているところがあるのだなと感じました。それについて賛否あるところだと思いますが、まずその意識を示す方法として借金時計を導入して、さらなる財政健全化を示すことができないだろうかという点についてお答えいただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 国吉真章副町長。
○副町長 国吉真章君 それでは、質問事項の(3)についてお答えします。ご提案いただきました借金時計でありますが、これは町内における町債残高の推移を分かりやすく公表する方法として参考にさせていただき、今後より分かりやすい公表を検討してまいりたいと思います。ホームページで他の市町村の事例を実際に見てみました。起債の総額を年、月、時間、分、秒で数字が変わる表現で、確かに分かりやすいと言うのですか、時間とともに減っていく事例あるいは増えていく事例があって非常に分かりやすいと思いました。これを参考に、町でも今ご質問の起債残高についてより分かりやすい方法を検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 今回の質問に至ったのも町民の皆さんといろんな機会でお話するなかで、新聞やマスコミ等で公表されている県内外市町村の財政力指数はじめいろんなものを見て他市町村と比べて南風原町は財政が豊かだとか、南風原町は人口も増えているから税収も大丈夫などとの声もよく聞えるところであります。そういったところは、議会としても行政としても決して楽観せず努力しなければいけないと説明はしておりますけれども、なかなか響いていないのかということも現状として感じております。わざわざ借金時計というように不安を煽る意図ではないのです。確かに副町長がおっしゃったように、増えていく部分、減っていく部分、そしてそのスピードと額についてもありますけれども、現状としてやむを得ず借金が増えている状況ですが、これを増える状況に転換させたときに町民の皆さんが最も目に見て分かりやすく示せるのではないかという意図で提案させていただきました。以上、申し上げているとおり行政もさらなる財政の健全化を目指すというご答弁もいただいておりますが、その必要があると私も考えております。その点で少し、今後の展開とか分かりやすく示す方法についてもしお考えがあれば併せてご答弁いただければと思います。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。先ほども答弁いたしましたが、議員おっしゃるように現実の財政運営としましては、できるだけプライマリーバランス、償還元金よりも借り入れはプラスマイナスゼロ以下を堅持するのは当然でございます。それから、人口増の地域であるのはまた事実であります。税収も町民の皆様のおかげで着実にと言いますか増えてはおります。トータルとしての南風原町財政の中身、それも分かりやすく示していく工夫が必要だと思っています。ご提言の借金時計は、私も直接他県のものを見せていただきました。これはたぶん年度間で借入元金が次の償還よりも減ったら減っていくし、何らかの事情で増えれば増えていくような形にはなると思います。見た目は非常に分かりやすいし良いものだとは感じました。ただ、この説明書きのなかで、これは元利償還金が交付税は入っていませんとか臨財は入っていませんとか、それによってトータル、借入額と償還額の関係というようなものもあります。そういったこともありますので、どういったもので実情として分かりやすく説明していくか、これは行政用語の難しい点もあるのですが、いかに分かりやすく今後示していけるか。それはまた提言も採用させていただきながら、今後もより分かりやすくする努力をしていきたいと考えております。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。趣旨は、総務部長が最後におっしゃったように本当に町民の皆さんに理解してもらえるような視点が必要だと考えております。私たちも分かっているつもりなのですけれども、説明して伝えているつもりなのだけれども伝わっていないなというところもあったものですから、そういった部分で町民の皆さんの理解を広げるというのも私たちも報告会で意見交換をしてみて分かったところもありますので引き続き努力いただくようお願いしたいと思います。
次に2番に移ります。歴史教育の現状はというところです。私もこの1年半ぐらい前から、ラジオ等で有名な亀島 靖先生を講師に招いて琉球の歴史や人物史についての勉強会を月1度、有志のメンバーで開催させていただいております。そこで学ぶ内容については、これまで小中高や大学の専門誌で習ってきた内容よりもとても充実していて日本と沖縄の関係やこれからの地方としての生き方にも通ずるものがあるように感じます。私も学生時代、そんなに勉強はできる方ではありませんでしたけれども、小中と副読本などをとおして沖縄の歴史を学んだと記憶しています。さて、その歴史教育ですけれども、やはり本町に住む子どもたちにとって自らが生まれた沖縄県や南風原町がどんな歴史をたどってきたのか、自分たちの親や祖父母、またその先祖はどのような生活を送り今自分たちが置かれているのか、そこに興味を持てるような教育が必要ではないかと考えております。そのような観点で質問いたします。まず1番目です。本県は、言うまでもなく日本本土とは違う歴史背景を持っております。近現代史においても歴史教科書の問題は、非常に注目されております。また、昨今、中城村では、独自で琉球史を学ぶ「ごさまる科」などの設置がされたと報道されております。本町、また本県では、歴史や沖縄の近現代史はどのように教えられているのかご答弁をお願いします。
○教育長 赤嶺正之君 それでは、照屋仁士議員のご質問にお答えします。(1)でございますけれども、中学校におきましては、歴史教科書のなかで琉球及び沖縄を扱っており、5乃至6時間程度指導をしております。本地区が指定している教科書は、沖縄関連が多く記載されています。資料集も沖縄県版を使用しているので、授業のなかで琉球及び沖縄を多く扱っております。また、慰霊の日に関連した戦前・戦中・戦後の授業は、毎年行われております。小学校におきましては、6年生の歴史の授業で、江戸時代のところで琉球のことが扱われております。4月28日、5月15日、6月23日、10月10日、10月12日等についての授業を設定したり、地域の方々による講話も行っております。教科書と併用して副読本『沖縄県の歴史と政治』を利用して、港川人の時代から復帰のところまで学習しております。琉球の大航海時代についても授業をしております。それから、平和学習を中心に総合的な学習の時間で歴史等に関する調べ学習なども行っております。以上でございます。
○2番 照屋仁士君 ご答弁ありがとうございます。教科書については、あとで触れますけれども、まず基本的に学校での授業内容というのが私の推定なのか分かっている範囲で言いますと文科省の学習指導要領等で定められていると理解しています。そこで、全国的な歴史教育の内容と本県における内容、また本町における内容などで違いというものがあるのかどうか。基本的には全国統一の要領になっているのかと考えるわけですけれども、そのへんいかがでしょうか。どうなっているか教えていただければと思います。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 再質問にお答えいたします。教科書が全国的にどのように扱われているかのご質問でございます。教科書につきましては、文科省の検定を経た教科書から採択されますので、内容につきましては図、写真、扱う量などの少しの差はあるものの全国的にほぼ同じ内容の学習をすることになります。また、副読本などについても郷土について学習するなどの幅を持たせることができるとしております。以上でございます。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 教科書は次の(2)で触れますので、ここで知りたいのは教科書ではなくて学習指導要領ですとかそういったものの内容なのです。例えば国ではこういう制度がありますと、あるいは県にはこういう制度があります、本町はこうしていますというように、どのような制度に基づいて授業内容が定められていて、また先ほど言った歴史問題については県や市町村でもあるのですけれども、県や市町村の裁量がどの程度及ぶものなのかどうか、そういったことを説明していただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 山内庸子教育指導主事。
○教育指導主事 山内庸子さん ではお答えします。この学習指導要領というのは、学校に示されます。私たち教師は、つい最近まで現場にいましたので、こういう教科ごとの学習指導要領の解説ということで、これが私たちの基本だと教えられています。まず学校に関しては教育基本法が一番で、それに伴って学校教育法のなかで教科書の使用義務が定められています。ですから、教科書を使わなければいけない、教科書を中心に授業をすることになっています。それから、教科書発行臨時措置法というものがありまして、教科書は教科指導のために主たる教材と定められています。それから学校教育法施行規則、それから学習指導要領においてそれぞれの教科の授業内容について、それから時数についても決められています。例えば中学校の社会で言いますと、中学校1年では主に地理を習いますが115時間、それから歴史に関して115時間、公民に関して140時間、最低それだけの時間は確保してくださいよということと、最低これだけの内容は扱ってくださいということがこのなかにあり、こういう目標で行いますと示されています。これを勝手に県の段階で変えるとかそういうことはできません。さらに先ほどあったように、副読本がありますが、このなかにも郷土のことについても学びましょうという条文があるのですね。では、その郷土のことについては文科省から資料は提示されませんので、それぞれの地域で副読本を作成することになります。例えば南風原町では「わたしたちの南風原町」。これは3、4年生が使いますが南風原町内の先生方で作ったりします。それから、中学校でも教科書プラスアルファとして現物を持ってきていませんが歴史資料集という沖縄県版とそうでないものがありまして、沖縄県版で琉球について8ページ程度ですがかなり古いところから近現代史まで扱われているものがありまして、そういうものが使える。それに関しては、法的にあまり縛りがありませんが、ただしそういう副読本を使うのだということに関しても教育委員会の許可を得ると言いますか、教育委員会とともに扱うということになります。
最後に、元に戻りますが、県や市町村の裁量はどのくらい及ぶのかという件に関しては、教科書については採択の段階で裁量がありますので、自分たちが教えたい内容がどれぐらい入っているか、島尻地区の内容に関しては沖縄県のページがかなり割かれています。会社の名前は言いませんが、そういう会社が扱っている教科書を使うとかそのへんで裁量権があると言うか、内容に関してこうせよ、ああせよということはやはりこれを中心にしなければいけませんので学習指導要領にある程度縛られていると捉えていただきたいと思います。以上です。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 分からない部分もあるのですが分かりました。聞いている人にも分かりやすくするために、教科書のことはあとでということで、内容について質問をしたのですけれども、答弁の最後にもあったように県や市町村の裁量については教科書の選択にしか及ばないと、そういうことでよろしいですか。
○議長 中村 勝君 山内庸子秀教育指導主事。
○教育指導主事 山内庸子さん 内容については、学習指導要領に定められているとおりとご理解いただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 繰返しお伺いします。それは先ほどお伺いしましたので、僕も詳しくは分かりませんけれども、もし県や市町村の裁量というものが及ぶとすればその教科書の選択といったところにしかないということでよろしいのかどうかもう一度お願いします。
○議長 中村 勝君 山内庸子秀教育指導主事。
○教育指導主事 山内庸子さん まず基本的な内容は、学習指導要領ですのでそこに私たちが入る余地はないのですが、郷土のことに関してはそれぞれの県や地域、市町村で内容については取り扱うことができますのでそこに関しては裁量の余地があります。
例えば、学習指導要領の内容に関与する余地はないと先ほど申しましたが、学習指導要領のなかでこういう単元があります。例えば小学校3年生ですけれども、「もっと知りたいみんなのまち」という単元があります。そのなかには、私たちの町はどんなまち、私たちの町の様子、町の紹介ポスターを作ろう、となりますと、これは南風原町について調べたり学んだりするということで、学習指導要領のなかではありますがそのなかに私たち町が関与する部分があるということです。そのときに先ほどの副読本なりまたは地域の人材なりを活用することになります。それから、3年生の3学期では、「探ってみよう昔の人のくらし」という単元があります。そこでは町の人たちが受け継ぐ行事だとか、それから昔の道具を調べてみようという単元が15時間ありますので、そのなかも私たちの市町村で関わっていくところになります。ですから、先ほどの学習指導要領の範囲に関しては私たちが関与できませんが、そのなかの細かな部分で私たち市町村が資料を作ったり、進めていったりするような部分がかなりあると考えていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 指導要領に定められている以外に学べという主張をするつもりでこの質問をやっているわけではないので、現状としても最初に答弁があったように中学校、小学校においてもいろんな取り組みがされていることは理解しております。そのようななか、先ほど最初に挙げたとおり、中城村では文科省より学校独自で時間割を編成することができる教育課程特例校制度の特例校指定を受けて、今年度から小学校、そして来年度には中学校でも実施をしていくとあります。内容としては、先ほど挙げた「ごさまる科」というように郷土の歴史を勉強する時間を割くというような流れだと思います。今その学習指導要領のこととか市町村の裁量が及ぶのかという質問を繰返ししたのは、それだけでは足りないと考えて新たな教育課程特例校制度というものを受けたのだと私は理解できますし、また先日実際に中城村の教育委員の方にもいろいろお話を聞いてその評価等も非常に良いことだと伺っております。そういう制度的な流れですとか、また本町教育委員会としての評価や見解について教えていただければと思います。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 お答えいたします。まず教育課程の特例校制度に関しましては、これまでの部長あるいは指導主事の答弁がございましたのでその件はさて置きまして、教育委員会の評価というようなご質問にお答えいたします。特例校制度に関しましては、特色ある学校づくりの観点からは非常に有効だと考えておりますが、現状と言いますか現実的な考え方になりますと、先ほど指導主事からもありましたように現在は生活科あるいは総合の時間等で地域の歴史あるいは地域の人物等の学習はしているわけでございます。それ以上の習熟度を深める観点で特別にこの教科を設けることになるわけでございますけれども、そうしますと学校におきましては例えば週何時間とか年間で何時間という時数がございまして、それは先ほど主事からございましたように学習指導要領に基づく教科指導がその時間帯で行われるわけです。それにプラスして新たな教科が加わるということでございますので、やはりその年間の時数のなかでやりくりをしなければいけないということで例えば生活科のなかから1時間あるいは2時間削ってくる、あるいは総合的な学習の時間を全てこの地域の歴史あるいは人物について充てることになると現実的には思っております。そういうことからしますと、一長一短あるのではないかと現段階では考えております。もちろん、地域の特色ある学校づくりの観点からしますとそれなりに勉強を深めていく必要がありますのでその点で非常に有効だとは思いますけれども、本町の教育委員会としてはまだそこまで議論もしておりません。また、他市町村の評価も現状では難しいと考えております。それに代わると言いましてはなんですけれども、本町としましては町独自の研究指定校も設けております。例えば平成24年、平成25年の2カ年間、翔南小学校が地域の教育資源を活かした特色ある学校づくりということでその研究授業に取り組んでおりまして、地域を巻き込んだ学校づくりを実践した経緯がございます。そういうことで、この文科省の許可・認可を申請する前に、本町としてできることはまずやってみたいと私自身考えておりますので、それぞれの学校でその地域の特性を活かした学校づくりを推進していきたいと考えております。以上です。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。一問一答で、あとで質問しようと思っていたことにも答えていただいている部分がありますけれども、本町の取り組みを紹介していただいて、その紹介を受ければこれがこれに当たるなということで確かにそうだと評価できる部分があると思います。引き続き、本町あるいは本県の独自性を保つような授業、教育に取り組んでいただければと思います。
それでは次の質問に移ります。先ほどからその内容も出ておりますが、学習指導要領の中身、内容について、または教科書の中の琉球史や沖縄史について十分な内容になっているのか。また、副読本がどのようにそれに利用されているのか。先ほども説明にありましたが、教科書が主たる教材だと、そのなかで副読本もあることは分かりましたけれども、その具体的な活用について、例えば何時間、何回ぐらいあるとかそのようなことを答弁は重なるかもしれませんがもう一度お願いしたいと思います。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 それでは、(2)のご質問にお答えいたします。教科書内での琉球史や沖縄史の内容が十分かにつきましては、基準はございませんので判断は難しいところでございます。そして、この内容等につきましては、各学校、各教員によるところが現状でございますので、質・量という点でもなかなか判断は難しいところでございます。また、教科書における取扱は、小学校、中学校でも異なっております。小学校の教科書に比べると中学校の歴史教科書のほうが内容は多くなっています。また、沖縄県版の社会科資料を使用しておりますので、教科書で足りない部分を補うことができます。それから、小学校の副読本は、後半に50ページほど本町も含めてでございますが沖縄の歴史・産業や偉人等についての取扱もございますのでそういったかたちで活用がされているということでございます。以上でございます。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 それでは、教科書については、八重山地区の教科書選定協議会などが話題として全国的に上がっているわけですけれども、本町においては先ほど島尻地区と答弁のなかにありましたけれども、教科書がどのように選定されるのかどうか。そしてまた副読本についても小学校では本町で作成したとか、また今の答弁のなかで沖縄県版のというような表現がありましたけれども、その副読本については県が作っているのか本町でも作ることができるのか、それともその地区で協議するのかなどそういったことも含めて今使っている小中の教科書がどのような選定で採用されているのか副読本も併せてお答えいただければと思います。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 お答えいたします。まず副読本に関しましては、担当部長あるいは主事から答弁がございます。私からは教科書の採択に関しましてお答えいたします。島尻地区の採択地区協議会は、島尻教育事務所管内の市町村教育長と保護者代表ということで11名のメンバーで構成されております。例えば平成27年度から使用される小学校の教科書の選定作業が今進んでいるわけでございますが、それを例にお答えいたしますと、まず基本的に6月2日から各市町村教育委員会あるいは各市町村小学校で教科書の展示が行われております。それが20日ごろまで行われまして、そのあといろいろと調査員が調査いたしますけれども、その後、7月18日から8月8日のあいだに調査結果を検討いたしまして、各市町村教育委員会で教科書を決定するということでございます。その前に、採択地区協議会でも決定をするわけでございますが、採択地区協議会で決定した教科書が各市町村の教育委員会に答申として通知されてきますので、それに基づいて各市町村教育委員会は教育委員会を開きまして決定するというような事務的な流れでございます。
島尻地区協議会におきましては、先ほど申し上げましたように調査員がおります。管内の各小学校から選抜された先生方30名いらっしゃいまして、その先生方が国語、算数、理科、社会、生活、図工、保健、音楽、それから書写等々各教科について調査研究をいたしまして、われわれ採択地区協議会のメンバーに報告がございます。その報告のなかで一番望ましいと言いますか、上位の教科書が提案されますので、どうしてこの教科書が良いのかを教育長皆で調査員にヒアリングをいたします。そういった手続きを経まして、最終的に採択地区協議会で決定をする流れでございます。この調査員からのヒアリングというのが本地区の特色かと私は考えておりますが、島尻地区はこの調査員の調査を重視していると捉えられると思っております。副読本の編成過程については、担当から答弁いたします。以上です。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 町で作成している副読本につきましては、先ほど主事からもございましたように3年、4年生が使う副読本を作成してございます。「わたしたちの南風原町」という副読本を作成しています。これは教科書の改訂時期に新たに副読本も改訂していきます。作成にあたっては、各小中学校から先生方を副読本の編成に代表で出てもらって、教育委員会の主事を中心に作成を手掛けているところでございます。また今度も教科書改訂がございますので、これについて新しい副読本を作成になるということでございます。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 教科書の採択地区協議会から教科書の、また副読本作成の実務的なところまでお答えいただきましたが、採択地区の話を出したのはまず基本的には教科書を主たる教材として学ばなければならないところで沖縄の歴史教育ですとかそういったところも勘案されて選定されているものだと理解するわけです。副読本を出したのは、教科書も報道等でもあるように中身が変わったり記述が減らされたりそういったことも懸念されるわけです。そういった教科書の内容を補うかたち、また学習指導要領のなかで定められているその地域のことを学びましょうというようなものを補完するかたちで副読本が作成されたり、そしてまた選定されたりというようなことをしているのではないかと理解するわけですけれども、そのような流れでよろしいのかどうか。そうであれば、当然、教科書の内容として不十分であるから県が作っている副読本を採用しようとか、若しくは県が作っているもので賄えない部分を本町で作って採択していこうという流れが出てくるのではないかと推測されますが、そのようなことでよろしいかどうかお答えいただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 お答えいたします。基本的には私もそのように考えております。ただ、現実的に申し上げまして、今回、小学校の教科用図書の目録として届いておりますのが247冊でございます。これが出版会社として14社です。これを全部、先生方が目を通すわけでございます。そのあとにわれわれ教育委員と保護者の代表も交えてヒアリングをしまして、この会社のこの社会の本はどういったところが良いのか、沖縄の内容はどの程度入っているか、郷土の歴史についてどの程度触れているか、もちろんそういったこともわれわれはヒアリングいたしまして、先生方が選んだ教科書が本当にそのようになっているのかどうかも検討するわけでございます。併せまして各学校にも展示してございますので、この調査員の先生方以外の先生方もご覧になってそれなりの意見も提出してきますし、それもわれわれの審議会に上がってきますのでそれも検討しながら教科書を選定していくというようなことでございます。各教育長の考え方のなかに、先ほど議員がおっしゃったような内容も念頭にあれば当然そういったものもヒアリングのなかで出てくるものだと私は認識しております。
副読本に関しましても、部長から答弁がありましたように指導要領を補填、補完する大きな内容がございます。例えば教科書では一定程度の量しか含まれていないので、これはややもすると教員のやり方によってはあまり触れない可能性もあるとかいう判断も無きにしも非ずでございますので、その点は副読本をしっかり作っておけばそこでまた先生方にしっかり取り上げてもらえるという観点で副読本の作成も非常に重要だと思っております。先ほど部長から答弁がありましたとおり、各学校の社会科の先生あるいは教頭先生、校長先生が先頭になって編成しているということですのでご理解をお願いしたいと思います。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 教科書選定の実務について、調査員の皆さんの調査を尊重して採択しているというのは非常に良いことだと思います。ただ、併せて270あまりのなかから現実的に中身を全部調べてすることは難しいと実務的なところもありました。この流れを聞いているのは、そういうことであれば今の教科書についてはある程度そのような流れで理解できますけれども、やはり学ぶべきとか主体的に子どもたちに伝えたいことというのは副読本などをとおしてやっていかなければいけないだろうと思います。本町でも独自の取り組みをしていますけれども、それの元となる資料については、例えば主体的に取り組んでその副読本になるのかと理解しています。そうであれば、その副読本の内容については県に求めていくとか、そして県に求めても補完できないところを本町でも新たに作っていくとかそういうことが必要だと思います。先ほど本町では先駆けて3年生、4年生の授業で本町独自の副読本を活用しているとご答弁がありましたけれども、そういった伝えたいこと、教えたいことを主体的に盛り込んでいくための手段が中城村にあるような手段だったのかと捉えております。そのへんは既に取り組んでいることではありますけれども、子どもたちの授業を増やせと言っているわけではないのです。子どもたちの負担もあることですので、バランスよく歴史教育が行われるように資料で充実させるとかそういったことも含めて県に求めていく、また市町村で議論していくことが必要になると思いますのでよろしくお願いします。最後に、そういうことを踏まえて本町の歴史や偉人について学ぶ機会はあるかご質問です。先ほど一部答弁もあったかと思いますが、もう一度お願いしたいと思います。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 それでは(3)のご質問にお答えします。中学校においては、社会の授業での指導は特にありませんが、総合的な学習において生徒個々のテーマによっては調べ学習をすることもあります。小学校においては、4年生が教育委員会の作成している副読本で本町の歴史や偉人について学んでいます。偉人では、南風原の先人たちとして新垣弓太郎、金城哲夫、飛び安里を掲載しております。3年生以上は社会だけではなく総合的な学習の時間も活用して文化センターの見学を行い、疎開移民に関わった先人たちについての学習も行っております。学校支援地域本部事業との連携により、町の歴史や偉人についての学習が深められております。以上でございます。
○議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございました。今後も先ほど申し上げたより良い教科書、副読本の選定ですとか、本町で取り組んでいる副読本の作成についても3、4年生とのご答弁もありましたけれども、それぞれの学年でそれぞれの学年に合った内容を検討することも必要かと考えます。おおまかで結構ですので、今後もこのような取り組みをさらに充実させていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 ただいまご質問がございましたように、今後も副読本等そのへんの表現を取り入れて子どもたちには教えてまいりたいと考えております。
○議長 中村 勝君 暫時休憩します。
休憩(午前11時31分)
再開(午後1時00分)
○議長 中村 勝君 再開します。宮城清政議員が都合により退席しております。この際、会議録署名議員の追加の指名を行います。6番 赤嶺奈津江議員を指名いたします。
通告書のとおり順次発言を許します。10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 午後の質問を行いたいと思います。一通り質問をいたしまして、そのあと再質問は一問一答で行いたいと思います。
1点目は、南風原南インター周辺の土地利用計画についてお伺いいたします。北インター、南インター周辺の土地利用については、多くの議員の皆さん方がこれまでも質問を行ってきているところであります。北インター周辺については、大型スーパー、映画館などできていてこれから町道3号線と町道43号線の間の開発が今後必要かと思われますけれども、これまで北インターについてはそれなりの土地利用がされていると考えます。しかしながら、南インター周辺の利用が進んでいないのが現状ではないでしょうか。総合計画では新規産業ゾーンとなっているのですけれども、なかなか土地利用がされていない。そこで、南インター周辺の土地利用計画が今どうなっているのかお伺いしたいと思います。(2)平成27年度オープンですか、南インター周辺にはファーマーズマーケット開発が予定されております。それ以外の計画があるのかどうかお伺いしたいと思います。それから(3)市街化区域とすべきだと思いますけれどもどう思いますか。そのへんをお伺いしたい。
それから2点目に、町内公園の駐車場整備についてであります。町内の公園整備が進んで特に遊具等が充実してきております。そのためでしょうか、公園利用者がだいぶ多くなってきています。駐車場の整備が急がれると思いますけれども計画をお聞きします。(1)本部公園の駐車場は、駐車台数も多いのですけれども、しかしながら利用者が多くて道路まで車が溢れていることも多く見られます。今後も駐車場を増やす考えはないかどうか、その点をお伺いしたいと思います。(2)宮城公園、神里ふれあい公園、山川体育センター、津嘉山公園等、駐車場の整備計画はどのようになっているかお伺いしたいと思います。それから、公園の駐車場として桁下の利用はできないかどうかをお伺いしたいと思います。宮城公園にも高規格道路が通っていて桁下利用、それから黄金森公園の所にも桁下があるわけですが、そこを公園の駐車場として利用できないのかどうかお伺いしたいと思います。
それから3点目に、介護保険制度の改悪を許さないためにということで質問いたします。医療介護総合法案が参議院で審議されています。衆議院では5月14日に通過しておりますけれども、介護保険制度の見直しでは2割負担の導入や特養ホームの利用制限、それから要支援1・2の介護外し等が明らかになってきております。その介護保険制度の改悪を許さないために声を上げるべきではないでしょうか、この点をお伺いしたいと思います。
それから、北丘小学校大規模改造工事についてであります。1点目に、北丘小学校仮設教室もできて改造工事が始まっているのですけれども、その仮設教室の使い勝手の実態はどうなのかをお聞きしたいと思います。抽象的に使い勝手はどうかとしているのですが、まだそんなに暑くはならないのだけれども、プレハブ教室ですから暑さ寒さの関係とか騒音の関係とか子どもたちの教室の距離の問題とかそのへんの使い勝手はどうなのかと思いましてお伺いしたいと思います。それから、(2)改造するにあたって将来の30人学級や児童数の増に対する対策はできているのかどうかお伺いしたいと思います。以上、大きい項目4点を質問いたします。よろしくお願いします。
○副町長 国吉真章君 それでは、1点目の南風原南インター周辺の土地利用計画はどうなっているかでありますが、それについてはご指摘ありましたように第四次総合計画の基本構想では新規産業ゾーンと位置付けをしています。同地区は県道レベルの土地利用の動向あるいは広域的な交通幹線軸の結節点、当地の埋蔵文化財等の多様な前提条件を考慮しつつ新たに産業が集積する空間づくりと位置付けており、なかなかこれまで土地利用計画が計画どおり進んでいないのが現状です。その後の進展としましては、JAファーマーズマーケットが近々オープンする計画があります。それを受けての2点目のファーマーズ以外の計画があるかということですが、ファーマーズマーケットの背後地や隣接地は農用地となっていることから、現時点ではファーマーズマーケット以外の計画はありません。(3)の市街化区域とするべきだというご質問ですが、南インター周辺を市街化区域にするためには、県の都市計画運用指針に基づき見直し基準が定められており、そのなかに人口集中地区(DID地区)であること、または既成市街地に連続し現に相当程度宅地化している区域であることなどいくつかの基準が定められております。また、国道507号バイパス沿道は、農振農用地区域が除外をされているものの沿道背後地については農振農用地区域となっており、現時点において市街化区域にするのは困難であると思われます。
2番の町内公園の駐車場整備計画の(1) 本部公園の駐車場についてでありますが、本部公園については、平成22年度に再整備事業にて駐車場の整備を行ってきましたが、土日において公園利用者が多く道路上への駐車が見受けられ通行車両への障害が出ている状況があることから、駐車場の増設を含めて検討をしてまいります。(2)の宮城公園、神里ふれあい公園、山川体育センター、津嘉山公園等の駐車場整備計画ですが、まず宮城公園、神里ふれあい公園については隣接地に駐車場の整備が可能か検討をしているところであります。津嘉山公園については、平成24年度に実施設計を終えており、津嘉山中央線沿いに24台、国道507号バイパス沿いに10台で合計34台の整備計画となっています。山川体育センターについては、現在のところ駐車場整備の考えはございません。現況のとおり使用していただきたいと思います。(2)の桁下利用についてでありますが、高速道路の桁下を公園の駐車場としての利用については、公園より距離があるため利用実績は低いと考えています。また、公園事業での整備が困難なことから、現時点において整備計画はありません。
質問事項3点目。介護保険制度の改悪について見直しの問いですが、現在、介護事業所にて要支援1・2に対して行われている訪問介護と通所介護は、現在の介護予防事業見直し後、日常生活支援総合事業となり利用者に多様化した事業に移行して利用しますので、極端なサービス低下はないと思われます。以上です。
○教育長 赤嶺正之君 質問事項の4点目、北丘小学校大規模改造についてのご質問にお答えいたします。(1)でございますが、仮設教室は本教室に比べ小さめでございます。教室が離れていて不便を来たしてもおりますが、学校と調整して進めておりますので特段授業に支障はないものと考えております。
(2)のご質問でございますが、現在の学級数は1年生が30人学級、2年、3年が35人学級、4年から6年までが40人学級で編成されております。大規模改造工事後も多目的教室が6教室ありますので、普通教室への転用が学級増には対応できるものと考えております。以上でございます。
○10番 宮城寛諄君 再質問したいと思います。総合計画でも新規産業ゾーンとなっているのですが、ただ、そのようにゾーン指定はしているのですがなかなか前に進まないところがあって、当局としてどういうふうにやろうとしているのかよく分からないのですね。企業の誘致ということで確かその係みたいなものがあったのかな。要するに、積極的に企業を誘致しようとしているのか、それとも来るのを待っている、どうぞ利用してくださいというかたちなのかこれまで全く動いていないのです。私は平成18年にもこの質問をした覚えがあるし、山川の神里良光議員もだいぶこの件を取り上げていましたし、神里博明議員も取り上げていたかな。その地域の有効利用ということでだいぶ取り上げているのですけれども、そういうかたちでゾーン設定しているのだけれどもなかなかできないのですね。皆さん方はゾーン設定をしたあと、どのようなアクションを起こしたのかお聞きしたいと思います。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。南風原南インター周辺の土地利用ということで、現在は新規産業ゾーンと設定をしております。新規産業ゾーンとは、全て第一次産業、第二次産業、第三次産業、トータル的に含めた総称となっておりまして、基本的な町の考え方としては、新たにいろんな産業関係にこちらへ来ていただいて、最終的なものはある一定の既成市街地を形成したのちに例えば市街化へ持っていきたいということです。ただ、こちらのゾーンは、ご存知のとおり全て地権者がおりまして、町がその地権者を飛び越えて企業誘致をすることはできないところがございます。開発関係に伴いまして、例えば町に打診といったものが来れば、町としても率先して行政として協力できるところはバックアップしていきたい考え方で進めてはおります。全体的にまだ沿線以外は農振農用地ということがございまして、実質的には現在もご存知のとおりそんなに進展していないのが現状でございます。今後はファーマーズマーケット建設を一つの足掛かりとして、南インター周辺の土地利用をできるだけ促進して、広くPRをしてできるだけ早い時期に産業ゾーンとしての位置付けができたらと考えております。以上でございます。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 1点目の南インター周辺の土地利用については、(1)、(2)、(3)ほとんど関連しますので関連させて質問したいと思います。新たな産業が来ればそれはそれで来て欲しいと、そういう相談があればアドバイスをすると。それから、市街化区域にどうかと言ったらそういった建物が増えてこないと駄目だと言うし、要するに地主の皆さん方がそこに家を造って市街化になってくる状態にならないと市街化はできない。それから産業も向こうから入って来ない限りは、アドバイスはするけれども特にやらないと。ファーマーズをとっても農協がそこに造りたいということでを出してそこになったと思うのですけれども、要するに町当局としては待っている状況なのですかね。その地域の開発をぜひして欲しい、有効利用をして欲しいとは何度か議会でも取り上げられていますし、そのへんの要望を皆さん方はどう受け取っているのでしょうか。それとも、地域の皆さん方、地権者の皆さん、そうでなければ山川区や照屋区、津嘉山区と相談などやったことはございますか。どうでしょうか。それとも皆さん方は待ちの状態なのか、自分たちから積極的に土地利用をしようとしているのかそこが聞きたいところなのです。どうも今は待ちの状態だと、地権者の皆さん方が家を造るならどうぞ造ってくださいと、産業が来るのでしたらどうぞ来てくださいという何かそういう感じがするのですね。そのへんはどうなのでしょうか。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。南インター周辺の土地利用におきまして、各地権者の今後の土地利用について確認したことがあるかでございますけれども、特に行政としてそこまでの確認は現時点で行っておりません。また、待ちの状態ということではございますけれども、実際には各地権者さんがおられましていろんな自分のその土地利用関係があることから、そこを飛び越して行政としても積極的に動けないところもございます。また、ファーマーズマーケットにつきましても例えばJAさんがこちらに造りたいからということではございません。実際には当初の段階で開発関係が非常に厳しいという位置だったのですけれども、その後のJA及び南風原町が一緒になっていろんな面で努力した結果でこのファーマーズ建設ができたものと私は考えております。他の地区に関しましても開発に向けてはいろんな業種関係、内容につきまして開発ができるもの、できないものがあるかと思いますけれども、ファーマーズ同様にそういった計画がもし持ち上がりましたら行政としてもできるだけバックアップして実現の方向で進めていきたいと考えております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 ファーマーズは町も入っていろいろ協議したからそのようになるのでしょうけれども、だからそのような感じで地権者なりその地区なりと相談していかなければ、いつまでたってもここは高度利用できないと思うのですね。畑のままでいいと皆さん方が考えておられるのだったらそれはそれで結構ですけれども、でも地権者や地域はそのようには考えていないですね。もっともっと利用できないのかと、なんで南インター周辺の土地が高度利用できないのかと皆疑問に思っているところなのですね。役場が動かないとなかなかできないと私は思います。地権者なりその地区なり、そのへんとの相談も必要だと思います。ファーマーズについては、農協と役場もいろいろ相談しながらやってきた。役場が入ってくればだいたいそういうかたちで業務は進むのではないかと私は思います。今後の問題ではあるのですけれども、以前にも皆さん方はそういう答弁をされているのです。地権者と話合いをしたことはない、地区と話合いしたことはない、これからだみたいなことをおっしゃっているのですけれども、それでも何年たってもずっとそのままなのです。以前にも文化財の問題などいろいろネックになっていると、生涯学習文化課ですか、担当課とも相談しながら進めていきたいみたいなことをおっしゃっているのですけれども、それだって前に進んでいない状況ですし、今のままだとあと10年、20年もそのままではないかと考えます。地域の皆さん方が、機動隊宿舎横にも自分たちで道路を開けて家を建てるというように進んでこないといつまでたってもそこにまちはできないと私は思います。皆さん方が道路も開けて家も建てられるようにすればもっと良くなるのではないかと思うのですけれども、先ほどの市街化にするにはいろんなハードルがあって既成市街地に連続し現に宅地化していないと駄目だとか人口集中地区でなければ駄目だとかなっているのですけれども、それまで待つというようなことになるのかと思います。今やっていないのでどうしようもないですから、地権者や地区と早めに相談しながらその土地利用を前に進める努力はぜひして欲しいと思いますけれども、今後もこれまでどおりの待ち状態なのかな。答弁してもらえませんか。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。ご提案、大変ありがとうございます。この南インター周辺も近年、ファーマーズも来ることからかなり周辺の状況が変わってきますので、私どもも国道507号沿線を中心としまして地権者の意向確認と言いますか、個人では開発を予定しているのだけれども自分の力ではどうにもならないという方がいらっしゃるのか、そういったものも踏まえて意向調査をさせていただいて今後の開発関係に有利にできるものか検討させていただきたいと思っております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 意向調査などもぜひ行って欲しいと思います。これまで行政懇談会が2年に1度でしたかあったのですけれども、近頃は区から出さなければ政懇談会もないものですから地域と皆さん方との交流というものがなかなか難しいと思っているのですが、十分に皆さん方で地域の声を吸い上げるようやって欲しいと要望いたします。
2点目の公園についてですけれども、チンクヮーランドとかビュウリーランドとか名前を付けて遊具がだいぶ整備されてきました。そういうお陰もあると思うのですけれども、土日になると子どもたちが集中する、その父兄の車が特に本部公園などは溢れているし、それから宮城公園も道路にまで停めるというまさに交通に支障をきたしている状態です。そういう意味では、本部公園は34、5台あるということでそれなりの台数は確保されているのですけれども、それでもまだまだ道路にはみ出すということがあるので、また今後検討していくとのことなので駐車場の増設についてぜひそうして欲しいと思います。宮城公園も台数はちょっと少ないかという感じはします。あれだけの大きなグラウンドがあって、野球はできないにしてもソフトボールなどできる状態でありますし、それから遊具も揃いまして車が多くなってきています。その宮城公園についても桁下利用ができるのではないかと思ったのですけれども、そのへんは無理なのでしょうか。先ほどの話では公園事業での整備が困難だとおっしゃっていました。それから公園より遠いため実績が低いということなのですけれども、整備をすればそれなりの利用はできるのではないかと思うのです。連続性がないから公園事業として整備ができないという話も聞いたのですが、公園事業で整備ができなければ町独自の単独ででも整備はできるのではないかと私は思うのです。そのへんを考えたことはございませんか。要するに、駐車場をもっともっと確保する意味でそのへんの努力もやって欲しいと思うのですが、どうなのでしょうか。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。宮城公園、神里ふれあい公園につきましては、先ほど答弁がありましたとおりに隣接地に再整備に向けて現在検討しているところでございます。もし隣接地に整備がどうしても無理だとなりましたら、議員ご提案の、距離的には少し離れますけれども簡易的な桁下を利用した駐車場も検討すべきかと考えます。今現在は、宮城公園で隣接地に2案を検討しております。神里ふれあい公園についても1案を検討しまして、これから再整備に向け可能かどうかについて進めてまいりたいと思います。その後の状況に応じて議員ご提案についても検討させていただければと考えております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 宮城公園は2案あると、神里ふれあい公園についても1案あるということなのでぜひ努力して欲しいのですけれども、少なくとも本部公園で34台でしたか35台でしたか、それぐらいの台数は確保して欲しいと思うのです。だいたいどれぐらい確保できるのか、宮城公園、神里ふれあい公園など案はあるのですか、どうでしょうか。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。現時点の段階では何台という具体的な数字は出ていない状況で、位置的に公園の再整備の場合は本部公園同様に一体形成の計画がどうしても必要となることから隣接地ということに限定されます。2公園とも隣接地に駐車場整備が可能な個人所有地ではございますけれどもその箇所が見当たることから、そちらをまず公園計画として立ち上げて、今後はその地権者の方々のご意見も確認をしながら進めていきたいということで、その意向確認をしようとしているところでございます。その後、ある程度具体化が決まりましたら議員のおっしゃった各公園で増設する駐車台数の関係について具体的な内容に入っていきたいと考えております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 宮城公園、神里ふれあい公園につきましてもぜひ駐車場の確保をして欲しいと思います。神里のふれあい公園につきましても、向こうの通りは通行量がそんなに多いようには感じないのですが、それにつきましても公園隣の道路は利用者の車が並んでいる状況です。駐車場にちゃんと車が収められる状況にして欲しいと思います。
それから、津嘉山公園については、24に10台で34台ということなのですけれども、多目的広場とパークゴルフ場を造る計画ですよね。確かそうだったと思うのですが、34台で十分なのかどうかです。これから造る公園ですので、できる限り駐車場を確保して欲しいと思います。特に向こうは国道507号バイパスが通っているし、それから第二団地を通る道は津嘉山中央線ですか、要するに大きい通りがあるのですね。路上駐車できるようなものではない。ましてそこに路上駐車するようだったら交通事故につながるようなことになるのではないか、今から造るわけですから今のうちにぜひやって欲しいと思うのですけれども、34台より以上の計画は全くないのですか。それともどこか考えがあるとかないのですか。34台で十分なのでしょうか。
○議長 中村 勝君 真境名元彦経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。津嘉山公園につきましては、先ほど答弁で申し上げたとおり合計で34台が今現在の計画となっております。公園関係につきましては、各公園の種別、例えばこの津嘉山公園は近隣公園という位置付けになっておりまして、基本的には半径500メートル圏内の方々の利用という位置付けであることから、他の公園を鑑みて駐車台数を増やすというのも計画上非常に難しい面もございますし、また面積的にもそう大きくないものですから、駐車スペースに取られますとパークゴルフや多目的広場がその分削られてくるということもございまして、この地域の方々とも調整した結果、最終的に押さえたのが34台となっております。整備をしながら実質的に可能であれば、1台でも2台でも増やしていければと考えておりますけれども、現在の実施設計上では34台ということになっております。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 地域の皆さん方と相談してその台数だということなのですけれども、これだけで十分足りるのか疑問と言いますか、本部公園でもそれだけあるわけですから、この津嘉山公園についてはもっともっと駐車場が必要ではないかと思います。特にこれから整備するのですから、駐車場が取れるわけです。十分に駐車場を取って欲しいと要望して終わります。
山川の体育センターについては、私の地元ですので周囲は農地、宅地ですので駐車場を取るのはなかなか難しいことは分かりますけれども、しかしながら農地の借り上げとかそういうことをしてでもできないものかと思います。例えば何か大会があったりしますと警察宿舎、要するに後ろの県道までの通りは両側に車が止められて農家の皆さん方が畑に農薬を撒くとかするときに自分の車が駐車できないというようなことが何度かあるのですね。参加する皆さん方にいろいろ注意はしていると話は聞くのですけれども、それでも両端に車が停められるということがあるのです。ですから、そのへんは何とかして欲しいと思います。私は地元ですから、確かにこのへんは難しいことはよく分かります。しかしながら、駐車場の確保は少々離れた所でも確保すべきではないかと思います。皆さんにはぜひ検討して欲しいと要望して終わりますけれども、本当に真剣にやって欲しいと思います。
それから、3点目の介護保険の制度についてですけれども、以前にもこの件で委員会に入る前の段階から質問してきて、サービスの低下につながらないようにすると町長、副町長はおっしゃっていました。そのとおりだと思うのですけれども、ただ、何と言うのですか要支援1・2を外すということは、普通の総合支援で対処できるかもしれませんが、対処できる人とできない人とがいるはずなのですね。何でこの要支援1とか要介護というものになったと思いますか。介護保険制度のなかで認定をして、あなたは要介護、あなたは要支援だというようになっているはずなのですね。そうじゃなければ外れるはずなのです。要するに、介護が必要だということで要支援1・2として、もちろん要介護よりもそれだけ軽度かもしれませんけれども、しかし重症にならないための要支援だと判定されて介護保険からの措置がされているはずなのです。それを外して各市町村に任せると、日常生活支援総合事業と言いますか、そこに任せるということにするのですね。そこがおかしいよということなのです。例えばそういう多様化した事業に移行しますのでと、多くのサービスが受けられますよという実はこれ田村厚生労働大臣ですか、その人もそう言っているのですね。市町村に任せれば多様なサービスが受けられますよと言っているのです。何かそのとおりの答弁が返ってきたなと思っているのですけれども、それまでどおりの介護保険の専門家によるサービスを受けながら、それプラス、それプラスですよ、多様なサービスが受けられればもっといいのかなと思うのですが、そうではなくて介護から外すのですよね。そこが問題だと言っているのですが、皆さん方はどのようなお考えですか。要支援1・2というのは、介護保険で支援が必要だと認定された方なのです。それを外すということですから、そこが問題だと私は思うのです。どうお考えでしょうか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 寛諄議員のご質問にお答えいたします。議員も既にご承知のようでございますが、介護の支援1・2は、考え方として介護予防給付、要するに介護にならないための予防ですよと、それを制度のなかで給付金として上げていますというものです。それが今回の改正では地域支援事業に回しますという、この地域支援とは保険給付ではなく市町村に交付したものから現在介護の使用した分の3パーセントが来ています。平成26年度予算で約6,000万円弱ですね。ですから、保険給付から事業としてやってくださいということです。今、介護の支援者で1・2の方は、例えば嬉の里とか第一病院にいらっしゃいます。その方々がそのまま今やっているサービスを継続することは可能ですね。これが給付金ではなくて市町村の支援事業から出しますということです。この財源的には介護保険制度内のサービスの提供であるという考え方です。直接給付金で出すか、市町村に下りてから出すかという部分です。今まだ市町村にも見えない部分があって、この3パーセントが要支援1・2の全額が来るのかまだはっきりしていません。これが全額来るようであれば、今までのサービスを同じように提供できると考えています。今回のご質問は、要支援1・2のことなのですが、以前にもあったように特養の3以下1・2については外すとか、そういうこともあります。あるいは、今後の改正で低所得者の保険料の軽減の拡充、あるいは個人負担の1割負担が一定以上の方は2割負担になります。これもすぐに2倍になるのではなくて、上限がありますので2倍以下になるとかいろいろ改正があります。あくまでも2025年、平成31年ですか、団塊の世代が年齢いきまして、3分の1が65歳以上になる推定ですので、その人口推移でいきますと当然、右肩上がりですと、これを地域で支えるかたち、地域包括ケアシステムを構築していろいろなサービスを考えながらやっていくことが趣旨です。いろいろご意見があると思いますが、こういう改正でございます。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 いろいろ改正するのは分かります。部長が嬉の里とかおっしゃっていましたが、その要支援1・2の方が今そこを利用していると、市町村に任されてもそこを利用できるのですか。同じように利用できるということですね。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 あくまでも介護保険の制度内です。現在、要支援1・2あるいは要支援1・2に入っていない方も総合支援事業でそこに行っています。そこで、要支援1・2以外は1回で4,000円、そのうち700円が自己負担です。本来、1割ですと400円なのですが。介護認定の方は週1回で1回5,270円、年間で2万990円ですからその1割を負担しています。この制度が先ほど答弁したとおり、同じ額を市町村の支援事業に回ってくれば1割負担でできます。ただ、この金額がまだはっきりしていないのですね。本当に10割くるのか。これは今年の夏ごろ、7月以降だと思いますが、こういうガイドラインが国から示されるということです。ですから、この事業については、基本的に市町村が単価を決めることになりますので、負担割合もどうするかを決めますので、財源があれば同じようにできます。これは負担の話ですね。サービスについては、今まで受けていたサービスを受けることは可能です。サービスを落とすことはしませんということです。先ほどから言うように、負担額がどうなるかがまだはっきり見えないところが懸念される部分でございます。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 でしょう。でしょうとはどういう意味か分かりますか。各自治体に任されると、自治体の財源の良し悪しによってサービスがだいぶ変わってくるのですよ。今は全国一律のサービスが、要支援1から介護5まで一律サービスが介護保険で受けられるようになっているのです。ところが、要支援1・2を各自治体に任せるということは、個々の財力によって変わってくるということなのです。では、要支援1・2の方が、私はずっとこの施設に居ますとしたら、皆さん方はそれを支えきれるのですか。これができないから今、皆心配しているのです。各自治体ではできないと。中央社会保障推進協議会というところが昨年行った自治体アンケートなのですけれども、要支援者の自治体事業への移行について可能と答えた自治体は僅か17.5パーセントだと、各自治体ではとてもじゃないけれども持ち切れませんという答えになっているのですね。だからこれが今、心配されているのです。介護保険はこれまでどおり払っていて、要支援1・2として介護が必要だと言われている。もちろん、見た目は健康だと、要支援1・2であっても大丈夫じゃないのというような方もいらっしゃいます。ところが、痴呆の関係とかガンの末期とかなると要支援1・2の可能性も実はあるのです。特に痴呆については、日々変わっていくわけですから、そういう人たちも要支援1・2で、そのままにしていると専門家に診てもらわないとだんだん酷くなって介護に回っていく方も多くいらっしゃるということで非常に心配されているところなのです。各自治体に任されると、財政力によって見放される、国からどれぐらい来るか分からない。国からもこれまで7パーセントあった伸び率を3パーセントから4パーセントぐらいに抑えなさいとの指示も来ているわけでしょう。そうなってくると、将来的にどうなるか分からない。これまでの質問でも町長、副町長は悪くなるようなことはありませんとおっしゃっていましたけれども、それはそういう構えでやらなければいけないだろうけれどもしかし、財政の問題では大変だと思うのですね。そこで見捨てられる可能性があるからぜひそのへんはそうならないように声を上げるべきではないかと思うのですけれどもどうですか。皆さん方はまだ分からない状況でしょう。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。私が持っています平成26年2月25日の厚生労働省老健局から担当課長会議ということで県では3月27日で説明されている資料から今お話しておりますが、介護保険制度内でサービスの提供があり、財源構成も変わらないという文言なのですね。要するに、国の負担分、県・町の負担分。1号が21、2号が29というような財源内訳構成は変わらないわけです。この部分については、今後も財源は減らさない考え方ですから、サービスを市町村がどれぐらい提供できるかが一番大きな問題になるわけです。そのなかでもご質問にありました痴呆症の施設の推進ということで、これも包括ケアシステムのなかで構築していくと、これも市町村でやるわけですから、それに対する人的確保も必要ですし、これを受ける組織と言いますかあるいは事業所等を発掘したりする業務は今後増えてきます。これは平成29年度までにはぜひ完成してくれと、包括ケアシステムについては平成30年度までにスタートしてくれという改正内容でございます。サービスを減らさずにいかに介護制度を持っていくかはやはり地域の大きな課題であると思っています。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 国・県からの負担が変わらないというのはおかしいと思いませんか。社会保障制度に金がかかり過ぎるから制度改革だと彼らは言っているわけでしょう。減らすために地方自治体に任せるのに負担は変わりませんと言うのは、どう考えてもおかしいですよ。そこに疑問を持たないというのもおかしい。将来、負担が変わってくるというのは目に見えている。彼らはそれを少なくするために切り離すのですから。負担が同じでしたら、何も切り離す必要はないのです。
それからもう1つ質問したいのですけれども、これまでデイケアとか要支援でも老健施設など専門職の皆さんがやっているのですが、総合事業の皆さん方の所へいくと専門職の職員で対応できるのですか。それともボランティアとかそういう皆さん方の育成でやる予定なのですか。そこをお聞きしたいと思います。
○議長 中村 勝君 神里 智保健福祉課長。
○保健福祉課長 神里 智君 お答えいたします。先ほどからあります訪問介護と通所介護は、今回から地域支援事業になりますけれども、訪問入浴とか訪問看護あるいは訪問リハビリ等はそのまま要支援1・2の方も使えます。地域支援事業でこれまでも3パーセント下りてきましたお金は、上乗せして下りてくるだろうということがありますし、これまで利用していただいた施設は介護保険広域連合が見ていますのでたぶん介護保険広域連合で28市町村は同じような金額でできるような方向で検討すると思います。与那原に住んでいるから、南風原に住んでいるからということではなくて、介護広域連合構成市町村の中は事業所と委託契約を結びますから今までどおりどれぐらいでできるか。それは先ほど議員がおっしゃったように、今まで全国一律だったものを保険者に任せますよということですので、そこらへんを含めて連合とも考えながらやっていきたいことと、もし、おっしゃったように財源を減らすためということであれば、今まで予防事業でやっていた地域でのミニデイ等をより強固に、1カ月に1回やっていたものを1カ月に2回にするとかそういったサービスの利用方法もありますし、訪問介護でできなかった分を家族支援という単費で持っているものもありますのでそういったものを充実させながら、できるだけ今までどおりの介護が受けられるような方向で検討していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
〔「休憩願います」の声あり〕
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午後1時55分)
再開(午後1時55分)
○議長 中村 勝君 再開します。
○保健福祉課長 神里 智君 ヘルパー資格を持った方を優先的にやりたいということで考えておりますし、介護施設ではそれまでの状況で利用ができるように努力したいと思います。派遣は、ヘルパー職と言うのですか免許を持った方を。(「ボランティアとか資格のない人は違うということですね」の声あり)ボランティアでできるところはボランティアも考えたいということです。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 時間がありませんのでこのへんで止めるのですが、先ほども言いました市町村に下りてくるのはもちろん、専門職ヘルパー中心にやるとおっしゃっているのですけれども、もちろんそういったボランティアもやるということですよね。そこも一つ懸念があるところなのですけれども、そこはあとに譲ります。先ほども言ったように、国では社会保障の問題では金がかかり過ぎるということで減らしているわけですから、それで要支援1・2を削ると、それから特養も介護3以下は削るということをしているわけですから、連合がトータルでやるとのことですが訪問介護の問題とか通所介護の問題とかそれは各自治体ですから将来的に問題もいろいろ出てくると思います。そこは注意していきたいと思います。
次、北丘小学校についてお伺いしたいと思います。先ほども言ったように、騒音の問題とかそういうものは支障ないと考えているとのことですが、実際に現場ではどうなのか。皆さん方が大丈夫でしょうと考えているのか、現場で大丈夫ですとなったのかお聞きしたいと思います。実は以前、南風原小学校の建て替えのとき、プレハブ校舎ではちょっとうるさいという話を聞いたことがあるのですね。今の運動場にプレハブがあったときでしたか、子どもたちがちょっと動いたりすると、やはりプレハブですから音が出るという話を聞いたものですから、今度の校舎はどうなのかと思って質問しているところです。そのへんはどうなのですか。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 北丘小学校の大規模改修に伴う仮設校舎についてでございます。確かに学校のほうに確認をいたしますと、教育長から答弁がございましたように授業については今のところ支障はないというような考え方で、しかし、学校全体の学校生活のなかとしてはやはり支障があるということです。仮設校舎は軽量鉄骨でございますので、それに壁もRCではなく板を張ってございますので、うるさいとまではいきませんがコンクリート構造よりも音が伝わるというようなことはあるようです。それから、子どもたちはどうしても走りますので、廊下ではちょっと振動があるという状況は学校のほうから伺っております。それについては、授業が始まったら静かにするよう子どもたちに指示をしてそれについては解消していく捉え方をしているようでございます。以上です。
○議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。
○10番 宮城寛諄君 確かにプレハブなので少々の音はするだろうと思うのですけれども、あまりにもうるさいと授業に差支えがあるのではないか。今は管理棟と特別教室で、これから教室に移っていくわけでしょう。それも同じプレハブを使うわけですから、今で対処できるのであったら対処して欲しいと思います。普通教室になったときにとてもではないがうるさいとなると困るので、南風原小学校であったことがないようにしてください。希望して終わります。以上です。
関連記事
お問い合わせ
議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp