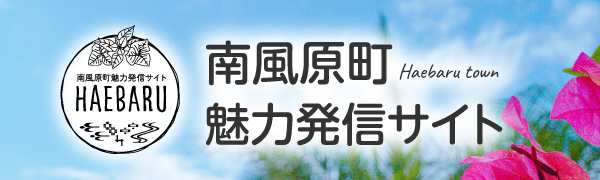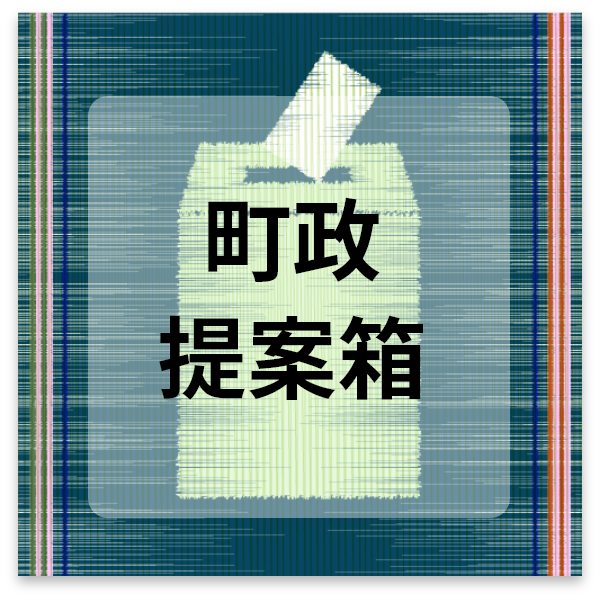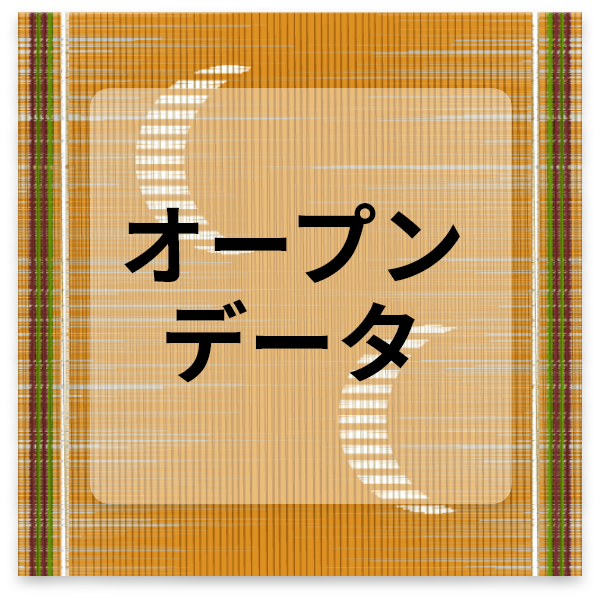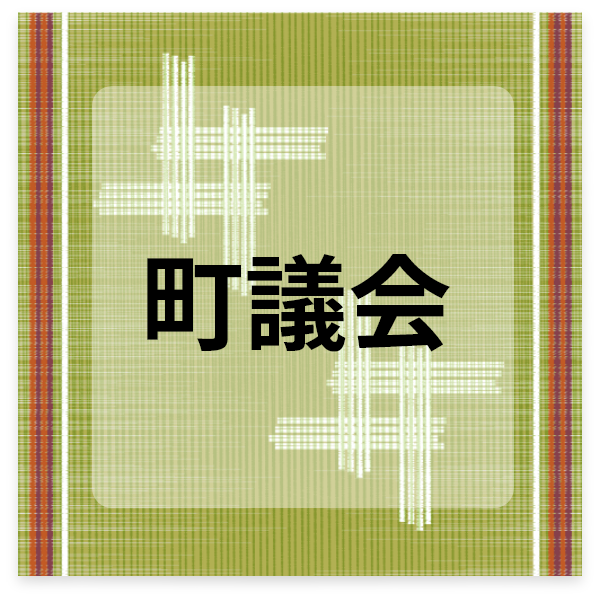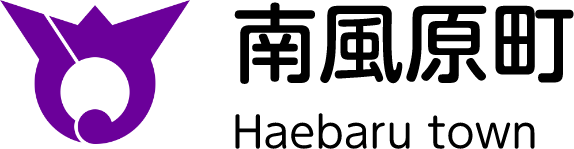本文
平成25年第2回定例会 会議録(第3号-1)
平成25年 (2013年) 第2回 南風原町議会 定例会 第3号 6月18日
検索
| 日程 | 件名 | 一般質問の内容 |
|---|---|---|
| 日程第1 | 会議録署名議員の指名 | - |
|
日程第2 |
|
|
| 照屋仁士 議員 |
|
|
| 宮城寛諄 議員 |
|
|
| 浦崎みゆき 議員 |
|
会議録
○副議長 玉城光雄君 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。
開議(午前10時00分)
日程第1.会議録署名議員の指名
○副議長 玉城光雄君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって14番 上原喜代子議員、15番 大城真孝議員を指名します。
○副議長 玉城光雄君 日程第2.一般質問を行います。それでは、通告書のとおり順次発言を許します。6番 赤嶺奈津江議員。
〔赤嶺奈津江議員 登壇〕
○6番 赤嶺奈津江君 おはようございます。一般質問2日目、今朝は火曜日なので北丘小学校の読み聞かせからこちらに来ましたけれども、子どもたちから元気をいっぱいもらってきましたので、私も元気いっぱい質問をさせていただきたいと思います。それでは、私は一問一答で質問をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。1.南風原小学校運動場ネットの修繕についてです。(1)南風原小学校グラウンドは、平日の放課後や休日に少年野球やサッカーにより利用されています。しかし、町道側(宮平学校線側)はネットが破れている箇所があり、穴から逃げたボールを追いかけるため、児童生徒の道路への飛び出しが見受けられます。事故が起こる前に直すべきではないかと思うのですがいかがでしょうか、お伺いいたします。
○副議長 玉城光雄君 教育長。
○教育長 赤嶺正之君 おはようございます。教育委員会に関するご質問にお答えいたします。1番の南風原小学校運動場ネットの修繕についてでございますが、南風原小学校グラウンドの町道側ネットについては、現場で調査した結果、議員ご指摘のとおりだいぶ破けておりまして修繕も厳しい状況でございます。さっそく、ネット全体を考える方向で検討してまいりたいと思っております。以上です。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。実際、私も役場へ用事で来たり、文化センターに行ったり来たりするとき、休みの日ですとかなり子どもたちがボールを追いかけて町道側に出たりするのですね。なかには練習試合で来た子たちがいるものですから、同じ南風原の子であれば出ないようにと指導はできると思うのですけれども、練習試合で来られた子どもたちは取っておいでと言われると道を確認しないまま走って取りに行ったりするものですからかなり危険だと思います。ですから、南風原町は結構スポーツでも頑張っていて、新川ダイヤモンズも派遣を取りましたし、そのように野球も頑張っていてグラウンドはかなり利用頻度が高く、社会人も使っていますし、ぜひ早めの対応をお願いして、子どもたちが安全・安心に使えるようお願いしたいと思います。先ほど早めに対応して全体を直すとのことでしたので、1番の質問は以上にしたいと思います。
では2番目にいきます。浸水対策についてであります。昨今、ゲリラ豪雨のように急に大雨が降って冠水する場所が増えてきていますのでその点についてお伺いします。(1)近年、ゲリラ豪雨等により町内でも多くの道路冠水や家屋への浸水等が見られる。当町は十数年でかなりの都市化が進んでいるため新たな対策が必要だと思うが町としてどう考えているかお伺いします。
○副議長 玉城光雄君 町長。
○町長 城間俊安君 お答えします。奈津江議員がおっしゃるように、南風原町においては都市化、また住宅、いろんな開発が進んで、今までの排水と異なり、また、流達時間が短くなっている部分等を考え浸水する箇所が多々あるのだということで、昨日も申し上げましたがこれは一地域ではなく町全体的なものであります。町全体的に排水工事をしたら10年も20年も放置された状況があったと、これでは小さな雨でも水浸しになる、それはどういったことかと言いますと、傾斜ではない平坦な所では土砂が溜まって機能を果たしていない、上まで砂地が入っているような状況で、これはやはり一地域ではなく全体的に調査をして、年次的に直していくことが大事だと、すぐやる班が調査をして、雨天のときも見ていますし、平日もどういった場所がある、時間がかかる場所、即できる場所などそういうことを調査するようになっています。一つの事例として、役場前の旧郵便局から中に入っていく場所もフラットになっていて調査したときは60センチほどの深さですが蓋まで溜まっていたと、ということは雨が降ると道路が排水の機能を果たすことになるという状況でした。これではいけないと、年次的に全部調査をして一番悪い箇所からやっていこうと指示をしています。箇所など詳しいことは担当からお答えさせます。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 それでは、お答えいたします。近年、集中豪雨により道路及び排水路等において浸水する事件が多くなっております。要因としまして、宅地開発等により都市化が進み、雨水が排水施設などに到達する時間が従来よりも早くなっているということで、既存の排水溝等の利用量を超えたことが原因と考えられております。対策といたしましては、道路内の排水溝の再整備では抜本的な解決は難しいと考えられるため、新たな排水施設等の整備を行う必要があると思われることから、現在、浸水対策下水道事業により計画及び整備を進めております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。やはり南風原町は、昨日もらった統計はえばるから見ますと、昭和57年から平成24年までの間に1万5,000人ですか増えて、宅地の造成もかなり進んで、新川もかなり人口が増えてきています。アパート等がかなりできてきていて、表面水を吸収する場所がないのですね。畑だったり空き地だった所がどんどん宅地造成されていくなかで、人口が増えることは嬉しいことではあるのですが、昭和57年以前に考えられていた排水とは全然違う状況にあるものですから、かなり前に整備した下水とかそういったものは容量をオーバーしてしまってなかなかきれいに流れず、冠水したり住宅地に浸水冠水して家の中まで入ってくることもあります。あんなに高い新川でさえなかなか水が流れなくて、213番地付近ですか奥のほうなのですが上から流れてきた水が一気に集中して下りてくるので、家の倉庫に入ってきて20センチぐらい浸水して被害を受けた所もあります。ですので、高台でも有り得るのだと理解していただいて、南風原町全体を見ていただきたいと思います。先ほどチェックしているとのことでありましたけれども、現在何カ所ぐらいが浸水、冠水しているか把握しているのかお伺いしたいと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。町内の浸水及び冠水箇所につきましては、まちづくり振興課すぐやる班で作成しております浸水・冠水箇所図と、下水道事業で作成されている南風原町浸水実績図や南風原町ハザードマップ等で確認はされております。概略的に箇所を申し上げますと、浸水・冠水が酷い地域で約15カ所ございます。あとは状況にもよりまして、例えば雨が多いときには末端の排水の要因ではなくてグレーチングとか排水に直接落ちる所が木の葉やビニールとかそういったものが被さってなかなかはけないと、掃除をすればすぐ水が引いた箇所もございます。基本的なものは末端の排水等の要因に伴って浸水する箇所が今把握している所で15カ所、あとは細かい所も少しずつありますけれども大きく把握しているのがこの15カ所ということで図面も作成されて、箇所については把握しております。例えばある一定の雨量が出た場合は、すぐさま現場の確認ができるよう体制を整えております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。先ほど今後の対策等もお話いただいて、箇所もある程度把握されているとのことなので、この把握されている大きい所で15カ所、細かい所もあるとのことですが、それぞれに今後の対策はある程度考えられているのでしょうか。お伺いします。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 今現在、排水の要因によって浸水・冠水する箇所につきまして、例を申し上げますと北丘小学校前の町道3号線、こちらは末端の排水が容量的に対応できなくなっていることがありまして、下水道の雨水で設計中でございます。設計が完了しますとすぐ工事を発注いたしまして、それの対策を講じてまいりたいということです。基本的には町道3号線から国場川に向かって直接排水を持って行く計画で現在進めております。もう1点につきまして今現在設計が進められておりますのが照屋の十字路から山川向けのほうです。そこに農林サイドの排水がございますけれども、こちらも断面的に近隣の開発に伴って容量が足りなくなっているということで、新たな雨水管によるバイパスの整備に向けて現在設計中でございます。そのように、末端の排水が要因のものにつきましては、浸水対策の下水道事業で検討を進めておりまして、今後も同様な整備をしていきたいと考えております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。このあいだ、北丘小学校前でも、すぐやる班の方だと思いますけれども排水を掃除されているのを見ました。今回、この容量が小さいとのことで大きくする計画もあるとのことですので、早めに対策を取っていただいて、またお家に浸水される方々の所は確認いただいて、住民の方の住み良い状況に持っていっていただけたらと思います。よろしくお願いします。2番は以上で終わりたいと思います。
次に、3番です。子どもたちの通学路の安全確保についてであります。京都の亀岡のほうでかなり大きな交通事故等がありまして、児童生徒の登下校中の安全確保ということで通学路のチェックについて国からもありましたけれども、その点で町にお伺いしたいと思います。(1)昨今、登下校中の児童生徒の事故が多発している。町内の通学路のチェックや安全対策はどうなっているかお伺いします。
○副議長 玉城光雄君 教育長。
○教育長 赤嶺正之君 それでは、3.子どもたちの通学路の安全確保についてのご質問にお答えいたします。(1)でございますが、通学路の危険箇所点検については、昨年、通学路緊急合同点検調査がありまして、夏休みに警察や道路管理者、学校を含めて安全点検をいたしました。安全対策については、道路管理者が早急に対応できる車両区分線引きの対策を終えております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 去年、チェックをされたとのことですけれども、ここが危ないというリストではなく地図上でも作成されていますでしょうか。
○副議長 玉城光雄君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 お答えいたします。先ほど教育長からもございましたように、昨年の8月の夏休み期間中に通学路の点検を、教育委員会、小学校、PTA、南部土木事務所、町の都市整備課、与那原警察署で行っております。危険箇所については地図も作成をいたしまして、その箇所はどういった危険のある箇所であると、例えば歩道と車両の区別がない等の地図も作成し、危険箇所として表示されております。地図は作成しております。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。地図は作成されているとのことですけれども、そのチェックは交通安全的なものだけですか。不審者とかそういった危険な箇所などもあるのでしょうか。人から見られない場所を通っていくとか、そういった所もあるのかどうかお願いします。
○副議長 玉城光雄君 教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 昨年調査を行いましたのは、通学路の緊急点検ということで道路の構造上とかそういった危険箇所についてですので、不審者といった記載はありません。道路についての記載がされております。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。実際、通学路の危険というのは、自動車関係だけではなくて不審者だったり人から見えない場所もかなりあるものですから、そういった所も確認されているのかと質問しました。北丘小学校の近くで話題に上るのが「あかばし」という所で、夕方等、学校の先生からも通らないようにと指導があるということで、町内の子どもたちだけではなくて町外からの子どもたちがたまっていたりとかそういったこともあるそうです。なかにはお酒を持ち込んで飲んでいる大人がたまにいる場所もあると聞いているものですから、そういった通学路として相応しい所、相応しくない所をチェックしていただけたらいいかと思います。学校側や保護者で注意をしていても、教育委員会側ではそれを把握していなかったということがないように、ぜひそういった危険箇所、登下校に使う道の安全を確認していただきたいということでこのチェックはどうなっているかの質問をさせていただきました。
次に(2)ですが、通学路で歩道やガードレールがない所については、ハンプ(道路を凸状に舗装すること)や路面表示を工夫するなど自動車が減速するような対策を取って欲しいと思うのです。実際、寿スイミングスクールの前ですか、速度を落とせと表示してあるということで保護者からもやはり目がいくとあったものですから、そういった歩道がない場所、交通量の多い所はやっていただけないかと今回の質問をさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。
○副議長 玉城光雄君 教育長。
○教育長 赤嶺正之君 子どもたちの通学路の安全確保(2)についてお答えいたします。歩道やガードレールがない通学路については、路面表示の工夫などその対策を道路管理の担当部局にお願いをしておりますが、ハンプについては道路安全面で設置が厳しいのではないかと思っております。それ以外につきましては、経済建設部と連携を取りながらその都度対応してまいりたいと思います。現在では、先ほど答弁いたしました通学路区分の線引きをやっておりまして、今後もその追加分もあると聞いておりますのでそのように対応してまいりたいと考えております。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。ハンプは難しいということで、前回、他の議員の方からもありましたし私も聞いたのですけれども、ハンプでも高さの度合いが結構あって、かなり高いものから低いものまでいろんなものがあると聞いていますし、また情報としては救急車両が通るときにはハンプがないほうがいいとも聞いておりますので、できればハンプのようなかたちを路面に描くことも可能なのですよね。那覇市だったと思いますけれども、視覚に訴えるということで黄色と黒でしたかハンプの画を立体的に描いてそれで注意を促す箇所もありました。他の所では、道を狭く見せるような、視覚を利用して減速を促すような対策をしていると聞いています。新川も歩道がなくて、また今はいろんなところから駐車場を借用されている方もいて、かなり交通量が激しくて、それが怖くて北丘小学校校門前まで親が送るというところもあるものですから、安全に通えるようなかたちにしていただけたらと思います。それから、大名の町道10号線ですが、東新川の子どもたちはそこから来るものですから、ある程度の歩道区分、小さなラインを引くだけでも運転者の意識が変わると思うのです。そういったかたちでぜひ対策を早めにやっていただきたいと思うのですけれども、路面表示も必ず線を縦に引くだけではなくて表示で減速を促すような検討されているかどうかお伺いしたいと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。集落内の歩道がない道路の通学路安全確保につきましては、前々からの私どもの課題にもなっています。以前からハンプの設置や議員が今おっしゃられた画を描くハンプ、これは一般的にイメージハンプと言いまして画を描いて視覚で立体的に見せてそれで注意を促して減速させる手法になります。あとは路面にその文字を書いて注意を促す方法、標識を作りまして一般的に接触事故多発地域というような注意を促す方法と種種ありまして、それを検討しているところでございます。町道10号線につきましては、登下校する子どもたちに車が接触する事故も結構ありましたので、今は立て看板で注意を促しているような状況であります。同様な箇所についても何カ所かそのような設置がされておりまして、今後有効な対策を教育委員会と調整しながら進めていきたいと考えております。ただ、通学路の緊急合同点検調査のなかでも双方、警察も含めて協議したのですけれども、道路の現況幅員によりましてはやはり子どもたちの通るスペースの側線(ライン)が引けない所も結構ありまして、その線を引くことによって例えば一方通行の制限を受ける道路もございますので、側線は全く引けない箇所も出てきます。引ける箇所につきましては、昨年から対応は随時やっておりますので、その状況に応じた対応を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 6番 赤嶺奈津江議員。
○6番 赤嶺奈津江君 ありがとうございます。去年チェックしてその対策は取られているとのことですので、早めに子どもたちが安心して通えるような道にしていただきたいと思います。親としては過保護になってしまう箇所があるのですよね。ここを通るのだったら送ろうかなというような箇所があって、学校前を渋滞させる原因にもなりますし、朝のラッシュ時にそういった状況を作るのも良くないと思いますので、子どもたちが自分たちの足で通えるような環境を整えていただきたいと思います。また整備を予定されている道もあると思いますので、早め早めの対応をお願いして終わりたいと思います。ありがとうございました。
○副議長 玉城光雄君 休憩します。
休憩(午前10時28分)
休憩(午前10時28分)
○副議長 玉城光雄君 再開します。発言を許します。2番 照屋仁士議員。
〔照屋仁士議員 登壇〕
○2番 照屋仁士君 おはようございます。本日、2番目の一般質問を進めていきたいと思います。私も一問一答でお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、質問します。
私は、先日、福島県を訪問してまいりました。今回の訪問は、津波の直接的な被害だけではなく、原発の帰宅困難地域やさまざまな風評被害に遭われている福島の皆さんの生活や県民感情に触れ、私たちのできる支援のあり方を考えるための訪問でした。現地で案内していただいた方は、福島県連合青年会会長の渡辺直也さんという方で、この方は会津若松市在住で専業農家として米、ピーマンの生産を営み、またJA青年部の役員としてもご活躍されている方です。2日間、渡辺さんと福島県内を回りながら被災の状況だけでなく農業に取り組む若者としての考え方を学ぶ機会となりました。昨今、TPPの交渉参加や食料自給率の問題など農業を市場原理だけで考えると大変なことになると議論が巻き起こっております。私の周りにも農業に携わる同世代のメンバーが何名もおります。また、先日、地元神里の生産部会総会においても、農業従事者に対する支援や台風等天災時の被害、また将来に向けた展望についても質疑されました。私はこれまで、農業に携わる機会がありませんでしたので無知なところも多々ありますけれども、一町議会議員として農業に携わっておられる方々に対し、また一般町民の皆様に対しても本町の農業施策や展望をしっかり説明できないといけない、また町政に対してもできるところは積極的に学習し、そして提言してまいりたいと考え質問いたします。1.農家がいきいきと暮らせる事業を(1)本町は、かぼちゃの産地として広く町内外に認知され、また、花卉、熱帯果樹など農業に携わる方々にもさまざまな施策を展開しています。私も議会等で触れその施策はところどころ審議しておりますけれども、いざ自分の口で説明するとなるとまだはっきりとしないところもありますので今回の一般質問をとおしていくつの事業展開をし総事業費はいくらかなどいろんなことを町民の皆さんに説明できるようにまとめたいと思っておりますのでよろしくお願いします。いくつの事業を展開し、総事業費はいくらなのか教えていただけたらと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。平成25年度の本町の農政関係施策については、26事業を展開しておりまして、2億2,938万1,000円の事業費となっております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。今のお答えで26事業、2億2,900万円の事業費で展開しているとご説明がありました。町が出している『ハイさいよ~さん』等そういった分かりやすい予算説明書もありますので、私もそれを通じて調べてみましたけれども、私が思っていたより多くの事業、またより多くの予算が使われていると思います。農業政策と一言で言ってもその担当部局もいろいろあろうかと思いますので、どの課で何事業、またこういう課でこういう事業を展開しているというような説明がいただけたらと思いますので、ご答弁をよろしくお願いします。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。農政関係施策事業につきましては、主にハード部門の畑灌整備、農道整備は都市整備課で事業を進めております。残りにつきまして野菜振興対策事業、花卉振興対策事業、さとうきび振興対策事業、あとはかなり細かい事業がいくつかありますけれども、そういった農政関係につきましては本年度より新設しております産業振興課で事業を行っております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ご説明ありがとうございます。大規模な基盤整備事業が都市整備課で、それぞれの各種野菜、花卉、さとうきび、またそれら以外の農政関係の事業を新設された産業振興課でやっているとのご答弁でよろしかったかと思います。各課に係るところはそれぞれ聞いていきたいと思いますが、それ以外で予算上で何事業、いくらかという聞き方をしたのですけれども、他の課と連携しているとか予算措置の係わらない事業もいくつかあるのかと思っていますが、どういったものがあるのかお答えいただきたいと思います。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 お答えします。予算措置の係わらない連携事業とのことです。いくつかあるのですが、例えば野菜に関してはかぼちゃ産地協議会がありましてJAさんや南部農業改良普及センターとで毎月定例会を開催して三者間で情報交換、課題についての検討等、それからJAさん主催の栽培講習会、そういったものを行っております。あとはJAさんの各生産部会において総会に参加して連携を組んで野菜振興等、課題に取り組んでいます。あとは本町の特徴と言いますか、本町では農業青年クラブさんが活躍していまして、農業青年クラブさんと生産農家さんの協力で緑肥ひまわりの種撒き体験をして、開花したら小学生を対象にそういうセレモニーをしたり、子どもたちが農業に接することができるような取り組み、こういったものは全部ボランティアでございますので予算の係わらないかたちの事業。それから、生活研究会の方々によります各小中学校での総合学習における家庭科の事業とかそういったところで町のヘチマなど野菜を使っての授業に一緒に参加してボランティアでの活動をしています。そしてまた島野菜を販売促進しようという方向で、最近では町のヘチマは「美瓜(ビュウリー)」と名前を付けまして、テレビに出たりラジオに出たり、いろいろな情報誌等に生活研究会や生産農家の皆さんと町役場、そして農協さんが関わって取り組んでいる状況であります。以上であります。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございました。予算事業としては26事業、2億2,900万円あまりの事業を展開しながら、今、課長がおっしゃられたさまざまな連携をされているというようなご答弁だったかと思います。非常に分かりやすく聞かせていただきました。個別のことについてまた以下に進めていきたいと思いますので1番は終わります。
次に、2番目として大規模な農業基盤整備のお話、先ほど都市整備課で進めているというようなものがありました。その基盤整備ですけれども、予算額も事業の期間も大きくなるというところでこれまでどういった実績、取り組まれてきた事業、そしてまた今後の計画が年度ごとであれば、今年度の予算審議にもあったわけですが改めてこれまでのことと今後の事業展開を年度、地域ごとに説明していただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 それでは、南風原町の農業基盤整備等の実績及び今後の計画年度について答弁いたします。本町ではこれまで土地改良事業や農村基盤総合整備事業、農道整備、灌漑排水整備などの各種農業生産基盤整備事業を推進してまいりました。土地改良事業ではこれまでに5地区、101ヘクタールが完了しております。北部地区の宮城土地改良区、23.4ヘクタールが昭和61年に完了し、東部地区の宮平土地改良区15.3ヘクタールや喜屋武地区土地改良区21.8ヘクタールが平成2年度完了。南部地区におきましては、神里土地改良区26.4ヘクタールが昭和55年度、山川土地改良区14.2ヘクタールが昭和63年度に完了いたしております。また、大規模な整備事業としまして、現在、再整備の一環として畑地灌漑排水等整備事業を実施しております宮城地区が平成21年度から平成25年度まで、山川地区が平成25年度から平成29年度までの事業として進めております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。今の説明で各年度において各地域の農業の基盤整備がされてきたことを改めて振り返ることができました。今、いくつか地名も出てまいりましたけれども、この基盤整備を入れたり、またこれは土地利用計画とも重なると思いますが、今出てきた所も含めて町が農業振興地域と考えている地区はどこか改めて教えていただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 それでは、お答えいたします。一般的に言われておりますのが農振地域ということでありますけれども、農政及び農林事業関係はその農振地域にほぼ限定されておりまして、その地区が私どもの農業振興の地域だと、イコールと考えております。また、ほぼその位置も土地改良から外れている所もありますが一般的には土地改良区を中心とした優良農地が農業振興地域だとわれわれは認識しております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。土地改良区を外れた所もあるけれども、主にその土地改良を行った地域を考えているとのことだったと思います。先ほどのご答弁で土地改良を行った地域、宮城、山川、宮平、喜屋武、神里、こういった地域が考えられるとのことかと思いますがそれでよろしいですか。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。土地改良区につきましては、宮城、宮平、喜屋武、山川、神里の5地区となっております。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 先ほど大規模な基盤整備がこの土地改良区ということで、農業振興については産業振興課を中心に野菜、花卉、さとうきび等のさまざまな事業を展開しているとのご答弁があったと思いますけれども、この事業に関しては特に土地改良地域、そういった所に限ったものではないと考えますがそのような理解でよろしいですか。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 農林及び農政関係の事業につきましては、特に土地改良区内という限定ではなくて農振農用地内が一つの取決めと言いましょうかその範囲内での事業が一般的に可能だとなっております。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。それでは、最近、その土地利用のところでよく議会でも出ますけれども、土地利用の制限によってアパートが建てられないとか人口が増えないとかそういった懸念で見直しできないかというようなこともあるわけですけれども、一方で農振地域であるために大型の事業が導入できるとかこういった補助が受けられるとか、農振地域であることによって受けられるメリットもあるのかどうか、そういった点を教えていただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 先ほどの答弁でも少し触れましたけれども、一般的に私どもが行っております事業、例えば畑灌でもそうですし、農道関係につきましても事業できる区域の一番上の条件がまず農振農用地となります。例えば調整区域で農林関係、農政関係の事業が可能かと言いますと、私の記憶している限りではまず第一の条件が農振農用地でございますので、そういう方面では農振農用地とまたそれから外れている地域とではそういった事業の導入の差が出てくるのではないかと考えます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。農振農用地だからこそ受けられるメリットも非常に多くあるということが、僕もはっきり説明できないところもあったので確認いたしました。それでは2番を終わりまして、これから少し具体的な、全庁的になると思いますけれども、そういったところの取り組みについてお伺いしたいと思います。
この農業振興については、JAさんが非常に大きな役割を果たしていることは、これまでの議会のなかでの説明でも分かっているところですけれども、改めましてそのJAをはじめとした関係機関との連携、先ほども少し産業振興課長の答弁でもありましたが、JAとの連携若しくはその関係機関との連携した取り組みというものをまずJAとの連携について教えていただけたらと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。JA、県南部農業改良普及センター、南風原町によるかぼちゃ、花卉、マンゴー、スターフルーツの三者協議会を設置し、現場での課題や問題点の情報交換、栽培講習会等を開催し技術面での情報共有を図っております。また、その他にさとうきびをはじめ各種の協議会が設置されており、県を含め南部地区市町村、JAが連携し農業振興に取り組んでおります。JAには作物ごとの生産部会があり、担当職員が適宜参加、総会時には生産量上位者の表彰で農家の士気を高めております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。かぼちゃ、花卉などの三者協議会。また、それぞれ各協議会が設置されている。それから、JAで作物ごとの生産部会が置かれているとのことですけれども、各協議会、作物ごとの生産部会もいくつぐらいあるのか、もし数字で分かるのであれば教えていただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 お答えします。まず両農協に野菜、花卉、そしてさとうきび、それからかぼちゃの生産部会があります。それから、協議会については南部地区の市町村の担当部署で集まる協議会と普及所が主になって行う協議会、そういった協議会があります。協議会、部会については以上です。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 JAと連携している取り組みをということで質問いたしまして、答弁のなかで普及所ですとか各協議会、外郭団体等もあるのかと思いますけれども、その他でも独自の取り組みとして、南風原だと「はえばる豚」の取り組みはNPO法人だったかと思いますけれども、そういったJA、関係機関、外郭団体以外でも何か特徴的な取り組みはございますか。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 お答えします。JAなど外郭団体等以外との連携した取り組みとのことですが、特徴的なものとしては先ほど答弁しました町の場合は町の農業青年クラブですね。すごく活発な活動をしているということで、そのクラブのボランティアによる活動が大きいと思います。それから、NPO法人の「はえばる豚」に関しましては、環境施策の取り組みの一つで、それが畜産につながっている部分もあるのですが、そういったところで農政との連携も少しずつできてきてはおります。それから、その他の事業については、JAさん、それから南部普及センターと全て連携しての取り組みとなっています。以上です。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。これだけ多くの連携事業や取り組みのなかでJAさんに協力していただいて事業を展開していることが分かりましたので3番を終わります。
次に、4番目の質問ですが、先ほどの説明のなかでもJAさんや関係機関と連携をしたさまざまな事業を展開していることが分かりました。一方、JAに全部頼っているのではないかという懸念が議会のなかでも、また町民の一部からも声があり私も言われたことがあるのですけれども、本町が直接農家であったり個人、農業関係の団体等を支援している事業もあると思うのでご説明いただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 答弁いたします。町の農業振興に関する事業としては18事業で、今年度予算額が1,393万8,000円となっております。主に補助金という支援となりますけれども、代表的なものは農業制度資金、経営基盤強化資金補助金、これは県・町です。ビニールハウス設置補助金が町単独になります。あとは畑地灌漑井戸設置補助金、これも町単独です。熱帯果樹振興対策事業補助金、これも町単独です。病害虫防除補助金、町の農業用廃プラスチック対策の負担金等も含めまして18事業、金額で1,393万8,000円となっております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。18事業、1,393万円の事業が展開されていると。細かい点がいろいろ議会施策でもありますので、町民の皆さんには『ハイさいよ~さん』を見ていただきながら、私も勉強しながらですけれども、これだけの事業をやっているとのことです。事業の金額など大小ありますが、相談などそういったことは関連団体ではなくても個人でもできると思いますが、主な相談窓口であったり、その案内は産業振興課でよろしいのですか。確認で答弁をお願いします。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 ただいまご説明しました18事業につきましては、全てが産業振興課を窓口として対応する事業となっております。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。産業振興課でさまざまな補助金や補助事業、町民の皆さんが利用できる制度についてはそちらで伺えるとの答弁でいいかと思います。その農業を営まれている個人や団体の皆さんを支援するにあたって、農業委員の皆さんも非常に大きな役割を占めているのかと考えるわけですけれども、農業委員会の事業は『ハイさいよ~さん』等で見るとその会議ですとか指導、情報提供が書いてありました。そういったものを改めてこの議会の場で、どういった役割を果たしているのか、どういったところを町民の皆さんに活用していただいているのか農業委員会の活用、役割についてご答弁いただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 農業委員会の役割とのことでございますが、農業委員会は農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。農業者と団体等の代表によって構成されている公正・公平な委員会ということです。主な業務としましては、農地法の第3条、第4条、そして第5条届出の審議、これが毎月1回、総会であります。それから、農地パトロールも毎月1回実施しています。そしてまた、通年で農業者の方へ農業者年金の加入推進等、それから農地の斡旋、そういったかたちで農業委員の皆様方は活動しています。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。法律で定められている役割と、また先ほどの答弁でもありました農地パトロールですとか農地の斡旋に関する事業に取り組まれているとのお話でした。行政の窓口に相談しづらい方々、そしてまた農業委員の皆さんは実際に農業に取り組まれている方々ですので地域に近く、声も反映されやすいと思いますので、今後とも活用するだけではなくて農業委員会の皆さんもしっかりとした活動できるよう支援していただければと思います。
次に、一昨年ですか出てまいりました本町に農業をサポートするための人材サポートセンターが設置されたと伺っております。利用状況についてもたびたび聞かれていますが、現況について、またもっと活用して欲しいとかそういったことも含めてご答弁いただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 お答えします。平成23年度に設置されました人材サポートセンターでは、平成23年度は求人が5件(11名)ありまして、求職者は18人おりました。マッチングで就職できたのが7名ということになっています。内容としてはキュウリ等の箱詰め、果実の吊下げ作業、そういった仕事に従事するということであります。平成24年の求人が3件(8人)で、求職者が11人。残念ながら双方の条件が合わず就職にはつながらなかったということです。平成25年度今現在は、求職者1人の登録がありますが、今のところ求人が0件ということで待機している状況となっています。以上であります。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 平成23年度からの利用実績についてご説明いただきました。残念ながらこの3年間で少し減少傾向で、今年はまだ始まったばかりで今後どうなるか分からないのですけれども、せっかく設置した制度ですのでやはりもっと利用しやすく、求人にしても条件を緩和するとか、もっと広く求人できるようにするとか、また求職している方についてももっと良い条件で求職していただける、例えば農家から求人に対して支払いがされるわけですが、今はそれのプラスアルファ等もやっていると思いますがそういったさまざまな条件を広げたり緩和したりしていくことでもっと利用実績を上げていけるかと思いますが、この人材サポートセンターについて今後の展望ですとか考えていることがあればご答弁いただきたいと思います。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 議員からもありましたように、確かに平成23年度から今年度まで減少傾向であります。これは町として広報も行き渡っていないのかという部分もあります。今年度からは産業振興課として新たにスタートしていますので、雇用の部分もさらに力を入れて、また特にこの人材サポートセンターに関しましては設置されている他市町村の進んだ情報を参考にして、町内の失業されている方々を1人でも多く就職に結び付けるような取り組みをしていきたいと思っています。以上であります。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。せっかく作った制度ですので、より利用しやすいよう広げていっていただければと思います。今まで言ってきたさまざまなところが、町が直接その農家や個人、団体等に事業を行っているということですけれども、現在、本町産業振興課に農政担当の職員がいらっしゃると思いますが、よくNHKの特集などテレビでも特産品開発であったり販路拡大であったり、農業の技術、専門的な、農業に専属して動けるような専門職員が町の未来となるような産品を生んだりといったことが見受けられるのですが、本町でも農業専門で農政担当を置かれているのか。状況はどうなのかご説明いただけたらと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 それでは、お答えいたします。現在、産業振興課の農政班の職員につきましては、一般の行政職でありまして、営農関係の専門職の配置は現在ございません。農業の専門職と言いましてもかなり幅が広くなることから、例えば専門職を据えて全てを網羅することは大変難しいのではないかということがありまして、一般的な自治体におきましては農業関係における専門的な指導・助言が行える普及所をはじめ両農協、JAおきなわ南部地区営農センターに営農指導員が配置され各要件に応じた専門職の方々の指導が行えることから、今の段階では町での専門職の配置は余地がない状況となっております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。確かに幅は広いと思います。これまでの事業でもそういったことでありますし、外部との連携を活用していくことも一つの手だと思いますけれども、幅が広いだけに相談などそういった展開も多岐にわたるのかと思います。営農の専門職員ではないけれども、農業についてのさまざまな専門分野に割り振ったり協力をお願いしたり、そしてまた誘導したり、そういったところでは一般町民の皆さん、農家の皆さんに不都合、ご不便をかけることはないといった考えでよろしいかどうか改めてご登弁をお願いします。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 農家の皆様方に多種多様にわたる助言関係、指導関係につきましては、普及センターの職員もかなり専門的な職員がおりまして、そういった方面から随時指導が行えると、また両農協にも営農関係に詳しい職員がおりましてその都度相談、指導をやっておりまして、今現在について私どもとしては対応できているのではないかと考えております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。部長の答弁にもあったとおり、いろいろな連携をつなげていくことは大事だと思います。ただ、現在、農家と一口に言っても営農されている方、兼業されている方、多種多様な形態があると思いますので、どういった農業に携わられている方でも役場に来てその窓口でいろいろな相談が受けられて、そして受けられるべき補助ですとか指導・助言が受られるように今後も取り組んでいただきたい。不便を与えないとは先ほどそういった趣旨で言いましたけれども、そういう考えでよろしいでしょうか。お手数をおかけしますけれども、再度ご答弁をお願いします。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。現在、その営農なされている方々の指導・助言につきましては、両農協、普及センターともこれまでの経過から既にそのようなシステムづくりがされていまして、農業を営んでいる方々にもおそらく浸透している状況になっております。あとは新規就農者等につきましても、事業をとおして町との関わりがある場合にそういった方面についてもまた適宜こちらからも支障のないような指導を行っていきたいと考えております。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。町として町民に安心していただけるように、窓口に来れば安心していろんな相談を受けられる、何とか保障できていますよとしっかり言い切っていくことが大事なことだと思ってこのような質問をいたしました。4番を終わります。
次に5番目ですけれども、本町だけではなく沖縄県は台風県であります。去った大雨等もありましたが、台風などの災害、そして天候不良等による減収というのが農家にとっては一番のリスクかと思います。その天候不良、天災等による対応できるまたは利用できる制度や対策等があるかお伺いしたいと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。生産農家が不慮の災害によって受ける損失を補填して農業経営の安定を図り農業生産力の維持発展に資することを目的として、農業共済事業があります。農業災害補償法に基づき、共済掛け金の50パーセントを国が負担し、町も負担金を支出しております。また、野菜生産農家が農協を通じて定められた対象市場に共同出荷した野菜の販売価格が一定の保障基準価格を下回るような著しい低下があった場合、その価格差について補給金を交付する野菜価格安定対策事業があります。この事業は、国と県の事業があり、国の事業としまして対象品目がゴーヤーの特定野菜と供給産地育成価格差補給事業、県の事業では対象品目がキュウリ(県内)、ヘチマ(県内)、かぼちゃ(県外)の重要野菜価格安定対策事業等があります。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。共済事業ですとか価格補償の制度があるというようなご答弁だったかと思いますが、私も実際そういった販売や生産に携わっていないので詳しく分からなかったのですけれども、共済事業で50パーセント掛け金が国の負担であったり、その価格が下がったときの保障があるとのご答弁だったと思います。そういった事業について、これも当然、町や関係機関から案内されると思いますけれども、今までの案内状況やその利用実績、こういったときにこういう補償が活用されたといったものがあれば教えていただけたらと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 先ほど答弁しました内容につきましては、県内ではなく全国的な規模のものとなっておりまして、例えば共済金の支払状況につきましては台風、冷害、そういったものが主な要因での支払いがあります。南風原町におきましては平成24年度の実績としまして、共済に加入している状況が家畜共済で乳用牛が5件、さとうきびが90件、園芸施設共済(ハウス)が41件、建物共済で12件というような加入の状況となっております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。県外もあるけれども、本町でも利用されている状況がある。加入の件数を見て僕も多いのか少ないのかなかなか判断しづらいところなのですけれども、町としては例えばこういった有利な制度を積極的に活用していくべきだ、または案内していくべきだとお考えですか。それとも、まだなかなか掛け金に対しての補償が伴わないとか、掛け金が高過ぎるとか利用し難い制度になっているとかそういった判断が町のなかであるのかどうか現状を教えていただけたらと思います。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 お答えいたします。この補償制度については、国も半分補助するとか県も市町村も負担しての掛け金ではあります。ただし、作物が限定されています。南風原町でしたら、対象野菜が特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の場合ですとニガウリ、そして重要野菜価格安定対策事業の場合はキュウリ、ヘチマ、そしてかぼちゃなら県外向けのみとなっています。あとはこの国の共済につきましても農作物共済、家畜共済、果樹共済というように作物ごとに分かれていまして、先ほど部長の答弁にもありましたが例えば家畜共済で乳用牛の5件というのは5農家が加入されていることになりますので件数からすると町内妥当な件数かとは思います。共済の加入については、JAをとおしての出荷等が対象になってきますので、自ずと農家さんへの加入促進等についてもJAが窓口になりながら取り組んでいくかたちになっています。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。言いたいのは、非常に活用すべきだというものに対しては、たとえJAが窓口であっても積極的に案内すべきだと思いますし、そしてまた少しこのへんが限定されるよという情報が事前に分かれば販売品目も考えたりそういった案内ができるのかという趣旨でご質問申し上げました。農家の皆さんのリスクを町が賄うことはなかなかできないと思いますので、今ある制度をしっかり周知したり活用したり、ときには補完するような、こういった事業ができないかとか県や国の制度を調べたりそういった取り組みをやってあげることが町の役割なのかと思いますので今後ともお願いいたします。5番を終わります。
それでは6番ですけれども、本町では今年度、観光協会も設立されて昨年度以来進んでおります農商工連携やその商品開発等、そしてまた農業の生産から出荷までという6次産業化、さまざまな取り組みがスタートし始めて、今後は町民の皆さん、関係者の皆さんが非常に期待していると思いますけれども、その現在取り組んでいる事業でどういった効果が表れてきているのかその点ご答弁いただければと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 お答えいたします。平成24年度から南風原町商工会へ委託しまして、町独自の商品開発技術力強化事業を実施しております。地域資源の活用や異業種連携による商品開発及び企業と連携による消費者ニーズを踏まえたデザイン性・機能性に優れた南風原らしい商品開発を行い、生産、販路まで展開していく取り組みであり、次年度には2商品が特産品として誕生する予定となっております。この2商品と言いますのが、まずスターフルーツ、もう1つがヘチマとなっております。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 平成24年度に商工会で商品開発に着手して、年度的には平成26年度にスターフルーツとヘチマが特産品として出てくる。分かりはするのですが、内容を説明しづらいと言いますかイメージがしづらいので、もう少し詳しく教えていただけますか。この事業をやったことによって、販路開拓までをこういう取り組みをして市場でこのように出るようになったとかそういったことがあるのかどうかです。町民の皆さんにも分かりやすくしたいと思いますので、もう一言お願いしたいと思います。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 お答えします。この事業については、平成24年度から一括交付金を活用して取り組んでおります。3年間かけての事業でありますが、平成24年度の成果としては、ものづくり産業展開プロジェクト事業報告書ということで一冊にまとめられています。この取り組みのなかで町の特産品のヘチマ、スターフルーツ、この2品を使って何か加工品等ができないものかとずっと取り組んできています。ヘチマのスムージーというものを作ったり、いろいろ試行錯誤取り組んできて、その平成24年度の結果がこの2作物ですね。これで加工品を作っていこうと現在取り組んでいる状況であります。例えば試作品等は物産展などそういうときに出して、そしてアンケート等を取って、そのアンケートもこの報告書にまとめています。そのまとめでこの2作物に決めて今後開発していこうとなっています。以上でございます。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。スターフルーツ、ヘチマを使った加工品、そういったものも含めた商品展開ができるというようなご答弁だったかと思います。非常に魅力的な展開だと思います。それ以外にも観光協会(旧まちづくり推進室)を中心にグルメコンテストですとかかぼちゃを使ったそば、いろんな商品を作っているところを見ると非常に期待が持てると思うわけです。今はその一つの事業を具体的にご説明いただきましたけれども、観光などとも関連したものが今いくつも展開されているのかと思います。それを産業振興課のほうで両方見ておられると思いますから、詳しくでなくていいのでいくつか象徴的なものがあると思いますので今後の明るい展望として少しご紹介いただければと思いますがいかがでしょうか。
○副議長 玉城光雄君 産業振興課長。
○産業振興課長 知念 功君 お答えします。これまでも物産展等で試食された方も多いと思いますが、かぼちゃをペースト状にして練り込んだかぼちゃそばですね。それはNPO法人かすりくらぶさんでかぼちゃをペーストにする取り組みができています。かぼちゃをペーストにして今後は麺作りと、既に「南風原かぼちゃそば」として商品化されていますので、これを今後はどんどん売り込んでいきたいと思っています。
それからもう1点は、ご当地バーガーです。これを今試作中です。1回目の試食回は終わりまして、好評ではありました。全て町内産に拘って作るハンバーガーで、パンはNPO法人てるしのさん、それからパティははえばる豚100パーセント、そして卵やマヨネーズ関係は諸見里エッグさんなど全て町産を使ったご当地バーガーは8月ごろ登場させるということで取り組んでいます。町内の障害者就労継続支援事業B型という福祉関係の事業所ですけれども、この3事業所、NPO法人のぞみの里、てるしのさん、そしてかすりくらぶさん、あとは町内の企業がいくつか一緒になって取り組んでいる事業で、8月には完成して町民の皆さんにお披露目できると思います。以上です。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。8月ごろには成果品もいろいろ表れてくると、非常に楽しみだと思いますけれども、ちょっと厳しいことを言います。今、一括交付金等、地域特性に合わせた事業展開ができる補助金があるわけですけれども、特産品などそういったものは商業ベースに乗らないと実際には続いていかないのですよね。南風原産品を作り出す、町民一体的にやっていくと次の売り込み方、それが継続できるかが大切な視点だと思いますし町民にとっての収入、かかわる雇用、そういったことが本来であれば後の目的としてしっかり念頭に置かなければいけないと思います。補助金があるうちに経営基盤をしっかりしたい大きな名目はあるわけですけれども、非常に努力しなければそういったものも難しいかと思います。そういったとき、多くの町民の皆さんを巻き込んでいく行政としてしっかりそのへんのヴィジョンと今後の収入、販路、産業としてつながっていくよう展開していっていただきたいと思うわけです。ぜひそのへんも含めた決意のほどを示していただけたらと思います。
○副議長 玉城光雄君 経済建設部長。
○経済建設部長 真境名元彦君 今取り組んでいる内容につきましては、一括交付金があるからやっているということではなくて、それも活用して、今後、南風原町内のいろんな特産品関係及び農産物関係も利用したものをより広く拡大していく意味で、まだ間もない状況ではございますけれども一歩一歩前進しながら今後取り組みを強化していきたいと考えております。
○副議長 玉城光雄君 2番 照屋仁士議員。
○2番 照屋仁士君 ありがとうございます。私たち議員もしっかりとそういった活動に取り組んで、またPRしていくよう取り組んでいきたいと思いますが、やはりPRについては宮崎県など一時は東国原知事が有名になったように、本町のリーダーとして町長の姿勢も大事だと思います。そのへんは今までの質疑も含めて、最後に町長からご答弁いただいて終わりたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。
○副議長 玉城光雄君 町長。
○町長 城間俊安君 仁士議員には今回、農業問題を取り上げてもらいありがとうございます。農業というのは一番の基本だと思っております。それをベースに私たちは生活を豊かにし、そしてまた今よく言われている6次産業においては、私たち南風原町は一括交付金を活用し、農業で生産して、作って、そして販売まで手助けするのが務めだということで自立するための助成をし、これが一歩一歩着実に進んできているのではないかと思います。商工会、町民が一丸となって私たち南風原町特産品で作って、そしてまた自分たちの製品が観光のPRとなり、日本中に羽ばたくようなものづくりをやっていく姿勢でいろいろな面でやってまいります。町長というのは、以前から申し上げている動く広告塔だと、私は営業マンです。仕事は職員、また仕事しやすいように動いて歩く、広告して歩くのが町長の務めである信念の基で頑張っていきたいと思っております。
○副議長 玉城光雄君 暫時休憩します。
休憩(午前11時39分)
再開(午後0時56分)
お問い合わせ
議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp