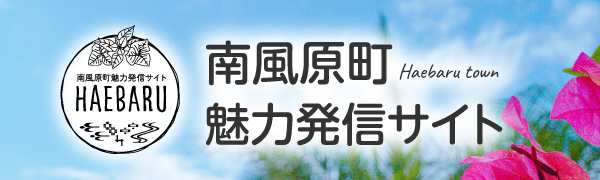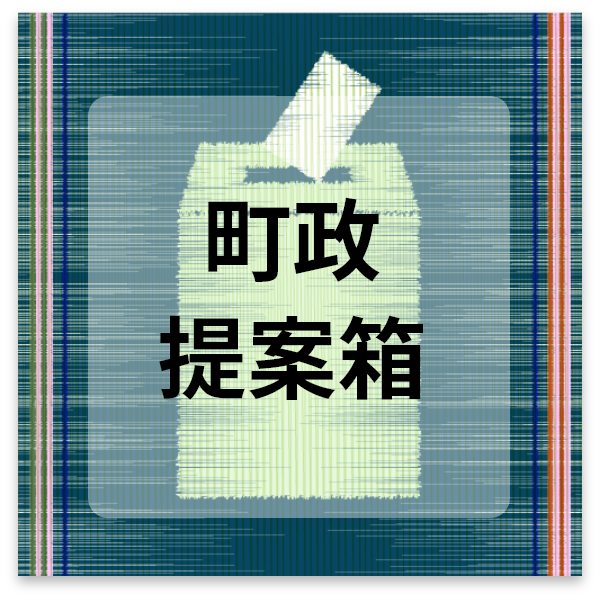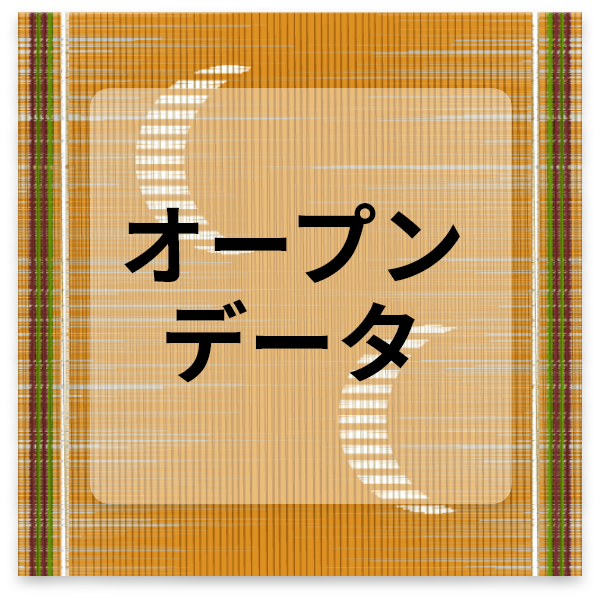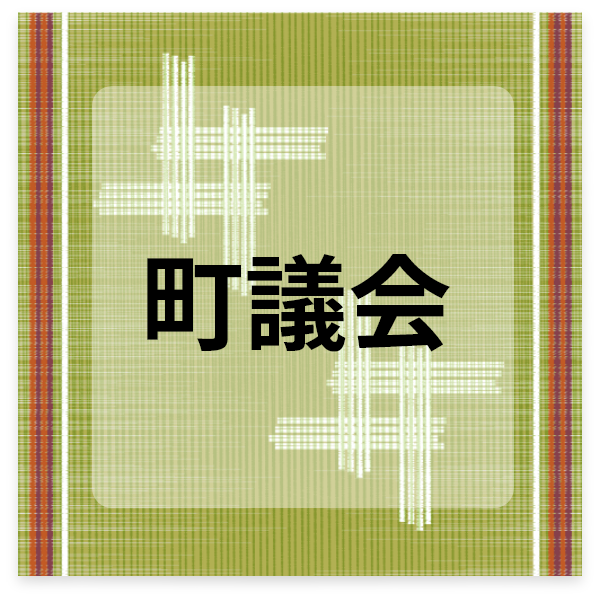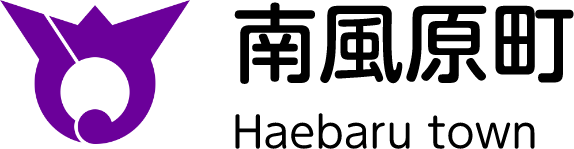本文
平成25年第1回定例会 会議録(第7号-1)
平成25年 (2013年) 第1回 南風原町議会 定例会 第7号 3月26日
検索
| 日程 | 件名 | 一般質問の内容 |
|---|---|---|
| 日程第1 | 会議録署名議員の指名 | - |
|
日程第2 |
|
|
| 浦崎みゆき 議員 |
|
|
| 宮城寛諄 議員 |
|
|
| 玉城光雄 議員 |
|
会議録
○議長 中村 勝君 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。
開議(午前10時01分)
日程第1.会議録署名議員の指名
○議長 中村 勝君 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって1番 玉城光雄議員、2番 照屋仁士議員を指名します。
○議長 中村 勝君 日程第2.一般質問を行います。それでは、通告書のとおり順次発言を許します。13番 玉城 勇議員。
〔玉城 勇議員 登壇〕
○13番 玉城 勇君 初めての対面方式での取り組みですけれども、第1回の定例会にして良い取り組みだと思っております。これが成功するように祈念したいと思います。それでは、本日最初の質問を行いたいと思います。まず1点目に沖縄振興特別推進交付金活用事業についてであります。平成24年度の一括交付金活用事業は何件であったかお聞きしたいと思います。
(2)同交付金の活用について、県内17団体で6億7,000万円の使い残しがあります。南風原町の状況はどうであったかお伺いします。
(3)平成25年度の交付金活用事業の調整は順調に進められているか。
2点目、宮城土地改良区内の安全対策について。以前にも質問しておりますけれども、その後の経過がどうなっているかお伺いします。(1)宮城土地改良区内の道路標示及び現在位置確認標示板の設置について進捗状況はどうなっていますか。
(2)交差点への停止線の取り付けはどのように検討されているか。
3点目、集落内住民の安全確保のための対策について。(1)集落内道路が狭隘にもかかわらず車両の速度があります。住民の安全を守るため、道路に凹凸を設けて車両の速度を落とす対策が必要と思うが設置できないか。
(2)道路が狭隘な地域で交通事故から住民を守るための対策はどのように行われているかお伺いします。
4点目、南風原町内の生活困窮者(世帯)の救済対策についてお伺いします。(1)生活困窮者(世帯)の救済並びに生活安全に向けての取り組みはどのように行っているか。
(2)就労支援の取り組みはどのように行っているか。
(3)困窮者(世帯)の生活を安定させるために、教育・学習支援と就労支援を併せて行う必要があると思うがどのように対策されているか。
以上、お伺いします。よろしくお願いします。
○議長 中村 勝君 城間俊安町長。
○町長 城間俊安君 皆さん、おはようございます。玉城 勇議員から沖縄振興特別推進交付金の活用のあり方とありましたが、南風原町としてもやりたいができない部分が今まであったわけですが、一括交付金のお陰でいろんな角度から町民要望、議員の要望等に応えることができたのではないかと思っております。しかしながら、初年度であるがゆえに右往左往して、また職員は通常業務以外に降って湧いたような事業だという部分もありまして本当に皆様方にご苦労をおかけしましたが、しかし職員一丸となって町民付託に応えるためにこの一括交付金を活用していくのだと、沖縄らしさ、地域の特徴に結び付けるためにはどうすればいいかいろいろな角度からノウハウを傾注し初年度においては大きな成果を上げることができたのではないかと思っております。しかしながら、2年度においては今回の反省を踏まえ、良かったものは継続しながら、また新しいアイディア等他市町村には私たちが思いつかなかった部分もありますのでそれも取り入れながら活用してまいりたいと思っております。具体的には(1)から(3)まで担当からお答えさせてもらいたいと思っております。
また2点目の安全対策についてでありますが、正に議員がおっしゃるように農道等においては怠っている部分があったと痛感しておりますので、標識等においてもぜひ議員がおっしゃること、問題点、農家の皆さん方や町民が通過するときにハッとするような部分がありますのでこれは警察とも連携しながらやってまいりたいということであります。具体的には担当からお答えさせてもらいたいと思います。
3点目の集落内安全確保のための凹凸の問題。これに対しても本当に議員が指摘されるように集落内においては凹凸がないがゆえにスピードを出して安全上厳しい状況もあって、以前にも議員から凹凸を付けるべきだというご指摘もあったような感じがするのですが、しかしながら事例として豊見城でしたか凹凸を作ってそこで事故が発生したときこの責任はどうなるのかと、道路を管理している市、町道では管理者である町でありますがその責任を問われて裁判等において負けた経緯があります。それで凹凸を控えるべきだということになって、セメントでやっていたものを全部撤去した経緯があります。
そういうこともありますので、凹凸を設置する場合においては何らかのカバーを設けて、クッションをポイントポイントに置いて、事故と結び付かないような工夫、方法も検討しながら警察とも連携していかなければならないと思っております。その件についても詳しいことは担当からお答えさせてもらいたいと思います。
また町内の生活困窮者の問題等においても、やはり私たち行政が手助けをし、学校現場とも連携をしながら進めていかなければならないと思います。これに対して詳しいことは各担当から説明させてもらいたいと思っております。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 私のほうから質問の1点目、沖縄振興特別推進交付金関連、それから2点目の土地改良区内の安全対策、それから集落内の安全確保について答弁いたします。まず1(1)でありますが、本町の平成24年度沖縄振興特別推進交付金を活用した事業は、補正予算提案時に配布いたしました資料のとおり人材育成事業、観光産業振興事業、環境にやさしいまちづくり事業、災害に強いまちづくり事業、子育て世代支援事業、文化歴史伝統継承事業、安心・安全な学校づくり事業、大災害時における電力供給及び避難拠点の整備事業の8つのパッケージからなる60の細事業となっております。
続きまして2点目であります。計画総事業費8億2,555万8,000円。交付金額が6億6,000万円であります。入札残などにより執行予算事業費額7億6,437万2,000円、補助金額6億1,110万円となり、事業費6,118万6,000円、交付金額で言いますと4,890万円の執行残を見込んでおります。
続きまして3点目であります。現在、平成24年度事業の実績報告等の準備と並行して平成25年度計画書を県に提出しております。今の段階では当初予算に反映されていない事業も含めて事業費ベースで5億976万5,000円、交付金ベースで4億781万2,000円の計画を立てています。平成25年度の本町の交付金配分額は6億円。事業費ベースで7億5,000万円の事業を計画する必要があります。残りの2億4,023万5,000円あまりの事業計画立案が必要となりますが、同事業についての調整は順調に進められております。
続きまして2(2)交差点への停止線取り付けについてであります。議員ご質問の停止線につきましては、与那原警察署に確認をいたしましたところによりますと、地域の理解が得られれば停止線を設置することは可能ということであります。ただ、停止線を設置することで法的な規制が発生します。そのことから地域の皆さんへ十分に説明し、それを認識していただく必要があるということであります。交通安全の確保のためには、注意を促す標識の設置などの方法もありますので、どの方法が一番良いのかそれは農地のなかに土地を所有している農家の皆さん、それから特に利用される地域の皆さんの意見も聞きながら検討してまいりたいと思っております。
続きまして3点目、集落内の住民の安全確保であります。町長からも答弁がありましたが、その点に関しては(1)と(2)は関連いたしますので一括して答弁させていただきます。与那原警察署によりますと、道路に凹凸を付けて速度規制を図る、あの凹凸のことをハンプと言うらしくハンプの設置につきましては特に二輪車や歩行者らの通行に危険が伴うこともあります。そのことから奨励はしていないとのことであります。交通安全確保については、道路法の規制によるものと地域事情に合わせた注意を促す標識の設置等の方法がありますので、こちらについてもどの方法がいいのか地域や警察、それから本町の道路管理担当課の意見も踏まえながらより有効な方法を検討していきたいと考えております。以上です。
○議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。
○経済建設部長 赤嶺 勤君 それでは、私のほうから2(1)宮城土地改良区内の道路標識設置の件についてでございます。ご指摘の道路標示及び現在位置確認標示等の設置については、町内全域を含めて今後平成25年度内に一括交付金を活用して事業化ができるかどうか検討してまいりたいと思います。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 それでは、勇議員の4.町内の生活困窮者の救済対策について(1)からお答えいたします。相談者の状況により生活保護につなげたり、生活保護の条件を満たしていない場合にはケースによって国の委託事業のホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業を行っているNPО法人いっぽいっぽの会や県の委託事業の母子家庭生活支援モデル事業を行っている、ゆいはぁとという法人につなげております。
(2)でございます。いっぽいっぽの会が行っている「絆」再生事業で、ホームレスまたは支障がなければ路上生活に陥るおそれのある方、ニート、ひきこもり等に対し技術支援の観点から総合相談、居場所の確保、食糧支援、緊急一時宿泊施設による支援など地域社会で自立し安定した生活が営めるように支援しております。そして、ゆいはぁとが行っている母子家庭支援モデル事業は、さまざまな課題を抱えて困窮している母子家庭に対して民間のアパートを借り上げて自立した生活が送れるよう就労支援を行っております。本町ではまちづくり振興課で行っている人材サポートセンター無料職業紹介所があります。人手が必要な農家と仕事を探している方が登録し、条件が合えば無料で仕事を紹介しております。それから町社会福祉協議会でもまちづくりサポートセンターを設置してございます。
(3)でございます。困窮者(世帯)の教育・学習支援等でございます。町独自の事業ではありませんが、県の事業として生活保護世帯には沖縄県子どもの健全育成支援プログラムで主に小学校高学年から高等学校入学前までの子どもがいる生活保護受給世帯であって、学力向上の支援を要する子どもたちがいた場合、子どもやその保護者が日常的な生活習慣を身に付けるための支援、子どもの進学に関する支援、ひきこもりや不登校に関する支援などを実施しております。以上でございます。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 それでは、1点目から一つずつ再質問をしていきたいと思います。まず1点目の沖縄振興特別推進交付金活用事業でありますけれども、8つのパッケージで60件という説明がございますけれども、当初の目標とするのと60件という件数は妥当なのか。それで満足していいのか。あるいは何件かできなかったものがあって最終的に60件だと思いますけれども、その総括的なものは出ているのかどうかお伺いします。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。昨日も沖縄振興特別推進交付金の質問について答弁いたしましたが、今般、交付金ベースで4,890万円の不用額が出ております。それにつきましては、当初の計画で確かに申請はしたものの内諾が得られなかった事業もございます。ただし、今回本町に割り当てられた交付額6億6,000万円の事業については全て執行できたと考えております。どうしても入札の残といったものがございまして結果的に不用額は出ておりますが、この事業の効果について当初見込んだ計画は得られたものだと考えております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 まず1点目から確認しますけれども、当初予定していたものよりも件数は落ちているが満足はしているとのことがありますけれども、平成24年度の一括交付金については2月あたりから準備をするようにということも提案にあったと思います。4月に入って中旬以降から要綱ができたということで取り組みが遅かったというのはございますけれども、一括交付金でできなかった事業については調査不足、資料不足、勉強不足もあったと思いますができなかったものがあるわけです。それについての反省はどうなのか。確かに2番目の点で言うとおっしゃるように交付金ベースでは満足したかもしれませんけれども、事業についてどうしてもやりたいと提案したけれども予算が付かなかった事業についてはどのようにお考えになるかをお聞かせください。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。沖縄振興特別推進交付金につきましては、沖縄振興に資するもの、沖縄の特殊性があるもの、その課題を解決するものですね、そういった枠と言いますか制約のなかでの事業の展開でございます。そういうことからどうしても本町ではニーズが非常に高いのですが沖縄に特化したもの、全国に比べとにかく沖縄だけに課題があるものというようなことからしますとどうしてもこの推進交付金事業の採択が得られなかったということもございます。今回、他の市町村でも平成24年度には事業の導入と言いますか説明をうまくやってと言いますかそのへんで採択された市町村もございます。ですから、そういった市町村の内諾を得られた事業も参考にしながら、特に本町の課題解決に対応できる事業を工夫しながら取り組む必要があるとは考えております。
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前10時24分)
再開(午前10時25分)
○議長 中村 勝君 再開します。13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 最後の確認をしますけれども、町長も町民の要望に応えることができたということでありますが、今回の平成24年度の交付金活用事業についてはまだまだ全町民に下ろしての募集ではなかったと思います。もっと早い時期に各種時団体あるいは町民からの公募をやるべきだったのではないかと思っております。それができなかったわけでありますので、まだまだ町民要望を受け入れていないというのがございますけれども、これについての検討がなされているのかどうかそれをお聞きしたいと思います。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。平成24年度スタートのこの交付金事業なのですが、実際に事業がスタートしたのが年度も明けて5月、6月ごろでした。どうしても先ほどから答弁しているように沖縄振興に資するものという制約のなかでの事業の展開でしたので、どういったふうに事業採択に向け取り組んでいくかも暗中模索しながらの取り組みでした。そういったことでいろいろ時間的に時差があっての内諾申請とはなっていったのですが、本町としては配分された額は全て申請してあるということであります。それ以上の事業と言いますと、枠配分以上には申請ができないこともご理解いただきたいと思います。それから、いかに町民の意見を反映させるかということになりますが、それにつきましてもこういった時間の制約のなかで事業もいろいろ選別していくと、より沖縄振興特別推進交付金の趣旨に合ったものを踏まえながら本町の課題を解決できる事業を実施していくには、全部が全部を採択して、それをひとつひとつ確認しながらではどうしても時間的に制約があるということであります。そういうことからやはり、地域の皆さんの声を例えば自治会長が拾って申請していただく、それから議員の皆さんの声も地域の代弁者の声として聞く、それから各種団体の声、そういった声を吸い上げると言いますか皆さんの意見を吸上げていただいて町に提言していただいてそれを事業化していくという段階を踏んだほうがより効果的ではないかと考えております。平成25年度も基本的にはそういった方針で取り組んでいきたいと考えております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 1番目の最後に、8のパッケージで60件ですけれども、皆さんが検討したのは全体で何件あったか教えてもらえますか。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。計画と言いますか、80件の案が出されております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 2点目に移りたいと思います。本町の使い残しが4,890万円。60件のなかの入札残あるいは事業残との説明ですけれども、4,890万のなかから新たな事業を検討することはできなかったのか。入札残のみであれば消化できないのか。それについてはどうですか。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 先ほども少し触れたのですが、4月当初から全ての事業が内諾を得られて開始しておけばそういった別の事業への展開も可能性は大いにあったと思います。ただ、12月、年末頃に認められたこともありました。それからこの事業は、その事業内容によるのですが基本的に繰越が認められておりません。また、3月いっぱいですから今月29日までに実績報告が求められております。事業のスタート時期によっては年度内ぎりぎりまで事業がかかったものがあります。そういったことから、次への別の新たな事業への展開がどうしても厳しかったことがあります。ただ、事業によっては例えば入札残のもとでまた変更契約して個数、台数を増やしたものとか、施工する面積を増やしたのもあります。本町としましては、できる限りと言いますか残がないように変更契約で数量等を増やせるものについては対応をしてきたことをご理解いただきたいと思います。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 少し気になるのが、6億6,000万円のうち使い切ったのが80パーセントちょっとですか。約5,000万円としても結構残った額があるものですから、それと関連しますけれども、県の17団体で6億7,000万円の使い残しがあると3月6日の県の2月定例議会で出ております。この不用額について可能な限り他の事業や追加予算が必要な市町村に振り分ける検討が答弁で出ているわけですけれども、3月にこういうものが出て、部長が今おっしゃるように3月に出ても3月中に報告しなければいけないから新たな事業は無理だとのことですが、この県の方針についてどう考えられますか。要するに、仮に本町があと1件事業をしたいと、やろうと思ったけれどもできなかった、予算がなかった、県全体の予算があまっていると、それを活用したいという要望を出したらできた可能性があるわけですけれども、これについて対応が難しいとの判断であります。こういう方針を出した県に対してどのように思うのか。あるいは町としてこれが分かっていれば対応できたのか。どうお考えになりますか。
○議長 中村 勝君 宮平 暢企画財政課長。
○企画財政課長 宮平 暢君 それでは、お答えいたします。まず県から残について各市町村へ問合せがありました。それには非常に限られた条件がありました。3月にきまして、3月の補正予算で予算を計上して、3月いっぱいに事業を完了すること。3月いっぱいと申しましても29日に県へ実績報告を出すことができる事業ということで、事業計画を立てて予算を提出して、そのあと実際の執行期間は正味10日もないような限られた事業内容になることになっておりました。県内では2町村が元々あった事業を前倒しでできるということでそこへ配分ができたのですが、南風原町としては相当限られた期間でありましたので事業を追加で提案することはしておりません。また、この県の考え方については、県も一括交付金を最大限活用しようということがありまして、ぎりぎりになったかもしれませんがそれに対応できる市町村はないかということで県もやっておりますので、県もぎりぎりの対応であったのかと考えております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 分かりました。(3)で併せて質問したいと思います。平成25年度の計画を進めておりますがそれが順調かどうかということでございますけれども、まだ2億4,000万円あまりの計画がなされていないというのと、今回県の方針がこのように示されたということは平成25年度についてもっと早めに計画ができるわけですね。平成24年と同様に県全体の交付金の残が出る可能性があるわけです。それに向けての対応も含めて南風原町は検討されていくのか、ご答弁をお願いします。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。あと2億4,000万円余の事業立案が必要でございますので、まずはその本町に振り分けられた分の事業計画をしっかりと立てることが前提だと思います。それをやった後に喫緊にと言いますか、それでも対応が可能であれば、先ほどのように全県的な予算残への対応ということで次の段階で考えるべきだと思っております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 ぜひそのように前向きに検討していただきたいと思います。それと前回もお話したのですが、やはり広く事業計画を募集していく。町民も2年目に入りましたのでそれぞれいろんな情報を持っております。職員の皆さんも大変だと思いますけれども、優秀な能力を持っている町民がいっぱいおられますので募集をしてそれをまた精査していけばいいわけですから、町民が参加できるような一括交付金の事業にしていただきたいと思います。ぜひ前向きに検討されてこの6億円の素晴らしい結果が出るようにがんばっていただきたいと思います。
それでは、2点目の宮城土地改良区内の安全対策についてお伺いします。道路標示版について町全域を対象に事業化を検討していくとのことでございますけれども、ずっと以前から提案しておりますが特に土地改良地区内の道路は道路名称がない関係で、そこで事故が発生した場合に警察や消防署への連絡が非常に難しい。救急車も近くまで来ますが周囲をぐるぐる回っている状況もございました。ですから、今いる場所がすぐ分かるように、あるいは消防へすぐに通報できるような体制が必要であるということで再三提案しておりますけれども、早急にその道路名称あるいは道路の番号と言いますかそういったものを決めて看板を設置する必要がございます。平成25年度の早期に、5月、6月にでもできるように取り組みをお願いしたいのですけれども、平成25年度に検討ではなく平成25年度に設置していただきたい。これについてはどうですか。
○議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。
○経済建設部長 赤嶺 勤君 一括交付金の活用については、ただいま総務部長からありました観光、人材、災害などいろいろな制約がありまして、申請する側の部課からの趣旨内容によってだいぶ左右されることがあると思いますので、そのへんはしっかり要望内容を確認して早めに事業ができるよう経済建設部でやっていきたいと考えています。
〔「休憩願います」の声あり〕
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前10時42分)
再開(午前10時42分)
○議長 中村 勝君 再開します。
○経済建設部長 赤嶺 勤君 申請したものを県が審査するものですから、なかには先ほど総務部長からありました平成24年度は80件ぐらい申請したけれども事業化できたのは60件が対象となっています。申請はするけれども、あくまでも審査するのは県ですから採択されるかどうか別の話となります。われわれとしては、申請が滞りなくできるよう早い時期に申請内容を精査して、どうにか事業化できるようがんばるとしか今のところお答えできないと思います。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 ぜひやっていただきたいと町長にお願いしたいと思います。それぞれの土地改良地区の道路は、同じような状況でたぶん近年交通量も増えていると思います。そういった意味で早急に対応をお願いしたいと思います。
では、交差点の取り付けでございますけれども、総務部長はいろいろと地域住民に不利益があるのではないかとの説明であります。最後にどの方法がいいか検討していくとのことですので、どの方法がいいのかはぜひ早急に検討していただきたい。地域の皆さんとの話合が必要であればそれも早急にやっていただいて、ここで事故が起きないように早めに取り組みをしていかなければ、土地改良区内の道路と言っても、農道と言うよりも地域によっては基幹道路となっている所もございます。標識は全くございませんので十字路でも結構なスピードで横断している、そういう場所がたくさんございます。まず現地も確認していただいて、安全なのか危険ではないのかぜひ現地をご覧になって判断していただきたい。必要であれば早急に対応していただくようお願いしたいと思います。
それでは、集落内の安全確保に移りたいと思います。集落内道路の凹凸、ハンプですかその設置でありますけれども、現在与那原町に設置されています。それから、那覇市の小禄地区においてはハンプではなくて交差点を盛り上げています。そういう場所がございます。これについても対応はどのようになっていたのか、もし調査されていればお答えをお願いしたいと思います。
〔「休憩願います」の声あり〕
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前10時46分)
再開(午前10時46分)
○議長 中村 勝君 再開します。新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 お答えします。与那原町のハンプについては確認しております。小禄地区についてはまだ確認を取っておりません。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 与那原町がどうして設置できたのか。与那原署が目の前にありますけれども、新島、大見武等に設置されております。設置した理由は明らかでありますが、これが設置できたのはどういう理由なのか。それから、那覇市においても交差点、交差点全て5センチ以上の盛り上がりを作っているわけです。車は一旦止まるか徐行しなければいけない状況を作ってありますが、それは市の事業としてなされているわけです。そのへんをどのように調査されたのか、あるいは見たのか、もし話を聞いたのであればそれをお答え願いたいと思います。
○議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。
○総務部長 新垣吉紀君 与那原町に関しましては、町が道路管理者としての判断で設置したとのことであります。ただ、先ほども申し上げましたが警察としてはこの方策は推進していないとのことであります。確かに私自身も何回か通ったことがあるのですが、歩行者が歩く部分までハンプ付けられていますので、たぶん夜間など自転車、そして歩行者にしても、オートバイにしても初めて通る方であれば、もしかしたらジャンプしてしまうこともあのぐらいの高さだったらあるのではないかと感じます。小禄地区の交差点全体を盛り上げている方法については、まだ確認を取っておりませんので調査する必要はあると考えております。
与那原町の情報なのですが、本町の都市整備課からの情報ですが道路管理者の判断ではなくて交通安全担当者の総務課が行ったと、道路管理人とは調整を行わずに設置されたということでございます。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 与那原は確かに役場が設置しております。与那原署としては推奨、推薦は全くないのですけれども、与那原署にはその権限がありませんと、これは道路管理者の判断ということなのです。ただ、そこで事故が起きた場合は設置者に問われるということを言っておりますが、現に与那原町には設置されている、小禄にもそれがあるという状況であります。オートバイや自転車がジャンプするような高さではなくて、ちょっとした凹凸を付けるだけで運転者は気が付くというのが目的であります。ジャンプするような大きな凸凹ではないわけです。5センチ程度にするか、市販の材料があります。そこらへん検討をすべきではないかと思います。与那原署としても駄目ですよとは言えないということで、あとは管理者である町の判断でありますのでそれについては総務課あるいは都市整備課、道路管理について調整で、道路が狭くてもスピードが出る箇所については対策が必要だと思いますけれども、もう一度どうでしょうかお答えをお願いしたいと思います。
○議長 中村 勝君 城間俊安町長。
○町長 城間俊安君 今おっしゃるようにハンプ、突然凸凹にすると大変なことになるので滑らかにやっていくこと、またこれは地域の皆さん方の理解がまずなければいけないのではないかと思います。100メートルに1カ所にではなくて10メートルに1カ所ずつ小さな波を打っていくとドライバーの皆さんには凹凸が多過ぎてむしろ不便が出てくるのではないか、無くしなさいと言われる可能性もあります。また、車体が低くて小さな凸凹でもかかるような車もありますので道路管理をしている町が責任を問われる部分もあります。例えば宮城の集落内にやるのであれば、区長名で、また地域の皆さん方の賛同を得てやっていくのかどうか、こういうことも判断は町が決定するのではなく地域と連携しながら、また1メートル間隔で小さな盛り上がりを作っていけるようなもの、またその経費についてはどうなのかも含めて今後の検討課題ではないかと思っております。即やります、やりませんではなく、もう少し検討を十分に詰めさせていただきたいと思っております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 町長がおっしゃったように緩やかにです。幅5、60センチで5センチぐらい。与那原町がやっているように道路全てではなく、交差する手前なのです。ですから、停止線の代わりにもなるわけです。そういった意味で、地域内の集落には交差点が多いですからそれ全て置きなさいではないのですが、少なくとも部落の出入口には設置することによって、そこを1回通ったドライバーはそれがあることを認識できますのでスピードが落ちていく、そういう効果が得られます。これについては昨年も質問をしております。ですから、検討を急いでいただいて要望があれば早急に設置していただきたいと思いますのでぜひそのように対策を取っていただきたいと思います。それぞれの部課にも指導していただきたいと思いますので一つよろしくお願いいたします。
それではこの件で、町でもこういうものが今検討されておりますけれども、これもスピードを落とすための一つの方法だと思います。ですから、これもそれぞれの集落内に早急に取り付けして意識を与えていただきたい。それもやりながら、この安全対策については検討していただきたいと思っております。できるだけ多くの枚数を確保されて、それぞれの地域の危ない箇所には早急に設置をお願いしたいと思っております。これが集落内の狭隘な道路は歩車道の区別もありませんので、そこでスピードが出ていると接触事故の可能性もありますし、それから交差点での飛び出しもありますのでそういったことが起きないように早めの対策をお願いしたいと思います。良い看板ですので早急に設置をお願いしたいと思います。
それでは、4点目に移っていきたいと思います。生活困窮者には今いろんな種類があると思います。病気で仕事ができない、怪我をして仕事ができない、健康だけれども仕事がない、いろんな状況がありますけれども、全てを一編にクリアするのは難しいですが、ひとつひとつの取り組みをやっていただきたい思いからこの質問をしております。まず町内の生活困窮者(世帯)がどういう状況なのか調査されて、前回もこういう質問をして社会福祉協議会やいろんな団体からの要請で把握していますとのことでありましたけれども、やはり町としても逆にそういう団体を集めてどういう状況なのかと、あるいは民生委員の皆さんを集めて各地域が今どうなっているのかと早めに状況把握をする必要があると思うのですけれども、今後どのように情報収集あるいは実態把握をやろうとしているのかお答えをお願いできますか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。生活保護については保護世帯ということで数値はございますが、それ以外の困窮世帯ということで以前にもご質問がございまして数値等示したことがあります。これについては、町社会福祉協議会が年末年始等の赤十字等での剰余金と言いますかそれで各字民生委員等含めて調査して金額は少ないのですがいくらか助成しております。あの数に近いのが実数かと思います。それに漏れる方もいるかもしれませんが、そういうことで把握についてはできるかと思っています。今後もそういうものがあれば地域の把握調査も含め、民生委員を含めて調査等し把握したいと考えております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 県内どこでもそうだと思いますが、生活保護については県がやっており、病気や療養費などの制度は本町にもございますがしかし、何とか体は大丈夫だという生活困窮者の救済が本町の条例にもないのです。救済する方策が例規集のなかには一つもないです。ですから、今後どのようにしてこの生活に困っている皆さんを手助けしていくのか、それを本町も考えなければいけない時期ではないかと思います。その方法として、まずある一定動ける皆さん、健康な皆さんには就労の場を与える。就労支援はいろんな方策を検討していいと思うのですけれども、部長が先ほどおっしゃった農家への紹介、これは製糖期間や野菜の収穫あるいは果樹の収穫といろいろありますけれども、せめて半年程度の期間を紹介するとかそのへんが必要だと思うのです。短期間の就労ではやはり解決が難しい。せめて半年、一年やれば、本人が新たな仕事を探す時間が与えられます。それから、仕事の内容についても農家の支援のみではなくていろんな仕事があると思いますけれどもそのへんの検討も必要ではないかと思われます。一つの方策として学校大工ですが、先日も北丘小学校へ視察に行きましたが今回大規模改修がありますがそのなかにトイレの修繕とか剥がれているタイルの修繕あるいはいろんな細かい作業があります。そういったものは現在学校大工がやっている仕事でも十分できると思うのです。ですから各学校を調査すればある一定量の仕事があると思います。そこに学校大工を中心としてその皆さんを集めて修理をするとか、要するにこのへんの仕事ができる皆さんもいらっしゃるはずなのです。そういったものを探してあげるあるいは与えてあげるというのも一つの方法だと思うのです。ぜひ検討して欲しいのですが、それについて民生部と経済建設部との協議が必要ですけれども、どうお考えになりますか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 お答えします。1回目の答弁で社会福祉協議会のまちづくりサポートセンター、まちづくり振興課の人材サポートセンターについては、一日とか時間区切りで単発的な仕事でございます。どこまでが困窮者かという部分もございますけれども、なるべく長い時間と言いますか3カ月や半年等について議員がおっしゃるのは町でできる仕事、町の直営でできる仕事と言うのですかそういうものがどうにか配分できないかというお話だと思いますので、これについては建設部でやっている部分、学校で行うものがありますのでどういう方策があるかについて町全体として検討できる部分についてはやっていきたいと思っております。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 それでは、今の就労支援についてもう少し踏み込んで質問したいと思います。本町の発注する事業がたくさんございますけれども、半年以上の工期の事業については生活困窮者の皆さんを全て1人ずつその現場に入れてくれとか、それからできる仕事があればぜひ地元町内の皆さんをその現場に1人は採用してくれと、そうすれば半年程度の仕事ができます。そのへんの条件と言いますかお願いをしてその現場で使っていただくというのも一つの方法ではないかと思いますけれども、まず経済建設部ではどのように考えますか。
○議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。
○経済建設部長 赤嶺 勤君 本町としてはまだ事例がありませんので、もし他の町村でそういった業務をなされているところがあれば詳細を調べまして、町になじむかどうか部内でも検討して、できるのであればやっていきたいと思います。まず調査することからということで答弁といたします。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 本町にシルバー人材センターがございませんので、この情報を把握している社会福祉協議会の担当が生活困窮者の情報を知っていると思います。そこを窓口にしながら、こういう皆さんの情報を入手して、今の質問の仕事を与えることができるのであればぜひ進めていっていただきたいと思っております。経済建設部と民生部でぜひ連携していただいて、この情報把握を採用に繋げて対応していただきたいと思います。
最後に質問しますけれども、南風原町の例規集のなかにこういった手助けをする条例あるいは規則、規程、要綱等もございません。ですから、今後、それらをまとめて仕事を与えたり紹介したりできるNPOの設立とか、あるいは本町でできるような条例を作ったりする必要があるのではないか。南風原町の困窮者を救うためにも町としてのいろんな施策が必要だと思いますので、それをやるために条例を作成することも方法であります。ぜひそこまでいけるように本町も県やあるいは他市町村の事例を調査されて、南風原町独自の取り組みができるように進めていただきたいと思います。町民皆がある一定安定した生活ができるよう皆さんの取り組みをお願いしたいと思います。最後にその思いを述べていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 困窮者(世帯)の就労を含めて救済対策については、県内あるいは他府県含めて条例等あるいは要綱等どういうものがあるか調査して検討していきたいと思っておりますのでしばらく時間がかかると思いますが、調査してみたいと思います。
○議長 中村 勝君 13番 玉城 勇議員。
○13番 玉城 勇君 部長、ありがとうございます。ぜひ本町の取り組みを期待したいと思います。それでは、最後に申し上げたいと思いますけれども、生活困窮者の世帯は、やはり厳しいものですから子どもたちが塾に行けないあるいはいろんな面で資金が足りなくて困っている面がございますので、その子どもたちが自分の友達のように塾に行けるようにするとか、その教育・学習の支援、併せて両親の就労支援をセットにして検討していかなければいけないと思いますので、今後そのような取り組みを検討されて進めていっていただきたいと思います。以上、終わります。
○議長 中村 勝君 暫時休憩します。
休憩(午前11時11分)
再開(午前11時19分)
○議長 中村 勝君 再開します。順次発言を許します。12番 浦崎みゆき議員。
〔浦崎みゆき議員 登壇〕
○12番 浦崎みゆき君 こんにちは。では、2番バッターがんばってまいりたいと思います。まずその前に訂正をお願いいたします。2(2)1行目後半に「保護者に」とありますその文字を削除していただきたいと思います。
それでは、通告にしたがいまして一般質問をいたします。1項目ごとに一括質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。まず給食アレルギー対策についてお伺いいたします。東京調布市の小学校で給食を食べた女子児童が、食物アレルギーに伴う急性症状アナフィラキシーショックの疑いで亡くなる事故が起こりました。事故に至った状況は、男性教諭が給食の残りのジャガチヂミをおぼんに載せおかわりの欲しい人と言って教室を回っていました。女の子が手を挙げ、粉チーズ入りのチヂミを受け取り食べてしまった。学校側は、初めに女子児童に出したチヂミには除去食が出されており、おかわりのチヂミには粉チーズが入っていた。また、食べてはいけない食物にバツ印を付けた除去食一覧表を用意しチヂミにはバツを付けていました。しかし、担任教諭は確認せずチヂミを渡してしまった。約30分後、女子児童は気持ちが悪いと訴えた。担任はアレルギー症状の改善薬が入った注射を打とうとしたが女子が嫌がったのでそのままにしていましたが、校長の判断で注射を打った時には約10分が経過をしてもう間に合わなかった。女子児童は搬送先の病院で息を引き取りました。警視庁は業務上過失致死容疑の可能性も視野に捜査をしているとの報道がありました。そこで本町における取り組みをお伺いいたします。
(1)宮平保育所や小学校では食物アレルギーを持つ児童生徒に対し、アレルギーを起こす食材を除いた除去食を提供しているか。
(2)給食で食物アレルギーに伴うアナフィラキシーショック及び似たような症状を起こした事例はあるか伺います。
(3)アナフィラキシーショックを緩和できるエピペンの使用は、保育士、教職員に周知徹底されているか。
(4)人為的なミスを起こさない対策をどのように取っているかお伺いいたします。
○議長 中村 勝君 赤嶺正之教育長。
○教育長 赤嶺正之君 それでは、町立小中学校や町立宮平保育所における給食アレルギーに関するご質問にお答えいたします。なお、宮平保育所につきましては、担当部局の確認を得ておりますので併せて私のほうから答弁をさせていただきます。
(1)現在、町立小中学校の学校給食ではアレルギーを引き起こす食材を除いた除去食の提供はしておりません。宮平保育所ではアレルギーを持つ児童が2名在園しておりますので提供しております。
(2)ご質問にある症状の発症について、学校給食による事例は小中学校ともございません。宮平保育所ではこれまでもそのような事例はございません。
(3)現在、エピペンを携帯している生徒がいる学校は1校しかありませんので、大方の学校では十分に周知されている状況ではございません。エピペンを携帯している生徒がいる学校では、養護教諭が実技研修を受講したり教職員に周知をしたりしております。宮平保育所ではエピペンを使用する児童が在園していないため、使い方の周知はしておりませんが、厚生労働省から平成23年3月17日付食安発0317第1号で、保育所におけるアレルギー対応ガイドラインが作成されております。該当する児童が入所した場合には、本ガイドラインを参考に迅速な対応をすることになります。
(4)給食アレルギー対策については、アレルギー児童の把握に努めたりアレルギー症状のある児童生徒の保護者にアレルギー献立表を配布し保護者と児童で確認をして給食を取るなどの対策を取っております。なお、牛乳アレルギーの児童生徒に対しましては、牛乳をお茶に変更して対応しております。宮平保育所では、調理人が給食等を調理する際には食器食材調味料等を別々にして調理しており、一時預かりも含め新入園児には保育所で初めて食べる食材は保護者と連携して調理しています。保育士もクラス担当保育士だけではなく、全職員が情報を共有し細心な注意を払っております。また、調理人はアレルギー除去食に関する研修会にも参加させております。以上でございます。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 小中学校ではアレルギーを持っている子はいないということでよろしいですよね。保育所で今お二人いらっしゃるということです。アレルギーに関しての申請と言いますかそれはどのように行われていますか。例えば保護者が診断書を出して申請をするのか、自己申告で行っているのかそのへんはいかがでしょうか。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 再質問にお答えします。現在、宮平保育所には2名いらっしゃってAさん、Bさん、同じアレルギーでありまして、食物アレルギーアトピー性皮膚炎ですね。卵が9程度の反応があるということで、2名とも医師の診断書を出していただいて、それに基づいて対応してございます。
○議長 中村 勝君 仲里 淳学校教育課長。
○学校教育課長 仲里 淳君 お答えします。先ほどの教育長の答弁は、アレルギーを有する子について、いないということではございません。学校給食による発症の事例がないということでございます。小中学校におきましては、食物アレルギーを有する児童生徒がおりますので、少し訂正をよろしくお願いしたいと思います。この食物アレルギーを学校でどう把握しているかにつきましては、小学校の事例で申し上げますと毎年4月には保護者へ家庭調査票をとおしてアレルギーの有無を確認してございます。それで確認を取り、またさらに家庭訪問等で保護者への再確認をしているということでございます。以上です。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 それでは、小学校、中学校にアレルギーの方はいらっしゃるということでしたので、保育所は2名とお聞きしましたが小学校、中学校にはどれぐらいの人数なのか把握していらっしゃいますか。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 小学校、中学校の食物アレルギーの児童生徒ということで、平成25年2月現在での確認で小学生が68名、中学生が34名になっております。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 申し訳ございません。訂正します。小学校が68名、中学校が48名でございます。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 これだけアレルギーを持っていらっしゃる方がいて除去食は作られていないとのことですが、再度確認をして、除去食を作らなくても大丈夫なのでしょうか。
○議長 中村 勝君 島袋義規教育総務課長。
○教育総務課長 島袋義規君 お答えします。現在、学校給食調理場ではスクールランチメニューとは別にさらにそのアレルギー児童生徒の詳細な献立も毎月作成して、その献立表に基づいて保護者と本人が給食を食べるかどうか各判断している状況でございます。
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前11時32分)
再開(午前11時32分)
○議長 中村 勝君 再開します。
○教育総務課長 島袋義規君 失礼しました。除去食を準備していません。しかし、学校給食調理場は毎月のスクールランチメニューとは別にアレルギーの子どもたち用の献立表を作成してそれを保護者に配って、それを見て給食を取るか取らないか判断対応をしています。特に弁当持参とかそういったことは学校から聞いておりません。以上です。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 ということは、メニューをいただいて、例えばアレルギーの卵や牛乳が入っていればその子はその日、給食を食べられないのですか。それと弁当はないとのことですので、それに代わる何か別のものがあるのですか。お願いします。
○議長 中村 勝君 仲里 淳学校教育課長。
○学校教育課長 仲里 淳君 お答えします。先ほどの学校給食の対応につきまして代替食ということではございませんで、例えば牛乳アレルギーのお子様につきましてはお茶で対応し、それから教育総務課長からありましたアレルギー献立表をその有する子どもたちに配布してございますので、保護者と本人がその内容を確認して、アレルギーの原因物質を分けて食べるとかそういった対応をしているということでございます。必ずしも給食が全て食べられない子だけではなくて、食材の中身を分けて食べたりする児童生徒もいますので、先ほどのアレルギーを有する児童生徒が給食全体を食べられないのではないということです。牛乳アレルギーにはお茶に変える、給食そのものについてはその原因物質を外して食べるというような対応ということでございます。以上です。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 今の答弁によりますと、そのアレルギーを持っている小学校68名、中学校48名の方は、自分に合わないものは取り除いて給食をいただくということで、その栄養に関して他の子とは足りない部分が出てくるのですよね。他の人が食べられる物を自分は食べられない、例えばおかずの中に卵が入っていて食べられないからパンと牛乳というそんな感じになるのかと思うのですけれども、そもそも除去食を作らない理由は何なのでしょうか。
○議長 中村 勝君 島袋義規教育総務課長。
○教育総務課長 島袋義規君 除去給食を作らない理由としては、現在の施設や人数の確保等の問題も一つあり除去食を提供するのは難しくなると思います。おおまかな理由としては、調理用の機材、まな板とか包丁、釜などにも残渣等が残っていたら困るということで厳しいということです。さらに、調理室も食材が紛れ込んでは困るので隔離のちょっとした調理室も必要だということで厳しいと考えております。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 除去食に関して私は沖縄県は調べておりませんけれども、それを採用している学校は年々多くなっております。アレルギー自体も増えてきております。やはり今のこの状況で除去食を作る際、確かに今言われたいろんな課題もありますがそこらへんはクリアすべき点もあるかと思いますけれども、まずはそもそも除去食の献立から作ったあとに一般の子どもたちの給食を作るというような手順になっているようでございます。ですから、できないことはないのではないかと思いますが、これだけの人数のアレルギーの方がいて言わば個人任せと言うか本人任せでは、本人が考え違いをして食べてしまったときどうなるのか今聞いていて懸念も感じました。この除去食に関しては、ぜひ調理場と連携を取っていただいて本町の調理場の施行規則で連絡協議会を毎学期開くとされておりますのでそこでしっかりと情報や問題点を話合われて、本町でも除去食をぜひ作っていただきたいと思うのです。連絡協議会はもっていますでしょうか。また給食調理場からそういう要望などはないのでしょうか。アレルギーのメニューまで作成しているわけですから、そのへんの要望なり、または父兄からの要望はないのでしょうか。
○議長 中村 勝君 島袋義規教育総務課長。
○教育総務課長 島袋義規君 運営委員会のなかでは、除去食やアレルギーについては話しておりません。以上です。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 アレルギーに関しては社会問題にもなっていますし、先ほど申し上げた事例が本当にあるわけですから、本町においてないということはあり得ないと思います。いずれまたそういった事件が出てくるかもしれませんのでそのへんの対応をしっかりとお願いしたいと思います。このあいだ新聞に載っていました那覇市におきましても4人の方でしたか救急車で運ばれた事例があったとのことですので、本町に限ってないとは言えません。ぜひ対応、話し合いを持っていただいて、また保護者が要らないと言うのであればそれはそれでいいかもしれませんけれども連携を取っていただいてしっかりと対応をお願いいたします。もちろん、そういったショック症状を起こした事例はないということでした。
(3)のエピペンの使用ですが、保育士、教職員への周知徹底がされて、養護教諭でしっかり指導しているとのお話でしたけれども、実際細かくどのような体制で周知徹底がされているのかもう一度お願いします。
○議長 中村 勝君 仲里 淳学校教育課長。
○学校教育課長 仲里 淳君 お答えします。アレルギー対策の周知徹底についてですが、平成20年に…
〔「休憩願います」の声あり〕
○議長 中村 勝君 休憩します。
休憩(午前11時43分)
再開(午前11時43分)
○議長 中村 勝君 再開します。
○学校教育課長 仲里 淳君 失礼しました。エピペンの使用についてでございます。学校でエピペンを使用する生徒がございますけれども、日頃からエピペンの所持など確認の声かけをしているということでございます。去年の12月、エピペンの研修会がございました。この生徒のいる学校においての研修ではございませんでしたけれども、新年度から幼稚園にエピペン保持の幼児が入園予定もございまして、その研修会に幼稚園の先生方が全員で参加しているという研修等々してございます。
養護教諭が研修して職員へ周知する方法につきましては、平成20年に「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」が文部科学省から届いておりその文書内容に沿って教職員に周知をしていると、そのエピペンの使用法、対応法について先生方に周知をしているということでございます。以上です。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 この研修が去年の12月、また養護教諭からガイドラインに沿った講習を受けているとのことですけれども、それはかなり受け身であってただ聞き流す程度になっているのではないかという感じがしたわけです。この周知徹底がされない限り、先ほどの事例にあった担任教諭が打とうとしたのだけれどもその子が嫌がったらしいのですね。それで打たなかったということで本当に命を落としてしまったというようなことがあります。実際にエピペンがどういうもので、どこに打って効果があるのだとしっかり担任お一人お一人が自覚をしない限りそういう事故はまた起こってしまうかもしれません。そもそもエピペンとはアドレナリンで、自己注射ができるものなのですね。ショック状況が起きたとき、それを打つことによって医療機関へ搬送されるまでの症状悪化の防止に役立っている。1本1万5,000円ほどするのですけれども、2011年より健康保険が適用になって患者本人、またそれを周知している家族、救急救命士、保育士、学校教職員もエピペンを打つことができるようになっている。学校の先生のなかには、現時点でもエピペンを先生が使用してもいいと認識している方はわりと少ないように見受けられるところもあります。打ってもいいものなのかどうなのか、自分は医者でもないのにとかそのへんがあるようですが、学校の先生、保育士さんも打てるのだと周知徹底をしていただいて、しっかりとした講習会、分かっているかどうかぐらいのアンケートを取ってもいいほどではないかと思うのです。周知徹底されているのかを確認する方策、今言ったアンケートなど取れるような、その講習会のなかででもよろしいですので必要ではないかと思うのですが、それについてはいかがでしょうか。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 ただいまエピペンの件でございましたが、先ほど担当課長からもございましたように現在1校、エピペンを所持している児童生徒がおります。その学校では、その生徒の顔写真なりを職員に確認をしているようです。それから、アレルギー関係の質問を各学校に配布して集約しているところからしますと、日頃からその児童生徒の顔写真等の確認を先生方でやっているようです。今は1校しかございませんので、そういった確認の声かけなどを職員の皆さんで行っているということです。それから、職員、担任の教諭、教科担任等も併せて生徒とのコミュニケーション等を取ってそういったことには対処していくことになっています。今後、食物アレルギーを持った多くの児童生徒がおりますので、所持をしている分に関しては学校にも徹底していきたいと思います。
それから、先ほどの回答にもございましたように、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインが学校にも配布されています。先ほど議員さんがおっしゃっていましたように、学校の先生でもエピペンが打てるのだと、医療行為のほかの部分で確認ができてガイドラインに入っていますので、先生方には今後機会があるごとにアレルギーに関する指導もやってまいりたいと思います。ガイドラインに沿ってその対応を取ってまいりたいと考えております。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 このガイドラインは、学校に1つなのでしょうか。それとも各教室に1つずつあるのでしょうか。ガイドラインが例規集みたいにあっても、これを全部読む方はなかなか少ないかと思います。大事なところだけポイントを押さえればいいわけですけれども、このガイドラインはやはり各生徒がいる教室に1つずつはあるべきだと思うのです。いざアレルギーショック症状を起こしたときに対応がすぐ取れるようにしていただきたいと思います。たとえ話でございますが、パイロットなどは何か緊急事態が起きたときには自分の知識に頼らず必ずガイドラインを見るそうです。そうすれば、自分の知識に頼らず、抜けている部分があるとか対応の仕方がしっかりと書かれているというところでガイドラインは利用されています。各教室にあるかどうか、またなければ置いていただく措置が取れるかどうか確認します。
○議長 中村 勝君 新垣好彦教育部長。
○教育部長 新垣好彦君 先ほどの学校アレルギー疾患に対する取り組みのガイドラインというのは、通達的なものでございますので学校にその配布がされていると考えております。それで各学級には置いていないと捉えています。議員さんから説明がありましたように、これはエピペンが必要なときの10分から15分ぐらいの応急的な措置でございますので、先ほどありましたように必要であればそういった措置を取ってまいりたいと思っております。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 ぜひこのガイドラインに関しましては、各教室が現場でございますので、校長先生が駆けつけるまでには時間が足りないかもしれませんし、ぜひその現場で使えるよう必ず配置をしていただきたいことを要望いたします。
それでは(4)人為的なミスを起こさない対策をどのように取っているかということで、調理人のこととか、また保護者と児童との話合いだとかそのへんが持たれております。これまたおっしゃられたようにいろんな関係者が集まってしっかりと対策、南風原町でそういった事故が絶対に起きないように、子どもたちは年々入れ替わって新しい子どもが入ってくるわけですからアレルギーも増えてきておりますので、本当にきめ細かな対応で大事な子どもたちを守っていただきたいことを申し上げてこの質問は終わります。
次に、子育て支援についてお伺いいたします。第四次南風原町総合計画後期基本計画における保育所入所定員は平成28年度1,260人を目途し、目標を設定していますが、既に平成25年度内に達成する見込みとなっており行政のご努力の賜物であり、保護者の皆様に喜ばれていることと思います。しかし、ここ南風原町は年々人口増加するわけでございまして、待機児童がゼロになることは厳しい状況があるかと感じております。先日、東京都で保育所不足で追い詰められた母親たちが立ち上がって抗議デモが行われたニュースがありました。景気の変動により家庭を維持していくためには夫婦ともに働かなくてはならない現実があり、母たちの助けを求める思いが伝わってまいりました。沖縄県の待機児童は、2012年4月で2,305人、最多の東京に次いで2番目に多く、人口比では沖縄の深刻さが飛びぬけているとの報告もあります。保育サービスの充実は緊急課題であります。そこで、本町の子育て支援についてさらなる充実を願いお伺いいたします。(1)平成24年度末までの待機児童は何人か。
(2)保護者の就労等で保育に欠け、保育所に入所できない児童を自宅等で保育する保育ママ制度を本町でも取り入れることができないか。
(3)保護者と行政や民間保育などのコーディネーター的役割を果たす保育コンシェルジュの配置で待機児童ゼロを達成した横浜市のような取り組みができないか。
(4)一括交付金特別枠を活用し、近隣市町村との連携による夜間保育園、夜間学童の見解をお伺いいたします。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 2番目の子育て支援についてでございますが、(1)です。平成25年3月1日現在で、待機児童が141人であります。そのうち保育に欠ける理由が休職で申し込まれている方が一番多くて45人ということでございます。
続きまして(2)の保育ママ制度とは、保護者が就労や病気などで昼間保育できない場合、そのお子様の家庭保育を行う者が保護者に代わって家庭的な雰囲気のなかで保育するもので、家庭的保育事業と言います。本町では現在の次世代育成支援行動計画では実施予定はございませんが、待機児童解消につきましては認可保育園の利用意向が高いのが現状であります。そこで当事業の実施につきましては、事業受託者の調査も含めて今後検討していきたいと思っております。
(3)でありますが、保育コンシェルジュとは、保育を希望する保護者の方々の相談に応じ個別のニーズや状況に最も合った保育資源や保育サービスの情報提供を行う保育専門相談員のことでございますが、本町の現状としましては、担当職員を中心に子育て支援班の職員がその業務を行っております。待機児童を解消したい思いは本町も同様でございます。公立保育園や法人保育園と連携し、これからも保護者の相談に丁寧に対応してまいりたいと思っております。(4)です。一括交付金を利用して夜間保育、夜間学童ができないかについてのご質問であります。厚生労働省の定めている夜間保育の要件としましては、開所時間がおよそ午後10時まで。運営形態として夜間保育専門の保育所または通常の保育との併設も認めております。定員が20名以上で、独立した保育所施設と、そして認可が必要とされております。夜間学童につきましては、当該事業では実施されておらず、開設時間の関係で他市で午後10時まで開園している学童クラブはあります。本町では午後8時半まで開設している学童クラブが1カ所ございます。しかし、同事業の実施につきましては、既存の補助事業がございますので一括交付金の活用についてはできないものだと考えております。以上です。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 ありがとうございます。待機児童が141人という数字にびっくりしておりますけれども、この141人の方はどうされているのでしょうか。本当に心が痛いことなのですけれども、今おっしゃっていただいた保育ママ制度は当初、この資格として看護師または保育士の資格が必要だったわけですけれども、2008年の児童福祉法改正によりまして家庭的保育事業として一つの研修を受けて、市町村が認定をしていく育児経験者がなれるものとなっています。88時間の講習を受けまして市町村が認定をしていく制度でございますので、最大3人から5人、補助者を付けて5人までは預かれるということで、先ほどもおっしゃっていたように待機児童の解消には手助けになるものと思います。そしてこの保育ママ制度の利用者は現在までに2,588人で、厚労省は2014年ですから来年度までには1万9,000人に増やす目標を掲げておりますので推奨をしているところです。また、子ども・子育て関連3法で、保育ママ制度に対しても給付金を支給することになっておりますので、ぜひ本町においてもこの制度の導入によって、また保護者の皆様にはいろんな選択肢ができて多角的な保育サービスになっていくのではないかと思われます。資格を持っている方、またやりたいと思う方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、ぜひ調査研究をして取り組んでいただきたいと思います。
また保育コンシェルジュのことですが、今でももちろん相談は受けていますし保育施設の増設や改築などによって待機児童をかなり減らしていっておりますけれども、横浜市の場合は保育所の定員は増えても待機児童の減少に至らなかった反省からこのコンシェルジュを置いたとのことです。コーディネート役として子育てサロンとかお母さんたちが集まる所に行って悩みを聞き、今は仕事をしたくても子どもがいるので仕事も探せない現状ですので、そういったところに例えばちょうど今やっているファミリーサポートセンターを紹介したり、認可外保育園のどこが空いているとか、または幼稚園での預かり保育をやっているとかそういう情報を意外と皆さんは知りません。どこに行って聞けばいいのということで、南風原町にはファミリーサポートセンターって素晴らしいものがあるのよとお話したこともあるのですが、以外と知りません。そういった情報を発信していく役割を果たす方です。去年ぐらいまででしたか、この方は自分で積極的に子育てサロンに出向いて行ってお母さんたちの困っている状況などをお話して、そこでまた悩みがあれば解決してあげる、紹介してあげてとても喜ばれていたのですね。この方が来て良かったということでありましたので、やはりこういった制度というのは必要ではないかと思います。ぜひ子育て世代の多い本町でありますので、多様なニーズに応えるために検討していただきたいと思います。
一括交付金の特別枠は、広域的に使用する目的のもので、先ほど一括交付金は使えないとのことでしたけれどもそれはどうしてですか。広域的にこういう事業をすることに使えないということですか、もう一度お願いします。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 再質問にお答えします。理由としまして、夜間保育や学童については、現在補助金がございます。補助を出して運営してもらっています。既存の補助事業については、基本的に一括交付金は使えませんということですので、これが広域であろうとどうであろうとこの事業は難しいであろうという判断です。そういうことで、広域でやるなり、単独でやるなり、一括交付金については事業外ですよということでございます。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 分かりました。忘れておりました。それでは、広域的にこの夜間保育または夜間学童をぜひ真剣に考えていただきたいと思います。今はいろんな職業の父母がいらっしゃいますし、また、母子家庭、父子家庭、家庭環境もそれぞれ違って、夜の時間帯に働く方は増えているのですね。看護師さんであったりお医者さんであったり、またはコンビニでの夜勤勤務、働く時間帯も夜中、明け方とか様々ですので、昼間働く父母には保育園があって夜働く人のために保育園がないのはどうしてでしょうかと思うのですね。同じ働く人の子どもです。例えば母子家庭のお母さんたちが夜勤のとき、兄弟若しくは一人で心細く留守番をしていて、なかには中学生ぐらいになると友達と遊び回るといった状況が沖縄では多々見受けられるところです。そのような非行に走る子どもたちも食い止めができますし、預かってくれる学童保育、または小さい子の夜間保育は今の時代必要なものではないかと考えますが、そのへんの見解はどうなのでしょうか。お願いします。
○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。
○民生部長 金城宏伸君 それでは、夜間保育、議員がおっしゃるようにそういう事業が必要だとは認識しております。県内で夜間保育を実施しているところが、沖縄市と那覇市と名護市の3カ所ございます。最初の答弁で話しましたように、定員20名以上で、これ以下になると経営する所も大変だろうということで事業自体が20名以上です。仮に20名以上ニーズがあると、あるいはまたそれを運営できる事業所と言いますか保育所があれば今後必要だと思いますけれども、今のところ町内であまりそういう声がありません。何名かはありますが、20名にはちょっと難しいかと思っています。その意味で近隣市町村でとのお話だと思いますので、協議はまだしたことがございませんがそういうニーズがあれば近隣で相談できるかどうか含めて、これまた市町村が変わって該当するのかどうか調べていませんので検討していきたいと思っております。
○議長 中村 勝君 12番 浦崎みゆき議員。
○12番 浦崎みゆき君 いろいろ課題はありますけれども、ぜひご努力をお願いいたします。今回、成立いたしました子ども・子育て関連3法の趣旨としては、子育て支援法では子育てに関して市町村の責任を盛り込んでいますね。今まで保育に欠けている子の義務でしたけれども、今回は保育を必要とする子どもたちに対して責務をかける法律になっておりますので、やはりそういう意味で言うと今お話をした夜間働く人たちの保育に対しては今後市町村においても責務が出てくるということであります。またこれまでの子育ては、家庭のことのみというような考えでやってまいりましたけれども、少子化になりまして子どもたちは社会全体で育んでいくのだという流れになっております。そういう意味からも、少子化問題は国の最重要課題であります。子どもを生んで安心して子育てをしながら働き続けられる社会づくりこそが政治の役割ではないかと思います。夜間保育、学童保育を望む保護者は少なくないと思いますし、先ほどおっしゃった那覇市、沖縄市、名護市が現実運営をしておりますので、課題はたくさんありますが今後の市町村の責務においてもしっかりとニーズに応えられるようによろしくお願いいたしまして終わります。
お問い合わせ
議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp