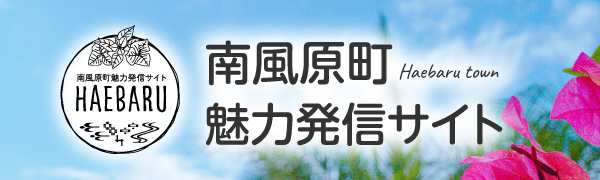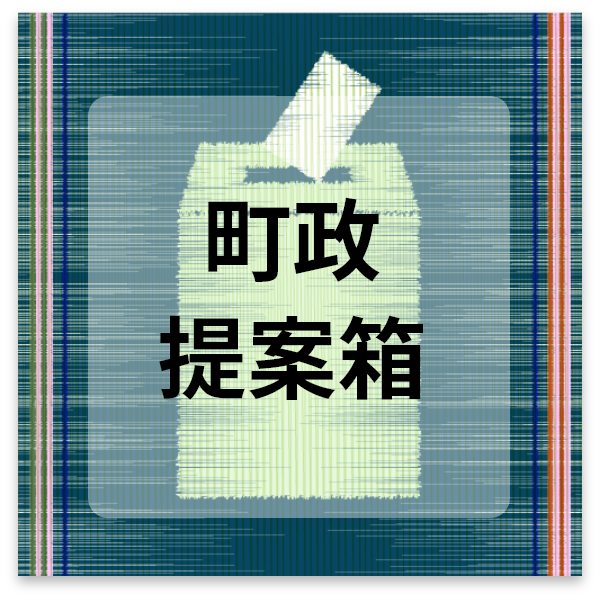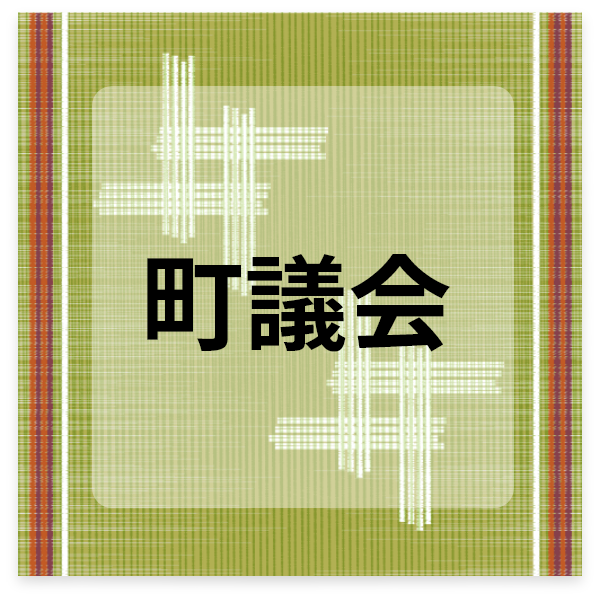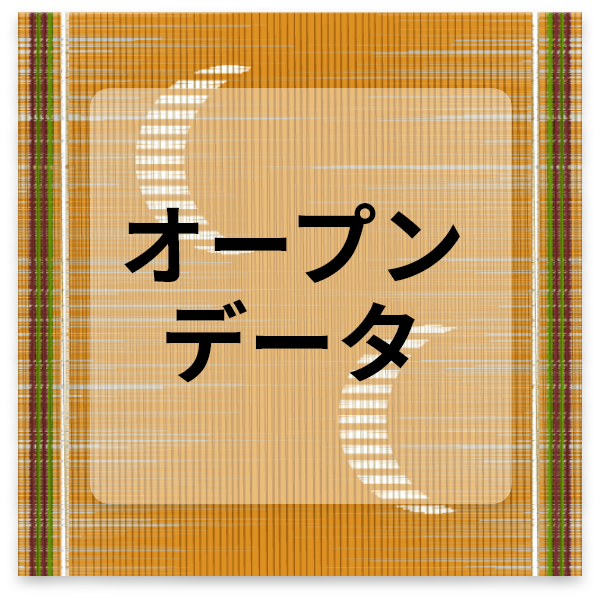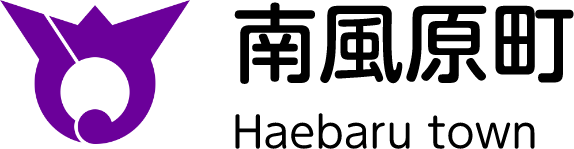本文
障がい福祉サービス・障がい児通所支援について
障がい福祉サービス・障がい児通所支援
個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と児童の発達支援を行う「障がい児通所支援」があります。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
サービスの種類と内容について
|
介護給付 |
居宅介護 |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上 |
|---|---|---|---|
| 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
区分4以上 | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 区分3以上 | |
| 同行援護 | 視覚障がいにより個人での移動が困難な方に対し、移動時およびそれにともなう外出先において必要な援助、視覚的情報の支援等を行います。 | 視覚障がい者の方のみ | |
|
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
区分6以上 |
|
|
短期入所 |
自宅で介護する人が病気の場合など、短期間(夜間も含め)施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上 | |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 | ※係に尋ねてください。 | |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創造的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
区分3以上 |
|
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分3以上 | |
|
訓練等給付 |
自立訓練 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
機能訓練 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | 2年間 | |
|
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
|
共同生活援助 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | ||
|
障がい児通所支援
|
児童発達支援 | 療育が必要な未就学児童(保育園、幼稚園)を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | |
| 放課後等デイサービス | 学校に就学している児童(幼稚園除く)を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 | ||
| 医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、医学的管理が必要な児童(小児発達センターや整肢療護園に通っている児童)を対象に児童発達支援及び治療を行います。 | ||
| 保育所等訪問支援 |
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として保育園等に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児を対象に障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
申請必要書類
申請時には、下記のものが必要となります。
(※新規申請の方の必要書類です。更新の方は、町からの更新案内通知に記載されている必要書類をご確認ください。)
| 障がい福祉サービス | 障がい児通所支援 | |
|---|---|---|
|
1 |
支給申請書兼利用負担額減額・免除等申請書 |
支給申請書兼利用負担額減額・免除等申請書 |
| 2 |
世帯状況・収入等申告書 |
世帯状況・収入等申告書 |
| 3 | ||
| 4 |
障害者手帳(身体・療育・精神)もしくは |
障害者手帳(身体・療育・精神)もしくは ※上記のいずれも取得がない場合、医師の診断書や意見書が必要です。 |
| 5 | 個人番号カードもしくはマイナンバーカード通知 | 個人番号カードもしくはマイナンバーカード通知 |
| 6 | 印鑑(認印) | 印鑑(認印) |
| 7 |
所得課税証明書(世帯全員分) |
所得課税証明書(世帯全員分) |
| 8 |
生活保護 被保護証明書 |
生活保護 被保護証明書 |
| 9 |
障害年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の受給額確認書類 |
障害年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の受給額確認書類 |
| 10 |
家賃証明書 |
在園証明書・通園証明書(多子軽減措置を申し出る方のみ) |
| 11 |
国民健康保険税の納付証明書 |
医療的ケアが必要な方のみ提出 |
※書類不備、記載漏れ等がある場合は、申請書を受理できません。不明な点などがあれば、福祉課(Tel:889-4416)までお問合せください。
※申請から支給決定までに約2ヶ月~3ヶ月程かかります。
※申請者の状況によっては、上記資料以外にも提出を依頼する場合がございます。
支給決定までの流れ
障がい者(児)の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において申請者の状況などを確認しながら支給を決定いたします。
1.申請
障がい福祉サービスの利用を希望する方(以下「申請者」といいます)は、町窓口(福祉課 3窓口)にて障がい福祉サービス・障がい児通所支援の申請を行います。
※申請に必要な書類は、上記申請必要書類をご確認ください。
2.計画案作成(※3.町による調査と同時進行します)
- 申請者は、特定相談支援事業所(児童の場合は、障害児相談支援事業所)と利用契約を行います。
(参考:計画相談事業所等は県のホームページから調べることができます。
障害福祉サービス指定事業所情報 )
) - 特定相談支援事業所(または障害児相談支援事業所)は、サービス利用計画案を作成し、町に提出します。
3.町による調査(※2.計画案作成と同時進行します)
- 町は申請者に対し、区分認定調査(福祉サービス利用)の場合、サービス利用の意向調査を行います。
- 介護給付のサービスを利用する場合、町は障がい支援区分認定審査会にはかり、障がい支援区分の認定を行います。
4.支給決定
町は計画案及び調査・認定結果に基づき支給決定を行い、支給決定通知書及び受給者証を申請者に交付します。
5.サービス利用開始
申請者はサービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。(※契約時には受給者証の持参が必要です。)
6.計画作成
特定相談支援事業所(または障害児相談支援事業所)は、「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画」を作成し町に提出します。
7.モニタリング
特定相談支援事業所(または障害児相談支援事業所)は、受給者証に記載されている期間ごとにサービス利用状況等を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。
利用者負担額について
原則1割の負担となります。ただし、所得に応じて上限負担額が決められています。
| 区分 | 対象となる課税状況 | 上限負担月額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給されている方 | 0円 | ||
| 低所得 | 市町村民税が非課税の方 | 0円 | ||
| 一般 | 利用者が18歳未満の場合 |
一般1 |
市町村民税額の合計が28万円未満 |
4,600円 |
|
市町村民税額の合計が28万円未満 |
9,300円 | |||
| 一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 | ||
| 利用者が18歳以上の場合 | 一般1 |
市町村民税額の合計が16万円未満 |
9,300円 | |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 | ||